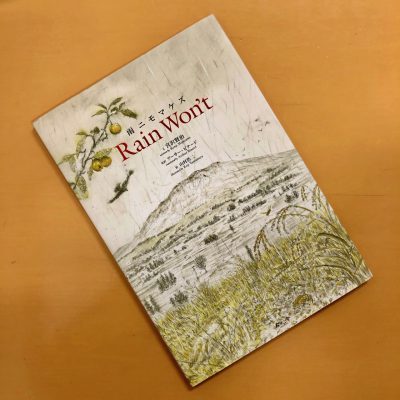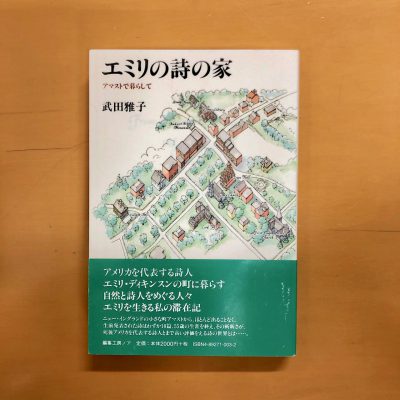宝石(鉱物)――エミリの場合・賢治の場合
武田雅子
ある時、自分の本棚の宮沢賢治の本を整理してみたら、あまりに多くが、文字通り、こぼれ落ちてきて、「あ、私はかなり賢治好きなんだな」と気づいた。そして、それが多くの分野にわたっていて、文学的観点からの本や論文もさることながら、宗教、科学、音楽、農学などなど、賢治の関心の広さに改めて感じ入った。そのさまざまな項目を解説した『宮沢賢治語彙辞典』は、『広辞苑』並みの厚さである(これを著したのが一人の人というのも、これまた圧倒されるが)。そして、美しい大判の、星と花と宝石の写真集のシリーズもありと、賢治の関心は、本造りの魂を刺激してやまず、魅力的な本が数多く出され、かくして私のコレクションが増えていったという次第である。

『新 宮沢賢治語彙辞典』原子郎著: 東京書籍(1999)/『定本 宮澤賢治語彙辞典』原子郎著: 筑摩書房(2013)
ところで、私は専門としては、アメリカの女性詩人、エミリ・ディキンスンを研究している。そして、何の交流もなかった、この二つの孤高の魂たちに結構共通点があることに気づいたのである。時代的には、エミリが1830-86年、賢治は、彼女の死後ちょうど10年して生まれていて、1896-1933年であるから、重なってはいないが、けた違いに異なった時代というわけでもない。
両者とも、全く中央の文壇と離れた田舎にいて、生前ほとんど作品は認められなかった。賢治の場合、草野心平との親交はあり、自費出版した詩集『春と修羅』は、佐藤惣之助の激賞を受けるが、童話集『注文の多い料理店』は生前出版された唯一のもので、しかもこれまた自費出版である。一方、エミリの詩は約1800編残されているが、生前発表されたのは、そのうち10編ほどで、しかも本人によるものではなく、すべて友人、知人たちが世に出したものである。そして、このようにほとんど無名であったが、死後から今日ますます評価は高まっている点も同じである。「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」という賢治の言葉は、世界が分断されている今の世の中、重さを増しているし、2011年、大震災の後、朝日新聞の「天声人語」に次のエミリの詩(中島完訳)が引用され、記者の自戒としているというので、話題となった。
失意の胸へは
だれも踏み入ってはならない
自身が悩み苦しんだ
よほどの特権を持たずしては―― (F1745/J1704)
何よりも、賢治は仏教、エミリはキリスト教という違いはあるが、自分なりに宗教を深く深く掘り下げていく追及心には激しいものがあった。その思いで世界を見渡してみると、実にさまざまなものが彼らの関心を引いた。エミリも賢治のように、広範囲な方面から研究がされている。
彼らの作品に花や鳥たちは欠かせないが、国による種類の違いから単純な比較検討は難しい。さて、それでは宝石はどうだろうと思いついた――つまり、二人の関心のあり方を調べて、何か見えてくることがあるのではないかと。そもそも私自身、宝石は装身具として見るより、石として、博物館などで、色や形を鑑賞するのが好きで、彼らの作品の中の宝石の使われ方が何かしっくりきていたということがあった。

宝石鉱物標本*著者私物
♦♦♦
エミリの場合は、詩の中に出てくる言葉すべてをabc順に並べたコンコーダンス(用語索引辞典)というものがあるので、どのような宝石が作品中使われているかを検索するのは、先行の研究もあることだし、それを参考にしつつ、それほど困難ではない。それで、彼女の方を基準にすることにした。賢治の方は詩だけではなく、童話を中心とした散文もあるので、出てくる回数を数えても、繰り返しなどのためあまり意味がない場合もある。ということで、彼の方は回数は挙げていない。
次が、作品に出てくる宝石と、それぞれの宝石の(エミリの)使用回数リストである。
エミリ・賢治共通の宝石
- 真珠 pearl (31)
- 琥珀 amber (23)
- ダイアモンド diamond (14)
- エメラルド emerald (12)
- ルビー ruby (8)
- 紫水晶 amethyst (6)
- オパール opal (5)
- サファイア sapphire (4)
- 水晶 crystal (3)
- トパーズ topaz (3)
- 玉髄(緑玉髄) chrysoprase (2)
- 瑪瑙 agate (1)
エミリの宝石
- bery 緑柱石
- garnet 柘榴石(ガーネット)
- chrysolite 貴からん石
- coral 珊瑚
- jasper 碧玉
- onyx 縞瑪瑙
- hyacinth ヒアシンス石 (風信子石)
賢治の宝石
- 月長石(ムーンストーン)
- 天河石(アマゾナイト)
- トルコ石
- キャッツ・アイ
- 孔雀石
- 黒曜石
- 黄水晶
- 翡翠
一瞥しただけで、二人の宝石好きがまざまざと実感できる。
♦♦♦
一つ一つの宝石の用例を見ていく紙面はないので、二人から数例ずつ挙げてみる。
まずは、エミリから――
宝石を 指の中にしっかり握って
眠りについた
その日は暖かく 風は物憂かった
私は言った「このままでなくなりはしない」目を覚まし 馬鹿正直な指を叱った
宝石がなくなっていたから――
そして今は 紫水晶(アメジスト)の思い出が
私の持っているすべて (F261/J245)
ここでなくした宝石、紫水晶が表わしているものは何だろうか。読む人それぞれの答えがあっていいと思うが、二度と帰らぬ子供時代か、去ってしまった恋人や友達か、失われた神や信仰といったものか。さらには、「物憂い」と訳した個所は、原詩の“prosy”に「散文的」という意味があるので、「散文」と対比される「詩」の世界で、手にしたと思った詩のインスピレーションを失ったとも読める。これは芸術家にしばしば訪れる苦しみ、悲しみである。
一方、賢治の「貝の火」からオパールの素晴らしい描写を引いてみる。
玉は赤や黄の焔をあげてせはしくせはしく燃えてゐるやうに見えますが、実はやはり冷たく美しく澄んでゐるのです。目にあてて空にすかして見ると、もう焔は無く、天の川が奇麗にすきとほってゐます。(中略)それはまるで赤や緑や青や様々の火が烈しく戦争をして、地雷火をかけたり、のろしを上げたり、又いなづまが閃いたり、光の血が流れたり、さうかと思ふと水色の焔が玉の全体をパッと占領して、今度はひなげしの花や、黄色のチュウリップ、薔薇やほたるかづらなどが、一面風にゆらいだりしてゐるように見えるのです。
エミリは朝焼け、夕焼けの描写に、ルビー、サファイア、エメラルド、オパール、そして先ほどの紫水晶をふんだんに使っているが、次は琥珀の例――
琥珀の帆船が乗り出していく
エーテルの海へ――
そして 深紅の水夫を穏やかに波間に消してしまう
この恍惚の息子よ
夕焼けの西の空全体がエーテルの海に喩えられ、そこに浮かぶ琥珀色の大きな雲は帆船。「深紅の水夫」は輝く太陽で、やがて沈んでゆく。太陽を最終行で「恍惚の息子」と言い換えているが、これはsun(太陽)とson(息子)を重ねた言葉の遊びである。そして、「息子」は「神の子」つまりイエスとなり、夕焼けの鮮やかさという光景を読んだ詩が、たちまちイエスの受難という宗教詩となり、「深紅」も「恍惚」も、その意味を帯びてくる。
同じく琥珀を賢治で見てみよう。
あけがたの琥珀のそらは凍りしを大とかげらの雲はうかびて (短歌)
正午の管弦よりもしげく
琥珀のかけらがそそぐとき (「春と修羅」より)
二人とも空の描写に使っている点は共通しているが、賢治の場合、冷え切っていく夕方のアカネ空は常に「黄水晶」で、しかも常に「シトリン」とルビをふっている。
「緑玉髄」という聞きなれない石を、エミリも賢治も使っていて、両者ともさすがに宝石好きの名に恥じない。エミリは、蜂の体の描写に「その胸は一個の縞瑪瑙/そして緑玉髄がはめ込まれている」と歌い、賢治は、「から松の芽の緑玉髄(クリソプレーズ)」とルビも振っている。
エミリは風のことを「エメラルドの亡霊」と名づけていて、死の不吉さの影を感じさせる。ゾクッとするような表現である。賢治は『銀河鉄道の夜』で、青と黄の星の光が重なって緑色になるさまをサファイアとトパーズを使って幻想的に描いている。
♦♦♦
二人の、こうした宝石への関心の根底には、まず宗教があった。エミリの場合、聖書の「ヨハネの黙示録」の玉座の描写、聖都エルサレムの描写が絢爛豪華なまばゆいばかりの宝石でちりばめられていて、強烈な印象を残していると考えられる。それに対して、賢治の方には仏教世界が読み取れる。例えば、「ダイアモンド」という言葉に対して、仏教と共にもたらされた「金剛石」という古い言葉を区別して使っているらしいということがある。そもそも「貝の火」や「十力の金剛石」は、仏教説話としての色彩が濃いものなので、中に登場する小道具も当然その色彩を帯びるわけである。
次に二人の根底にあったのが科学への関心である。これまでわかりやすい「宝石」という言葉を使ってきたが、実は、彼らの造詣が深かったのは、いわゆる「宝石」ではなく、鉱物に近い「貴石」の方だった(それもあって、賢治は宝石商になろうとしてなれなかったのであろう)。
ここまで、賢治の宝石に関しては、ほとんど板谷栄城著『宮沢賢治の宝石箱』によったのだが、この書ではさらに次のように述べられている――賢治が「トルコ石の空」というとき、それは「トルコ石のような空」ということではない。そこでは「トルコ石」と「空」のイメージが完全に一体となって、少しも間然とするところがない。
これは、エミリの場合も同じで、引用した紫水晶の詩において、「紫水晶の思い出」は、元の言葉では、“an Amethyst remembrance”で、冠詞“an”を取ると、あとは、“Amethyst”(紫水晶)と“remembrance”(思い出)という二つの単語だけである。この二つがぶつかり合って火花を散らしている。「の」の入る余地すらない。これはエミリの方が賢治より優れているというのではなくて、英語がそういう言語であるということである。両者のこの感じ方の切実さ、表現の切実さが、何ら影響関係のなかったはずのこの二人の、何よりも深いところで見られる共通点ではないだろうかと思われる。
♦♦♦
彼らは、中央とつながっていず、孤立していたからこそ、普通ではできない、そうした言葉の実験ができた。どう受け取られるかと、批評家や読者のことを全く考えなくてもよかったからである。
エミリの場合、まず表記自体普通ではなく、文法も破格になっていることが多く、翻訳する際、悩まされる。小さな例では、引用した紫水晶の詩の“prosy”をどう訳すかというのがあった。賢治の「雨ニモマケズ」は、最後の最後になって「サウイフモノニ/ワタシハナリタイ」と、やっと主語が出てきて、それがこの詩のポイントでもあるのだが、英語でそれに倣って訳すと、主語がすぐに必要な言語なので、ちょっと変な感じになってしまう。
このように、エミリを日本語に訳したり、賢治の英訳を読んだりすると、彼らの、それぞれ英語での、また日本語での、実験の大胆さに改めて驚かされる――時には、我儘と見えるまでに自分のやり方を貫いている。それで、彼らが直接語り掛けてくるように感じられるのである。最初あまりの変格な表現に驚くことはあっても、やがて、それこそが彼らの本質であり、魅力であるとわかる。詩人として、このことにおいてこそ、私の中で、孤高の二人の魂がつながっているのである。
- *引用した、エミリの詩の後の数字は、詩にタイトルをつけなかった彼女の詩の識別番号。Fはフランクリン、Jはジョンソンによるもので、それぞれ全詩集を編纂したディキンスン学者。
(1/11/2020)
読書案内

『宮沢賢治 花の図誌』松田司郎著, 笹川弘三写真: 平凡社(1991)/ 『宮沢賢治 星の図誌』斎藤文一著, 藤井旭写真: 平凡社(1988)/『宮沢賢治 宝石の図誌』板谷栄城著: 平凡社(1994)

The Poems of Emily Dickinson edited by R. W. Franklin: The Belknap Press of Harvard University Press
付記(3/21/2022)
鉱物は好きだが、あまりにも私の関心が、色とか形、文学作品に出てくる描かれ方といった皮相なものなので、少しは科学的観点からも見てみたいと、昨年、近くで開講された鉱物の入門クラスに、全9回通った。最初の3回のつもりが、熱心な同級生たちの要望で、次々とクラスは続き、また講義の後に実習が必ず入って、先生がなかなか面白くクラス内容を提供してくださったので、私も思わずつられてしまった次第。
その最後のクラスで「造岩鉱物(石をつくる鉱物)」として、黒雲母が取り上げられた。黒雲母は、酸性の火成岩にはたいてい含まれているが、岩石が風化するときは、まずこの黒雲母から風化が始まるとのこと。さらに、この風化を、宮沢賢治は「楢の木大学士の野宿」で次のように表現していると紹介された。(バイオタさんは黒雲母、プラヂョさんは斜長石。)
その時にわかにピチピチ鳴り
それからバイオタが泣き出した。
「あゝ、いた、いた、いた、いた、痛ぁい、いたい。」
「バイオタさん、どうしたの、どうしたの。」
「早くプラヂョさんをよばないとだめだ。」
「ははあ、プラヂョさんというのはプラヂオクレースで青白いから医者なんだな。」
(中略)
「なあにべつだん心配はありません。かぜを引いたのでせう。」
「ははあ、こいつらは風を引くと腹が痛くなる。それがつまり風化だな。」
鉱物の深い知識をこのように生き生きと童話に生かしているのは、賢治の面目躍如といったところ。他にも、童話の中に、賢治の鉱物への深い関心を伺うことができるのだろう。最近、『宮沢賢治の地学読本』『…地学教室』『…地学実習』(いずれも創元社)といった本が出ていて、読みたいと思っていたが、はたと気が付いたことには、これらの著者こそが、鉱物クラスの講師の柴山元彦先生その人だったのである。