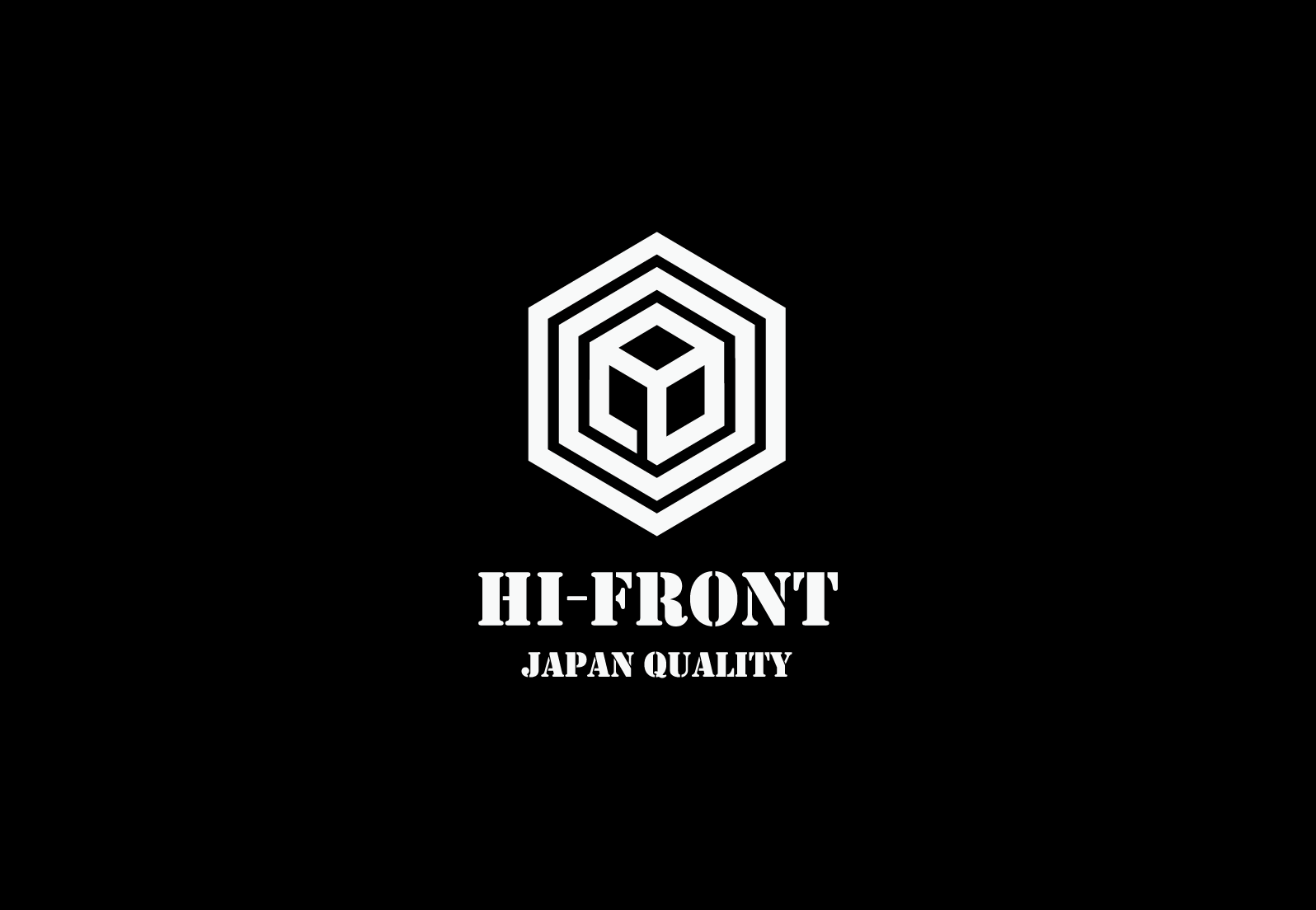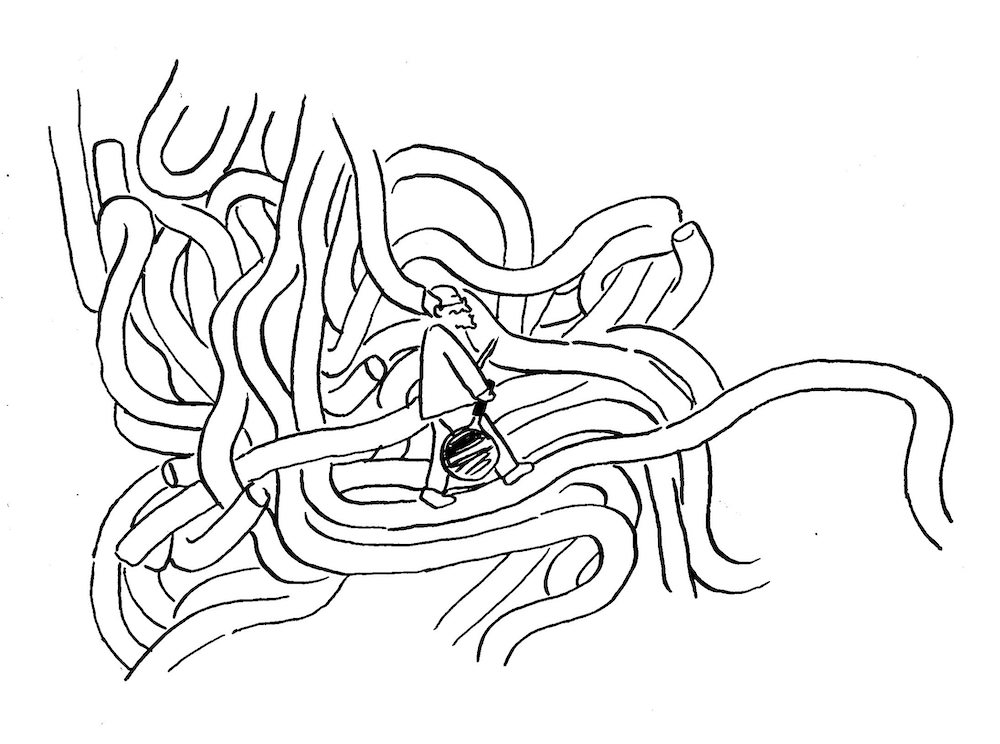
挿し絵:北林研二
その後のやきそば
週に一、二度、やきそばを作るようになった。
基本は土居善晴先生のレシピで、やきそばに焼き目をしっかりつけてかたい部分を作る。けっこう長い時間(といっても5分くらいだが)火にかけたまま放置する。箸でいじりたくなるが、「ほっといたらええの」という土井先生の声が頭にこだまする。我慢して、別の鍋で豚肉と野菜を炒めておく。ソースをからめて一丁上がり。その日に余っている野菜を使ってもうまいので、バリエーションには事欠かない。
ときどき、やわらかい麺も食べたくなる。知人に教えてもらった、ウー・ウェン先生の長ねぎ焼きそばのレシピがおいしくて、よく作っている。酒で蒸し焼きにしたあと黒酢をたっぷり入れるのがポイントで、まったく焦げのない、なめらかな麺の味わいが楽しめる(ウー先生といえば、昨年出た『10品を繰り返し作りましょう』もたいへんよかった)。
やきそば用のゆで麺は、バラで買うと一袋100円くらいするのだが、ときどき、スープ付き3食100円で売ってることがあって、安上がりだからとまとめ買いする。しばらくやきそば三昧になる。コロナ禍以後、昼も夜も家で作ることが多くなったので、じきになくなる。

ところで、やきそばの「焼き」問題の続きである。
前回、やきそばについて書いたあと、やきそばに関する二冊の新書が出ているのに気づいた。塩崎省吾『ソース焼きそばの謎』『あんかけ焼きそばの謎』(ともにハヤカワ新書)がそれである。やきそばの歴史を追って昭和・大正・明治と遡っていく、じつにおもしろい内容で、たいへん勉強になったのだが、この二冊のほんの始まりのところで、わたしは軽いショックを受けた。
それは『あんかけ焼きそばの謎」の第一章に記された次のようなくだりだ。
ところで、あなたが「あんかけ焼きそば」と聞いてイメージする焼きそばは、どんな麺だろうか? おそらく表面をパリッと焼いて、中は軟らかな麺を思い浮かべる方が多いと思う。(塩崎省吾『あんかけ焼きそばの謎』p.21)
じつを言えば、わたしはついこの間まで、やきそばを「ソース/あんかけ」に二分するという考えを持っていなかった。あんかけといえば、あんをかけられているのは全体を揚げた「かたやきそば」であって、それはやきそばの範疇ではなかった。「表面をパリッと焼いて、中は軟らかな麺」を意識し始めたのはごく最近のことだ。
これはもしかして、わたしだけなのかと思って何人かの関西の知人たちにきいてみたのだが、わたしと同様いわゆるカップやきそばや屋台、お好み焼き屋のやきそばのみを「やきそば」として認知している人がけっこういた。『ソースやきそばの謎』にも、近畿ではお好み焼きとやきそばとがしばしば同じ店で提供されており、「コナモン」と受容していたことが記されている。また、中華料理店でも、麺をかたく揚げたり炒めたりしない「上海風やきそば」を出す店があるため(このルーツがまた興味深いのだが、それに関しては『あんかけ焼きそばの謎』をお読みいただきたい)、必ずしも焼き目のあるやきそばに遭遇するとは限らない。あんかけやきそばを食べる機会じたいが、関西人には少な過ぎるのかもしれない。
このあたり、長らく東京に暮らす人にとってはどうなのか、比較してみたらおもしろいだろう。

ともあれ、どうやら、味のつけ方と麺の焼き方との結びつきにおいて「ソース:やわらか/あんかけ:焼き目または揚げ」という組み合わせが、現在わたしたちが体験するやきそばの、おおよその区分らしい。とすれば、土井先生のレシピである、焼き目を存分につけたソースやきそばは、現在の区分を越境した、ラジカルな料理だということになる。
さて、今週もやきそばを作ってしまった。焼き目をつけたやきそばの仕上げに黒酢を混ぜ合わせてからソースをかけると、小麦の味がひきたつことに気づいた。土井先生とウー先生のレシピの折衷だ。なかなかうまい。うまいが、わたしのやきそばのイメージはますます混迷を深めつつある。
(12/17/24)
これまでの「東京なでなで記」はこちらから