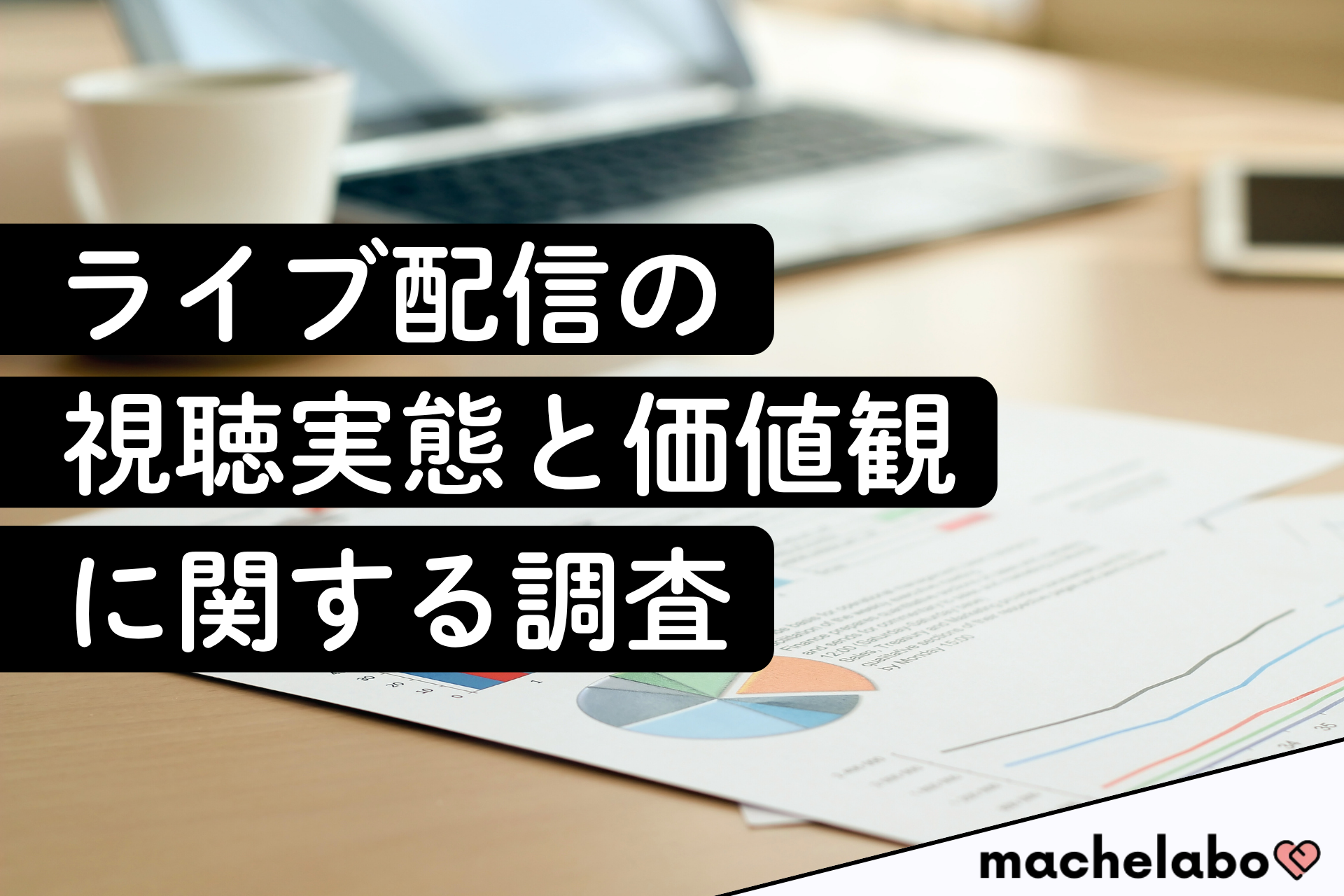「おしゃべり階段」
「おしゃべり階段」
地下鉄に下りる階段の踊り場に、「お願い」と題された表示があった。
「お客様同士の衝突事故が報告されております」
さもありなん。東京の地下鉄構内には、あちこちに上り下りや通行の左右を示す表示がある。しかし、実際には、守らない人が多い。うっかり表示を信じて歩いていたら、曲がり角でいきなりぶつかりそうになることもときどきある。
なぜ、わざわざ通行の方向が記されているのに、人々はそれを守らないのか。理由はおそらく、一つではない。
地下鉄の通行表示では、出口に向かう方が入口に向かう方よりも幅を広くとってあることがしばしばある。わたしがよく使う早稲田駅のある出入り口は、出口と入口が手すりで仕切られているのだが、入る方は人がぎりぎり一人分の幅で、出る方が三人分くらいある。理がないわけではない。一般的に地下鉄から出る客は列車の発着時に集中するから、人があふれやすい。だから、出る方の幅を多くとる一方で、入る人のために一人分でもスペースを確保しておく。これは朝やイベントの混雑時には確かにいい方法だ。
ただし、これに対して入る方も、いつも空いているわけではない。帰宅ラッシュの際は、むしろ街から地下鉄へ人がどっと入り込んでくる。一人分のスペースではとても間に合わない。こういう時間ではたいてい、出口向きの矢印は無視されて、上り用の通路を人がどんどん下りていく。
場所によって左側通行や右側通行になっているのも紛らわしい。鉄道駅は一般には左側通行だと言われているけれど、さまざまな路線が交差し、改札付近の人の流れが複雑な東京の地下鉄では、必ずしも当てはまらない。
だからこそ、いちいち通行方向の表示が記されているわけだが、それがしばしば地味なことも、理由の一つだろう。床にプリントされた白や青の三角印は、矢印に比べるとどちらを向いているのか曖昧だし、混雑時には見逃されやすい。さらに、年月が経つと人々の靴跡でどんどん薄汚れてすり切れていくので、曖昧さはいや増す。
曲がり角のある階段が多いのも原因かもしれない。特に長い階段の上り下りが苦しい人にとっては、外側を行くよりも内側を行く方が楽だ。たとえそこに自分の行きたい方向と逆のサインが記されていたとしても、つい内側を選んでしまうのも、無理はない。わたしは、階段を見上げながら、通行の左右にかかわらず、カーヴの少し外側を行くことにしているけれど、腰の調子がよくないときはつい内側を使ってしまいがちになる。
いまのところ、誰かと正面衝突して転んでしまうという事故にあったことは幸いなく、目撃したこともない。ときどきぶつかりそうになりながらも、どうにかこうにか切り抜けている。しかし、年をとっても、同じように切り抜けられるだろうか。
*
ある日、早稲田駅の改札で少しもたついていたら、もう次の列車が近づいてきたので、混み出す前にあわてて階段を上った。滋賀にいるときは、電車は少なくとも30分待つものだったから、ほんの3、4分で次が来るのは、便利を通り越してせわしない気がする。階段を曲がったところで、もう改札の方から列車の到着音がゴウゴウと響いた。
急に既視感に襲われた。
「おしゃべり階段」だ。
「おしゃべり階段」は、1970年代末、わたしがおそまきながら、くらもちふさこという作家の魅力に気づいた作品で、当時、何度も読み直したのだが、その後しばらく遠ざかっていた。読んだ人の誰もが思い出すであろう名シーンのひとつが、タイトルのもとになっている、過去にきいたさまざまな声が、列車の轟音となって階下からきこえてくる場面である。その場面と、わたしの感じたことは、まるでそっくりだった。
あの場面の前後は、どんなコマだっけ。幾たびもの引っ越しの末、「おしゃべり階段」は残念ながら手元になかった。それではと買い直して、問題のページを読み直して、はっとなった。
予備校生となった主人公の加南が、今度こそと受験した大学の合格発表に向かう。大学そばの地下鉄の駅を、加南は階段を息を切らしながら上る、そのときに、彼女は「おしゃべり階段」を見出す。それは覚えていた。しかし、わたしは加奈の志望校をすっかり忘れていた。それは「W大学」なのだ。ということは、彼女の上る「おしゃべり階段」は、W駅、すなわち、わたしが毎日のように上り下りしている、早稲田駅のことではないだろうか。
いや、「おしゃべり階段」には、早稲田駅構内であることをはっきり示すような、独特の景色は描かれていない。地上の出入り口にはただ「駅名駅」と記されている。地上に続く階段があり、地下から響く音があり、出口から差し込む光がある。それはさまざまな都市の地下鉄道に共通の風景であり、だからこそわたしたちはこのマンガで起こっていることを、想像することができる。「W大学」というのも、さまざまな大学に置き換えるための仮の記号ととるべきだろう。
地下鉄の轟音が階下からきこえるというのは、考えてみれば世界のさまざまな駅で起こっていることである。いままでこのようなありふれたできごとと「おしゃべり階段」を結びつけなかったわたしの鈍さの終着駅が、早稲田駅だったということなのだろう。
それでも、駅の階段を上りながら、地下の轟音をきくたびに、何か、聖地巡礼の現場にいるような、奇妙な臨場感に襲われる。主人公の加南はふと振り返って立ち止まり耳を澄ます。しかし、東京の駅の朝は、立ち止まるには混み合いすぎており、わたしは轟音を背中でききながら上る。
(9/14/22)