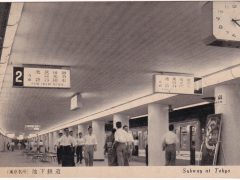子どもの時に読んで、今でも大好きな児童文学作品は、『小公子』、『ハイジ』、『くまのプーさん』などいろいろあれど、フランスのエクトール・マロの『家なき子』ほど、登場人物と一緒になってハラハラドキドキし、また熱い涙を流したものはないと言ってよいだろう。それほどだったから、今の私を作るのに大いにあずかったのではないかと思われる。
子どもの時に読んで、今でも大好きな児童文学作品は、『小公子』、『ハイジ』、『くまのプーさん』などいろいろあれど、フランスのエクトール・マロの『家なき子』ほど、登場人物と一緒になってハラハラドキドキし、また熱い涙を流したものはないと言ってよいだろう。それほどだったから、今の私を作るのに大いにあずかったのではないかと思われる。
賢治も『家なき子』か
門井慶喜氏の、直木賞受賞作『銀河鉄道の父』を読んで知ったのだが、宮沢賢治は子どもの頃、出たばかりの『家なき子』を先生が朗読するのを聞いて、いたく心打たれたらしい。6か月かけての朗読だったから先生の方も熱がこもっていた。『銀河鉄道の父』は、そのタイトルが示すように、賢治を父の目からとらえたもので、伝記で確認を取らなければならないのだが、とにかくこの本では、他の作品名はあがっておらず、ひたすら、この作品に惹かれたというように書かれている。
のちに、「私の命なんか、なんでもないんです。あなたが、もし、もっと立派におなりになる為なら、私なんか、百ぺんでも死にます」(「めくらぶだうと虹」)、「まことのみんなの幸のために私のからだをおつかひください」(『銀河鉄道の夜』)とまで思い詰める芽はここにあったのである。
あぁ、賢治も「家なき子」だったんだとなんだか腑に落ちた気がした。ただし『家なき子』が賢治を作ったというよりは、もともと彼には、そういう資質があって、それが、この作にビンビン共鳴したということなのだろうと思われるが。私は、賢治ほど真面目ではなくいい加減な人間なので、そこまで思い詰めたりはしていないが、子供心に、善いことはできないまでも、悪いことはしてはいけないと諭されたように思う。人は悪をなすつもりがなくても悪をなしてしまうということはあるだろう、しかし、意識して悪をなすことはならないと。

門井慶喜著『銀河鉄道の父』講談社文庫
『家なき子』のものがたり
このように深く影響を与えられた作品なので、かなり勝手なものになると思われるが、ひとまず、あらすじを辿ってみよう。
農村でバルブラン母さんと幸せに暮らしていたレミは、自分が捨て子であったと知らされ、無慈悲な義父により、旅芸人ヴィターリス老人に売られる。猿や犬たちと共に、町から町を行く巡業の旅はつらいものだった。猛吹雪の中、狼に襲われたりして、動物たちを失う災難も共にし、ヴィターリスは、レミに読み書きも人生も教えてくれる師となる。だが、その彼も、老体に鞭打っての苦しい旅で、遂に凍死してしまう。そして、じつは彼こそ昔は一世を風靡した大歌手であったことが分かる。
してみたら、旅芸人としての彼は落ちぶれた姿だったのか。いや、彼はそうは思っていなかったろう。かつての栄光の日々に、人々にちやほやされたことが本当の幸せか、それよりも真の自立、自由の生活の方がいい、自分がみじめだと思わなければみじめではないという誇りと矜持の気高い生き方が、子ども心にもこたえた。こうありたいと、今、ヴィターリスの年代になってしみじみと思うことではあるが、子どものときにすでにしっかりと刻み込まれたのであった。彼の力強い「さあ、出発だ」の掛け声が、私を励ましてくれた。
このヴィターリスが歌手であったという設定は、じつによく考えられたものだと思う。音楽家ヴェルディが作った「引退した音楽家のための憩いの家」があるが、歌手に特化した老人ホームも併設されていて、以前そのドキュメンタリー映画を見たこともある(1984年。スイスのダニエル・シュミット監督。記録映画ではあるが、彼独自の不思議で耽美的な視点による)。未だに、舞台に立っていたころのままにしなを作りながら歌う姿は、どこか異常な雰囲気があった。自分の声が音楽であった彼らは、楽器を演奏する音楽家よりもそれほど誇り高いのである。ヴィターリスは、その誇り高さはそのままに、他の余分なものは、旅巡業の生活の中で、剝ぎ落とされていったのだ。
さて、ヴィターリスが亡くなった時、レミも凍死しかけたのだが、花作りの一家に救われ、この貧しくとも暖かい一家の下でしばし幸福な時を過ごす。しかし、彼らの温室が雹でやられ、破産し一家離散ということになってしまう。なんという運命だろうと胸がふさがる思いがしたものである。そして、炭鉱の町で、他の人たちと共に生き埋めになり、暗闇の中でレミが命懸けで活躍し、まさに手に汗握るハラハラの連続。
以上のようなところが、子供の私に大きな印象を与えてくれたのだが、もう一つ、私は動物好きなので、犬のカピのことを省くわけにはいかない。レミがヴィターリスに売られるという、突然我が身に降りかかった悲しい事実に直面しベッドで泣いていると、カピがそっとレミの手を舐め、前肢を手の中に入れてじっと動かない。それでレミはひとりぼっちでないと悟る。ここは、犬の毛の感触や息が感じられて、犬って本当にこうだと思う。そして、老犬カピが最後に出てくるところも楽しい。大人になったレミと友人のマティアが巡業していた昔のように人々の前で演奏したとき、カピも昔のように、投げ銭を集めるべく受け皿の前に座る。「実入りのよさに目をまるくしながら」というところで、犬好きはもう涙ぐんでしまうのである。
子どもの頃の児童文学全集
こうして私が子どもの時に読み、何度も読み返した本は、今も手元にあって、講談社版世界名作全集の中の1巻である。中の紙や印刷は今日からすると相当粗末なものであるが、ハードカバーで1冊ずつ函に入っているという、豪華な造り。中には挿絵が入っていて、最初に入っている見開きの1枚と、箱の絵はカラーである。『家なき子』の最終ページに50巻までの目録が出ていて、もっと新しいものの後ろには88巻までのが出ている。学校図書館にはこれがずらっと揃えてあって、読書三昧に耽って、全巻読みたいとどんなに思ったことだろう。
私の持っているこのシリーズの中での一番古い初版は昭和25年で、終戦後5年にして、このような立派なシリーズが出始めていたということは、戦争を経験した大人たちが、次の世代の子どもたちの教育に希望を託した、熱い思いが伺える。同じ講談社からは、厚さはもう少し薄く、中の字は大きく、年齢を下げた読者層を対象とした、世界名作童話全集も出ていた。

世界名作全集 講談社版「家なき子」

講談社版・世界名作全集(左)と講談社版・世界名作童話全集(右)
5年ほどして、より本格的な世界少年少女文学全集が創元社から出ている。より本格的というのは、大きさの点でも厚さの点でもずいぶん大きなものとなっていてしかも2段組、全体を統一する表紙の色が、渋いピンク色で、子供心にも大人の本と同じ風格を備えていることが理解されるのだった。これは、初山滋装丁ということもあずかっていたかもしれない。また、講談社版ほどの堅牢な函ではないが、これも函入りである。これほどの整った児童文学全集はその後も出ていないのではないか。

世界少年少女文学全集(創元社刊)装丁:初山滋
ただ、紙と印刷は、それほど向上していない。その後、大きさといい、函入りといい、同種のものが3シリーズほど講談社から出て、やがて、より新しい作品を中心とした岩波版へと続く。これは大型本で、今も我が家にあるものについて辿ってみたのだが、子どもたちに良いものを届けようと、出版界は意気込んでいたことが伝わってくる。

少年少女世界文学全集(講談社刊)

世界童話文学全集(偕成社)

岩波少年少女文学全集(岩波書店)
大人も名作全集
その頃、大人の世界文学全集、日本文学全集、美術全集、百科事典など、いずれも狭い日本の家屋で、函入りというのは、まとまればそれだけでも場所取りなのに、教養ある家を表わすものとして、できるだけ見た目立派にと、飾りになるにすぎないケースも多々あっただろうに、競って出版されたものである。しかし、こういうスタンダードなものを何とか身につけたいという思いは、それはそれで熱く貴重だった。だから、これで育った私たち世代は、学生の頃、友人たちと、読書会をしたり、感想を熱心に語り合ったりしたものである。
だが、やがて、こうした風潮への反省点や批判も言われるようになった。ここでいう「世界」とは、日本が明治のころから追いつき追い越せと頑張ってきた対象としての欧米であって、真の意味での世界の視野が欠けているとか、規範として選ばれた名作群、すなわち「キャノン」(canon) は権威主義によりかかったものではないかということである。
前者に関しては、その後南米やアフリカ、アジアにも目が向けられるようになったことは喜ばしい。後者に関しては、今やキャノンを離れ、どんどんサブカルチャーが幅を利かせるようになってきて、大学生ですらドフトエフスキーの名を知らないというようなことも珍しくなくなってしまった。これはやはり憂うべきことではないか。キャノンはキャノンなのであって、サブカルチャーはどうしたって「サブ」なのである。人生の深いところまで描いた作品について仲間と語り合うということは、特に若いうちにあってほしい。
最近、光文社文庫や新潮文庫を初めとして、名作の新訳がいろいろと試みられているのも、こんなところからだろうと思われる。原作はそのままであり続けるが、翻訳は時代と共に古臭くなる。その古臭さのゆえに、名作への距離感があるのだとしたら、あまりにもったいない、出版業界としてやるべきことがあると、戦後すぐにあった熱い思いに似た使命感が再燃したかのよう。
原題「サン・ファミーユ」は「家なき子」にあらず
さて、私の講談社版『家なき子』は、8版で、発行年からすると3年生の時に初めて読んだことになる。中学校くらいまでは読み返したとしたらこの本で、その後は、子供の時の大事な本として本棚に並べてあるだけで、もう読んではいない。
いずれにしても、その最初の時だったのか、その後のいつかはわからないが、内容に心を捉えられていた他に気になっていたのが、解説にあった「原名は『サン・ファミーユ』といいます。ただしく訳すると『家なくて』というのであります」という情報だった(ただしくというのはすこしそぐわなくて正確にということだろうと思われるが)。本当にそうなのだろうかと疑問を抱き、大人になってフランス語が読めるようになったら、確認してみようと決心したのである。
大学に入ってフランス語を取ったので、これはすぐに難なく分かった――英語でいうところの”without family”なのであった。長年の疑問氷解だった。そして、日本語の「家」は、建物としての「家」も、また「家族」をも指すので、「家なくて」でいいのだが、厳密に言えば、「家族なくて」である。捨てられた子が本当の母親を捜し歩くのだから、「家族」がないということだが、「家なくて」という日本語訳は、定まって住む「家」もないという意味も含む。
そこで、最近、一定の居住地がなく、住まいをしばしば替えて暮らしている人たちはaddress hopperと命名されているようだが、わかりやすく「家なき子」と称されてもいる。人々は、必ずしもこの作品を読んでいないだろう。それでもこのタイトルが、こんな形にせよ今日まで生きているのは、翻訳のタイトルにインパクトがあったということで、ただしくはなくても名訳だったことになる。この訳語は、講談社版よりも前に、すでにつけられていたもので、そう考えると、相当の歴史を持っていることになる。ついでながら、明治に成された初訳では「未だ見ぬ親」であった。
完訳本が、令和に新訳で出版される
先ほど触れたように、名作新訳は、新潮文庫では“Star Classics”名作新訳コレクション―としてすでに30冊ほど、そして令和元年に、『家なき子』が、上下2冊の完訳としてこのシリーズに登場する。大人になって初めて読むのが完訳というので、やっとこの作品の本来の形を知ることになると楽しみですぐ求めた。といっても、手に入れたらいつでも読めると安心してしまって取り掛からずにいた。それが一気に読了することになったのは、新作映画が来ると知ったからだった。
昔、大学生の頃に映画化されたものを見た記憶があり、悪くはなかったが、特に印象に残るものではなかった。名作の映画化というのはほとんど満足することはないのだが、やはりどのような形になっているのかは知りたいし、それならその前に作品そのものを読んでおきたいと思ったのである。

「家なき子」〔上・下〕エクトール・マロ著 , 村松潔訳 新潮社刊
この新潮版解説によると、これまでも「全訳は少なく」とあり、これで初めてというわけではなくて、講談社版の解説に、当時は岩波文庫に完訳があったことが記されている。抜粋・抄訳ということになると、レミに焦点があてられることになるが、全体像としては、もっと当時の社会、庶民の生活が生き生きと描かれていることが分かる。さらに、これも当時の在り方のそのままということで、児童虐待ともいうべき過酷さも見逃されてはいない。
ところで、新潮版にそのまま取り入れられている、原書の挿絵はギュスターブ・ドレの版画ばりのすばらしさだが、その時代の空気をよく伝えている。あとで触れることになる原書の場合、表紙は、この絵をうまく取り入れ、格調高いものとなっている。

プロシャとの戦いに敗れ、国土が疲弊した有様を見て、その再建を考えたある編集者が、マロに持ち掛けたのが、フランス中を旅する子供の話だった。それで、講談社判にも地図は付いているが、全エピソードが紹介されてこそ、地図が本当に生かされることになる。
映画『家なき子-希望の歌声』
今回の映画化(『家なき子 希望の歌声』監督:アントワーヌ・ブロシエ 2018年 公式サイト)は、副題が表わしているように、レミの美声がヴィターリスにより見出されるということになっていて、それはいいとして、ヴィターリスがヴァイオリニストになっていることにどんな意味があったのだろう。上で触れたように、私にとっては、彼は歌手でなければならなかった。また、私にとって重要な、炭鉱の話、花作り一家の話が全く出てこないのは、大いに不満であった。
とはいえ、前者は、ことが大きくなり、全体の強い印象としてそちらに取られてしまうし、後者は登場人物が増えすぎて、これもテーマが絞られにくくなるという危険性はある――と、映画と小説という手段の違いを考えれば、無理ないことかもしれない。
その分、映像でこそ見られる風物は美しいし、舞台をイギリスに移してから、レミを捨て子にした張本人をはじめ、財産をめぐっての大人たちの醜い争いの方に重点が置かれている。これは、レミの運命やいかにと、見る者をドキドキさせるための流れでもある。原作通りというのも芸がないというわけか、実の母や、最後にレミと結ばれるリーズの出し方は変更してあり、これはなくもがな。ヴィターリスのダニエル・オートゥイユは、さすが名優の貫禄。全体の物語を語るのは、老年のレミという設定でこれまた名優のジャック・ぺランが演じていたが、これも映画なりの工夫と考えられる。
音楽家のリスト登場
話が前後するが、完訳本のずっと前に、じつは原書を見ていた。もう一昔か二昔か前になると思うが、以前、梅田阪急百貨店には、書籍部があり、しかも洋書も売っていた。1966年刊の『家なき子』の原書を見つけたのは、ここだった。2冊本だったから、それからしたら講談社版はかなり省略されているのが分かって、読みたいと思ったが、その頃にはもう就職していたので、辞書を引きつつ読むような時間とてなく、少し気になるところをパラパラ見た程度だった。

Sans famille[I][II] Hector Malot, 阪急百貨店書籍部のカバー(左右)
ただ、最後に楽譜があった。「あの(思い出の)ナポリの民謡を私(主人公レミ)より優れた音楽家の(友人)マティアが書いてくれた」というもので、その楽譜を音にして辿ってみて驚いた――私はこの歌を知っている! リストのピアノ曲「タランテラ」の中間部がそれだった。
今ピアニストとなった妹の子どものころの発表会で、妹の先輩がこの曲を弾いた、私たちはレコードも持っていた。リストの組曲『巡礼の年』に〈第2年:イタリア〉があるが〈第2年補遺:ヴェネツィアとナポリ〉として出たものに3曲が含まれ、その第3曲目が「タランテラ」である。
タランテラは、ワルツやポロネーズといった舞曲の一つで、名の由来は、毒蜘蛛タランテラに嚙まれて狂ったように踊るというのを模したからという説もあるが、この曲はそういう狂気を思わせるものではなく、急速な指の動きによるテクニックを要するものということである。これが、3部形式の最初と最後の部分で、中間に、素早い動きの前後とは対照的な、ゆるやかな民謡が置かれている。歌詞を知らなければ、旋律としてはそれほど切ないものでもなくて、昔懐かしいような物憂く甘い曲想に身をゆだねてしまうおだやかさを持っている。
この〈ヴェネツィアとナポリ〉3部作は、二つの町の自然から受けた感興を曲にしたものであるが、それぞれの町にかかわりのある旋律が取り入れられていて、このナポリ民謡は、ギョーム・ルイ・コットウ(一説にはジョヴァンニ・ボノンチーニとも)の作曲になるカンツォーネとのことである(CDのライナー・ノートより)。

Liszt: Piano Works Vol. 6 – Venezia e Napoli; Ballade No. 2 Jorge Bolet
この民謡を、レミはヴィターリスに習い、巡業の時には、おはことなっていて、旅先で凍死しかけたところを救ってくれた花作りの一家にも演奏して聞かせた。一家の末娘のリーズは口がきけないというハンディを持っていたが、レミのこの演奏をとても気に入り、二人は大の仲良しとなる。しかし、その後、数奇な運命の下、二人は別れ別れになる。
物語の終わり近く、ある時、門の鉄格子の前で、レミがこの歌を歌っていると、背後の塀の向こうから、弱弱しく歌う声が聞こえる。誰の声だろう。「そこで歌っているのはだれ?」すると、その声が答えた。「レミ!」――ものが言えなかった子が突然話すようになるというのは、いかにも小説的な展開なのだが、ここでのリーズとの思いがけない再会は、曲がもたらしてくれたということもあり、大好きな場面だった。その曲が、知っているものだったというのは、何かいっそう印象を深めてくれるように思え、うれしかった。
そして、同時に、ナポリ民謡(イタリア)をはさんで、フランスの作家マロと、ハンガリーの音楽家リストが結びつき、ヨーロッパをひとまとめにする大きな文化圏というものを感じたのだった。最終的に、レミは、イギリス人ということになるのだし、ヴィターリスはイタリア人であり、もともとこの物語はそういう大きな視野を持ったものだったのである。
ポエトリーの登場、そしてママン
原書の楽譜の中にも、歌詞は印刷されているのだが、ナポリ民謡だからイタリア語である。フランス語とイタリア語は似ているとはいえ、原書を読むフランス人がどこまでこの歌詞を理解していたのだろう。新しい完訳本には、ちゃんと訳も付いているので、じつは日本人の方が分かったことになるのでは……
その訳を引用してみる。
つれないひとの低い窓辺で
わたしはどれだけため息をついたことか
わたしの心はロウソクのように燃え上がる
美しいひとよ、あなたの名前が聞こえるときああ、雪になってはくれまいか、
雪は冷たいけれど、手でさわらせてくれるのだから……
あなたはなぜこんなにきびしく、残酷なのか?
わたしが死にかけているのに、助けようともしてくれないなんて……わたしは少年になって、
水がめをもって、水を売りに行きたい
そして、このお屋敷街で叫びたい
「美しい御婦人のみなさま方、水は要りませんか……」上のほうから美しいひとが姿を見せて、
「あの水売りの少年はだれなの?」と訊いたら、
わたしは慎み深く答えるだろう
「これは水ではなく、愛の涙なのです……」
これは美しい女性に片思いをして、彼女のつれなさを嘆く男性の歌である。こういうテーマは、特に民謡によく見られるものでもあり、作者も曲は曲として取り入れただけで、フランス語訳を入れなかったのも、べつに歌詞にはあまり留意していなかったからかもしれない。しかし、最後に置かれてみると、やはりこの作品は、恋愛に限らず、広い意味での「愛」の物語だと言えるのだと改めて気づかされる。
師弟愛も友愛も動物と人との愛も描かれている。そしてなんといっても母恋—―全篇、実の母を求めての旅なのであるが、8歳まで育ての母が実の母だと思っていたとあるからには、そのバルブラン母さんも生母に劣らず大切な母である。イギリス人の金持ちの貴族のマダムが実の母でした、というのは、ある種、子どものための物語の「めでたし、めでたし」という着地点であって、バルブラン母さんの意味こそが真に求めていたものかもしれない。
講談社版で読んでいたとき、私の身近にそのような呼び方をする人がいなかったせいだろう「おっかさん」とあるのが、心に残っていた。訳としては、ちょっと、田舎の感じを出すためもあったのだろう。フランス語では、もちろんmamanママンである。
今回、映画を見た後、また別の映画を見たおりに、この映画の予告編がはさまっていた。これが日本語吹き替え版で、レミがヴィターリスに売られ、村を離れるときに、遠くにバルバラン母さんの姿を眼にし、声は届くはずもなく空しく「ママー」と叫ぶ場面があった。この「マー」というのは、外に開放して出る音だが、字幕版で見た時、「ママン」の「マン」は、内にこもって、本当に切ないまでに甘い音だったのを思い出した。ここに、この物語のエッセンスが集約されている。
(3/22/2021)