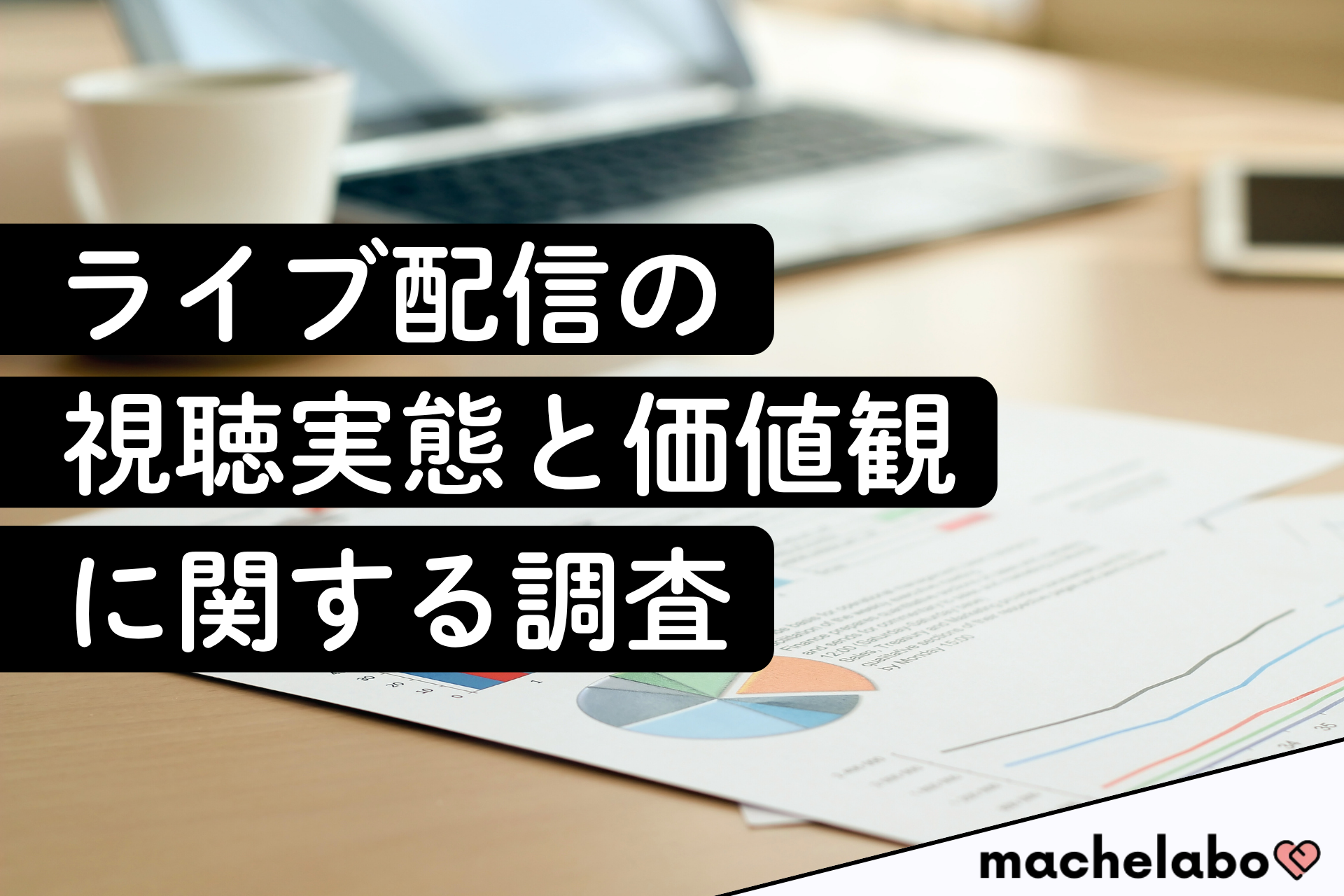どこの国にも永遠の青春文学というものがある。ドイツなら、一昔前はシュトルムの『みずうみ(インメンゼー)』、次の世代はヘッセだろうか。だったら、日本は何だろう。“永遠の”をつけなければ、聖地巡礼が行われているアニメ作品や、村上春樹作品なのだろうが、“永遠の”をつけたいとなると……。
昔は『伊豆の踊子』とか、もっと前になると『野菊の墓』もあるだろうか。私は『たけくらべ』を押したいのだが、納得してもらえるやら、今はタイトルすら認識されていないかもしれない。
しかし、フランスの永遠の青春文学と言えば『モーヌの大将』ではないだろうか。ラディゲの『肉体の悪魔』は反道徳的だし、『青い麦』は作者コレットが長生きしたので作品も多く焦点が絞りにくい感がある。それからすると『モーヌの大将』は、作者が28歳で第1次世界大戦において戦死していて、これがほぼ唯一の作と言ってもいいというところが、これまた永遠の青春文学の名にふさわしい。
*
パリからずっと南、森と沼のソローニュ地方、ここの寄宿舎にいるのが語り手の、校長の息子フランソワである。そこへ、転校生モーヌがやってきて、大柄な彼は兄貴分として皆の人気者になる。ところがある日、モーヌは失踪、数日後にようやく戻り、フランソワにだけ、その時の出来事を語った。
彼は、森の中の城のような邸宅での幻想的な結婚式に迷い込み、そこで花婿フランツの姉イヴォンヌと運命的な出会いをしたのだった。しかし、モーヌは邸宅への地図を失った。イヴォンヌと会えぬまま時が過ぎ、やがて彼女がパリに行ったことを知る。パリに彼女を探すがうまくいかず、別の女性ヴァランティーヌと一夜を共にする。その後、イヴォンヌと出会い結婚するも、ヴァランティーヌはじつは、フランツとの結婚式を捨てた女性だと知り、フランツとヴァランシーヌの仲を取り持つべく、また罪の意識もあり、イヴォンヌのもとを去る。その間、イヴォンヌは、フランソワの助けを借りて女の子を出産するが、産後の肥立ちが悪く亡くなってしまう……。
私はこれを55年くらい前の大学生の時、角川文庫の水谷謙三訳(初出は戦前の1938年。戦前にはほかに那須辰造訳もあったとのこと)で読んでいる。その後、旺文社文庫からも田辺保訳で出ていたらしいが、いずれも消えてしまって30年近くにもなり、残念に思っていた。ほかのいくつかの青春文学も同じ運命をたどっていたが、この本だけは出し続けてほしいと願っていただけに、1998年、宮沢賢治研究で知られた天沢退二郎訳『グラン・モーヌ』として岩波文庫に入った時は、とてもうれしかった――もうこれで消えることはないと。のち、2005年にはみすず書房より長谷川四郎訳が刊行される。これは1952年版の復刻である。

左:アラン・フルニエ著 水谷謙三訳『モーヌの大将』1938年, 角川文庫 右:天沢退二郎訳『グラン・モーヌ』1998年, 岩波文庫
原題は冠詞つきで “Le Grand Meaulnes”。英語で言えば “The Grand Meaules” — “grand” は「大柄、背高」ということで、讃嘆の気持ちも含まれ、フィッツジェラルドのThe Great Gatsbyのようなものだろうか。ただ『モーヌの大将』という日本語のタイトルだが、“大将”というと、飲み屋での呼びかけみたいで、この訳のタイトルが、日本の読者を遠ざける一因となってしまっているようで、何とかならないものかと思う。今なら「モーヌの兄貴」「モーヌあにい」というところだろうが、これではタイトルにならないし、別の世界を連想させてしまわないとも限らない。それならいっそということで岩波版もみすず版も「グラン・モーヌ」になったのだろうが、このカタカナばかりのタイトルも何を示しているのかわからず、これまた読者を遠ざけてしまっている。タイトル一つでもむずかしいものである。
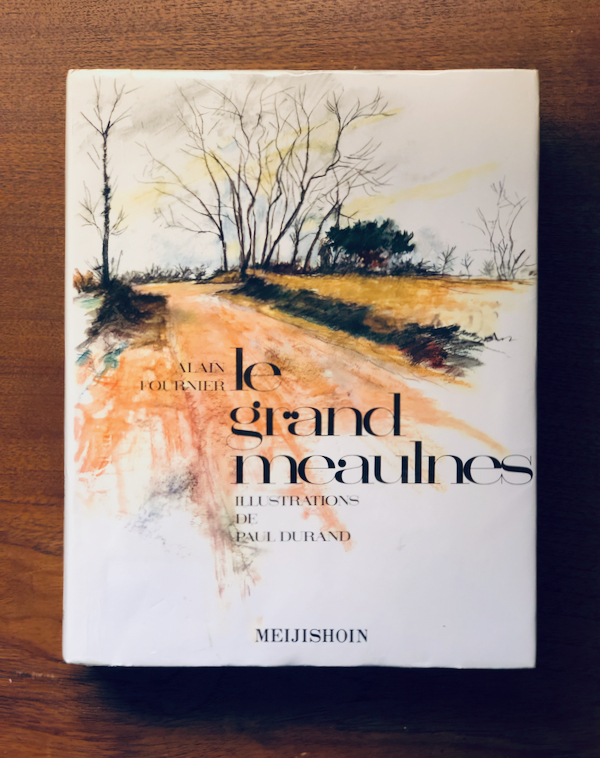
鈴木壽一, 関戸嘉光, 渡辺康 訳 ポール・デュラン絵『ル・グラン・モーヌ』1985年、明治書院
広くは行き渡らなかったと思うが、じつは1985年に、まさに永遠の青春文学という冠にふさわしい日本語版が出版された。原書にある24点もの美しい挿し絵も入った、明治書院刊の豪華本である。訳者として名があがっている鈴木壽一、関戸嘉光、渡辺康の3氏は、昭和7年(1932年)、明治の香りがする漆喰壁平屋建ての一高の校舎で、フランス語入門の授業を受けた。夏休み前に初歩の文法を終え、9月から読まされたのがLe Grand Meaulnesで、教師は、私もその名をフランス文学の世界で多く見ることになる、若き日30歳の川口篤先生だった。
初歩の文法の知識だけでは難解だったと訳者が「あとがき」でいうのも無理はないだろう。しかし内容の面白さに惹かれたという。
「登場する人物がちょうど私たちと同じ年ごろの若者であったし、その若者たちが取り組んだ問題がちょうど私たち自身の問題でもあったからだろう。少年の空想の世界から大人の現実の世界への意向の時期に、必ず一度は通過しなければならない形而上学的問題がテーマになっていたからであろう」
その学生時代から50年、若いころへの懐旧の思いから、先生への謝恩と若き日の記念のために翻訳を思いたち、同級生たちの協力のもと、川口先生の没後10周年の年に出版にこぎつけたのである。出版の裏にあるエピソードも、まさに「永遠の青春文学」そのものである。こんなふうにして世に出る本も幸せだと思うが、それは原作そのものの持っているたたずまいが生み出した力であるといえようか。
私はこの本は新聞広告で見て、買うべきだと直感したのだが、よくぞ気づいたと今にして思う。そして、本は、本当に欲しい人の所に来るものなのである。今回、『星の王子さま』つながりで、『モーヌの大将』を扱うと友人に話したところ、10歳ほど年下の彼女が「私、とてもきれいな本を持っているんですよ」と、この本に言及したので驚いた――彼女はいかにしてこの本にたどり着いたのだろう、本が欲しい人の所に行ったとしか思えない。彼女はこの作品に着想を得た映画『わが青春のマリアンヌ』のテレビ上映を録画して持っているとも言った。
なお、この本のタイトルは、訳読の授業から生まれたものだけに、律儀に冠詞もつけて「ル・グラン・モーヌ」となっている。
「表題では(略)難航した。原題をただ片仮名書きにしただけでは訳書として不合格であるばかりでなく、読者にも不親切に過ぎるので、作品の内容を象徴ないし暗喩する何か適当な訳題をと考えたのだが、ついに最後まで、これはと思う題が思いつかず、心ならずも副題をそえるにとどめざるをえなかった」
「あとがき」にこう書かれていて、この作品のタイトル問題はなかなか厄介であること、つまり翻訳とはただ単に訳せばいいというものではないということを如実に伝えている。ちなみに、苦心の副題は「若き日のバラード」である。
*
これほどの作品なので、映画化が考えられて当然だろう。『にんじん』『望郷』『舞踏会の手帳』で知られるジュリアン・デュヴィヴィエもその一人だった。しかし、作者の遺族が、映画化によってイメージが固定してしまうことを恐れ、版権を盾に、首を縦に振らなかったらしい。人々の心にそれぞれのモーヌ像があるだろうに、そしてそれはそれぞれの人にとってこの作品そのものがいとしいように大事なものだろうからと。それでも、諦めきれないデュヴィヴィエは似たストーリィの本を映画化するしかなかった――それがドイツ/フランス合作の『わが青春のマリアンヌ』Marianne de Ma Jeunesse (1955)である。
確かに、設定は類似したところが見られる――男の子たちの集団である寄宿舎で、そこに新入生ヴァンサンがやってくる。アルゼンチンからやってきた少年は、別世界からの旅人の雰囲気をまとっていて、たちまち皆の心をとらえる。ある時、彼は湖の向こうの霧の城を訪れ、そこでマリアンヌと出会う。彼女は、厳粛な、はるか年上の騎士によって捕らわれの身であるというのだ。ヴァンサンの物語は皆のあこがれの思いをかき立てる――ヴァンサンの恋が伝染したかのように。
どうしてもまた会わなければと再び城を訪れたヴァンサンにマリアンヌは、騎士により結婚式の準備がされていると訴える。しかし、騎士は別の物語を告げる――自分は、彼女を束縛している騎士ではなくむしろ彼女の庇護者であると。以前、マリアンヌは結婚式を目前に婚約者が失踪してしまい、それ以来、気がふれてしまった。それで、その時と同じ状況をつくって式の準備をすれば、正気に戻るきっかけになるかもしれないと言うのである。ヴァンサンはそう聞かされて、城を追い出される。その後、土地の祭りで、馬車で連れ去られて行くマリアンヌを見かけたヴァンサンは、彼女を探すべく旅立つのだった。少年たちの中で最年長(18歳)である語り手の「私」も、彼を見送る生徒たちの中にいた。
この2作は、テーマも求めてやまぬ青春の憧れということで、ほとんど同じといえよう。しかし『わが青春のマリアンヌ』の物語は、『グラン・モーヌ』の前半だけという大きな違いがある。それで、似ている前半の、それでも存在する相違、そして『グラン・モーヌ』だけが持つ後半の意味を考えることで、それぞれの作品をよりよく知ることができるだろう。

メンデルスゾーン著 岡田真吉 訳『わが青春のマリアンヌ』1969年, 田園書房(三笠書房)

挿し絵は映画のスチール。
数年前、倉敷の古本屋で、『わが青春のマリアンヌ』の原作の翻訳を見つけた――あるのを知らなかったので探していたわけではないが、これも本の方からやってきた一例だろう。原題はSchmerzliches Arkadien (苦しみの高原-としてあるが、「アルカディア」は「理想郷」で、あえて「苦しみ」と相反する語をタイトルに持ってきたのだろう)で、ドイツのペーター・メンデルスゾーン作である。多くの場合、原作があってそれを映画化されるとがっかりすることが多いが、これは映画が原作をうわまわるケースではないだろうか。この物語の全く荒唐無稽な幻想に実体感を持たせるには、映像というはっきりしたものの方が、訴えるところが大きかったように思う。それはデュヴィヴィエの処理のうまさ、抒情性、品の良さといったものが大いに預かっていただろう。
一時期、この映画のタイトルは憧れを込めて語られていたほど、あるところでは、それなりに一世を風靡したと言ってよい影響力を持っていた。デュヴィヴィエは、本国フランスより日本の方が評判が高かったといわれるが、それにはそのころ強かった西洋への憧れも絡んでいたと思う。
『グラン・モーヌ』と『わが青春のマリアンヌ』との対比については、最後にふれることにしよう。
*
作者の遺族が握っていた原作の版権が切れたからだと思うが、『グラン・モーヌ』がついに1966年、ジャン・ガブリエル・アルビコッコにより『さすらいの青春』として映画化された。あの、幻の、モーヌの憧れの女性役として、監督が探し出したのが、フランス人が皆知っていて、それでいて誰も知らない、ブリジット・フォッセーだった。このキャスティングだけで、映画は成功したといえる。

ジャン=ガブリエル・アルビコッコ監督 アラン・フルニエ原作『さすらいの青春』 復刻シネマライブラリー販売
ここで、ようやく、『星の王子さま』と『グラン・モーヌ』がつながるのだが、彼女は、映画『禁じられた遊び』で、ジョルジュ・プージェリ(のちに『星の王子さま』の朗読レコードで王子さま役)と共演したという縁があった。この映画で5歳の少女ポーレットを演じ、名子役ぶりをうたわれたが、その後映画界からは遠ざかって、すっかり忘れ去られていたところ、18年経って、美しく成長した姿を再び銀幕に現したのである。美しさ、気品、そして青春のはかなさといったものが、見事に一人の女性の形となって具現されていた。

右:フランソワ・ボワイエ 著 花輪 莞爾 訳『禁じられた遊び』1970年, 角川文庫 左:ルネ・クレマン監督の映画DVD
ここで、話がそれるが、映画『禁じられた遊び』について少しふれておく。これは、フランソワ・ボワイエの原作をもとにしたもので、それまでに『鉄路の闘い』で知られ、のちに『太陽がいっぱい』や『雨の訪問者』を監督したルネ・クレマンの1952年の作であるが、戦争がテーマであるという理由で、フランスはこれをカンヌに出すことを拒否し、皮肉にもヴェネチアでグランプリを受賞、アメリカのアカデミー外国語映画賞をも受賞した名作である。戦争がテーマとはいいながら、冒頭の避難者への爆撃以外、戦争場面は出てこない、それでいて訴えるところの大きい反戦映画になっている。
この最初に出てくる爆撃で両親を失った少女ポーレットは、農村に分け入り、そこで少年ミッシェルと知り合う。二人は大人の知らないところで、お墓づくりに興じ、ついには教会の十字架を盗むまでになる。それが露見し、ポーレットは難民収容所にやられる。どこかで「ミッシェル」と呼ぶ声がして、少女は友達のミッシェルかと、声がした方に向かう。そしてさらにふと母親の面影を持った人の姿を認め「ママ」と人ごみの中に消えていく。ナルシソ・イエペスの「愛のロマンス」のギターの旋律とともに、この場面を思い出すだけで、私の喉の奥には飲み込みにくい大きな塊が生じてしまう。プージェリ、フォッセー共に、子どもにどうやって演技をつけたのかと思われるほどの名演である。特に、お墓にいろいろ埋めようということになって、その時ポーレットが「人間!」と言う、恐れと恍惚のないまぜとなった表情は、壮絶である。
さて、映画『さすらいの青春』に戻ろう。霧の中の森、夢のようなパーティ、不思議なサーカスの一団など、映像でこそ追求できる美に溢れていて、映画としての魅力を持っていたと思われるが、あまり話題にならなかったのはなぜだろう。映画の邦題『さすらいの青春』は、この物語の主題を端的に捉えていて悪くないと思うのだが、むしろ副題として「グラン・モーヌ」を添えてもよかったのではないだろうか、文学の方から、映画に関心を持つ人もあったかもしれない。また映画を見てから原作を読み、また映画に帰っていくということもあったかもと思うのだが。
*
今回、名画『禁じられた遊び』の二人の名子役たち、男の子の方のジョルジュ・プージェリが朗読において『星の王子さま』の王子役となり、女の子の方のブリジット・フォッセーが長ずるに及んで『モーヌの大将』のイヴォンヌを演じたという、それだけの理由で、かなり強引にこの2作を結び付けて、この文を書いてきた。ところが、驚いたことに2作を結ぶ縁がほかにもあったことがわかったのである。
一つは、豪華本『ル・グラン・モーヌ―若き日のバラード―』に関することで、この本は直接この作品を共に読んだ川口先生に捧げられたものだが、訳者たちが教えを受けた他の先生の名として、内藤濯氏があがっていたのである。氏は、岩波版『星の王子さま』の訳者として、つとに私たちの記憶にある人である。
もう一つは、『グラン・モーヌ』そのものにかかわる。この作品は発表されて好評だったため、フランス文学の有数の賞であるゴンクール賞の有力候補にあがった。ところが、対立候補として、レオン・ウェルトの『白い家』もあり、長時間の激論の末、決着に至らず、一転して全く別の作品が受賞したという。
レオン・ウェルトという名にご記憶のある人もあろう――彼こそが『星の王子さま』を献呈されているまさにその人物である。同一人物かどうか調べたわけではないが、そうある名ではないし、サン=テクジュペリの「親友」というのだから作家であってもおかしくない。
「わたしは、この本を、あるおとなの人にささげたが、子どもたちには、すまないと思う。—中略—そのおとなの人は、むかし、いちどは子どもだったのだから、わたしは、その子どもに、この本をささげたいと思う。おとなは、だれも、はじめは子どもだった。(しかし、そのことを忘れずにいるおとなは、いくらもいない。)—以下略—」(内藤濯 訳)
あの印象的な、ある意味『星の王子さま』という作品を包括したような、献呈の言葉の中に見られる名前なのである――2作の浅からぬつながりを知って、心が震えた。
『星の王子さま』について書いたとき、詩の出てこない作品を「ポエトリーの小窓」と名付けたコラムで扱う許しを請うた――全篇散文詩であるということで。今回も同じことを最後につけ加えなければならない。そして、これこそが、『グラン・モーヌ』と『わが青春のマリアンヌ』を隔てる大きな理由だと思う。
前者は詩で後者は散文なのだ。
とにかく私は、『グラン・モーヌ』の最後の一文「そして、私はその時もうすでに、彼が、夜、その娘をマントに包んで、共に新らしい冒険に出発する姿を想像していたのである。」(水谷謙三訳)は、詩そのものだと思っている。
(11/20/2021)