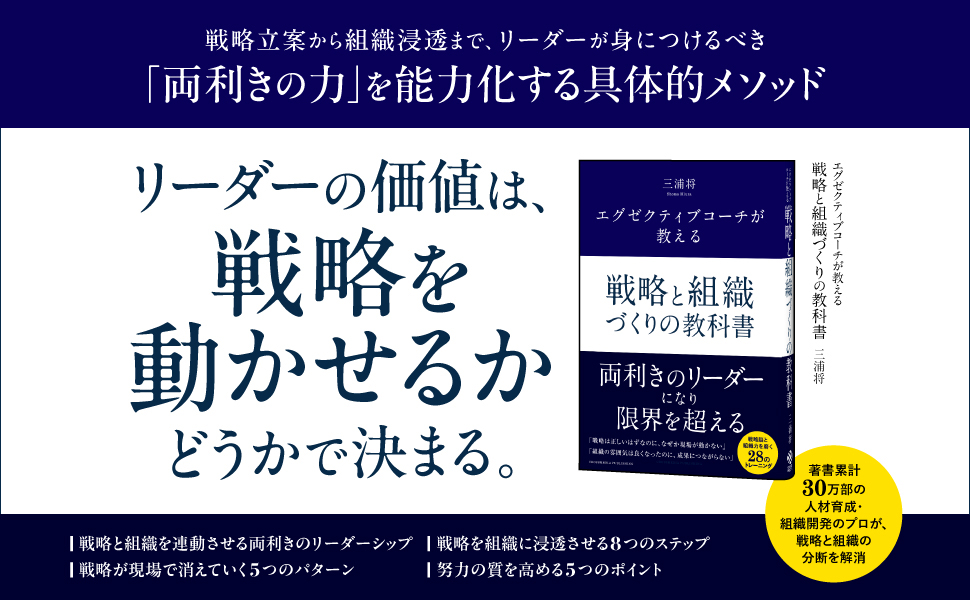第1回から第4回までは、2月に発売された鈴木さんの小説『離人小説集』(幻戯書房)のことを中心にお話を聞いてきました。最終回にあたる第5回では、鈴木さんの交友関係、なかでも盟友・中島らもさんとのこと。また、「EP-4 unitP」などミュージシャンとしての面についてもお話をうかがいました。フランス文学者、評論家、翻訳者、小説家であり、ミュージシャンでもある。知識人でありながら不良であり、神秘体験もある。そのすべてが鈴木さんであり、同時に鈴木さんの分身なのでしょう。(丸黄うりほ)

らもは寿命だったと思う。僕はなぜか生き残ってしまった
——「花形文化通信」は、90年代はフリーペーパーという形で刊行されていて、創刊号から中島らもさんの連載「わるもの烈伝」がありました。らもさんは「花形文化通信」主催のイベントにも何度か出演されていましたし、とても関わりの深い方だったと思います。一方、鈴木さんはらもさんの古い友人でいらして、らもさんが亡くなってすぐに『中島らも烈伝』(河出書房新社)を出してらっしゃいますね。
鈴木創士さん(以下、鈴木) らも君はね、逆に僕のこといっぱい書いているんだよね。けっこう嫌でね、それが。だってあれでお嫁に行けなくなったんだもん(笑)、あんなめちゃくちゃ書いて。それで、僕はそれまでは書いたことなかったんです、彼については一回も。彼は僕の本の書評とかもしてくれて。意地でも書くもんかと思っていたんだけど、でも死んでさ。編集者の誘いもあって、河出の人が「いっぺん書いたらどうですか」って。で、まあさらっと書こうかみたいになって。
——あの本を書かれたのは亡くなってすぐだから、もう15年くらいたってますよね。今ってあの頃と思いが変わったりしています?
鈴木 いや、あんまり変わってない。僕は彼と、自殺したやつとか共通の友達いっぱいいてさ、そいつらのことも今はどう思っているのかといったら、寿命だったと思っているんですよ。らもも寿命だと思っている。自殺したやつはまあ、らもとは違うけど、それ以上生きられないし。
だってさ、難病とか、赤ちゃんで死ぬ子とかいるじゃない。3歳で死ぬ子と80いくつまで生きたのとどっちが人生を全うしたか、これは言えないですよ。だから3歳で夭折だけど、それが人生半ばにしてなのか、誰にもわからない。3歳の命で3歳まで生きたら僕は長生きしたと思っている。90までいっても長生きだけど、じゃあ30で死んだらそれは挫折なのか?自殺ですらそう思わなくなった。ただ、僕からみて、終わった感じがしないときもあったから、自殺っていうのは結構いろんなことがあるなとは思ったけど。今にして思えば彼らが年いった姿ってまったく想像できないから、あれでいいんだというふうに思ってますけどね。まあ生き物だから、寿命ってあると思う。
僕はめっちゃ病弱やったんですよ。でも、クソみたいに生きてしまって。20歳まで生きられないって言われていてね、結核だったし、毎週注射打ってるみたいな。40度の熱なんてしょっちゅう出てて、もう幻覚見えますよ、40度こえたら、朦朧として、子ども心に覚えているけど。だからわかんないです、生きているのが、何の因果か。
——らもさんと出会ったのは確か鈴木さんが中学3年生で、神戸のお店だったんですよね。身体が弱いのにそんなところに出入りしてらしたんですね。
鈴木 そういうのを探していた時代だから。僕は初めは音楽がやりたくて、ピアノとかクラシックをやろうと思っていたんだけど、小学校の高学年の時にローリングストーンズやビートルズ、ロックを聴くようになって。胸の病気になったし、ピアノ続けられなくなってやめちゃったんだけど。音楽は好きで、そういう人たちを探していたからね。だから、髪の毛長いやつのあとをつけていった。当時は情報雑誌とかないじゃないですか。『ニューミュージックマガジン』ってできた時だっけ、そこに広告が載ってたんですよ、「バンビ」じゃない、「ニーニー」っていうジャズ喫茶だった。でも僕は、その髪の毛長いやつのあとを、この人たちどこへ行くんだろうと思ってつけていって。で、見つけた。
——音楽好きが集まる店だったんですか?
鈴木 いや、必ずしもそうじゃない。でも、そういう音楽聴いている人は本も読んでたし、僕の大学みたいなもんですよ、そこで本とかもだいぶ覚えて。
——鈴木さんは、らもさんの一番古い友達といっていいですよね。
鈴木 神戸の連中はみんなだいたい同じ頃です。まあ彼は灘高だったから、灘高の同級生も来てた。灘高の外の友達では僕はわりと早い時期だったな。だから当時は灘高も、ドロップアウトしたみたいな全然勉強もしない人たちはジャズ喫茶とか来てたから。そういうのが何人かいて、みんな別々に来るんだけど、そこに来るわけですよ。だからそれはみんな死ぬまで友達だった。何人か神戸にも生き残っているけど、もうほとんど死んじゃった(笑)。ドラッグ、自殺、事故。
——鈴木さんは生き残った。
鈴木 その仲間ではそうですね。らもの奥さんも生きてるけど、僕も生き残ってしまった。なんでかわからないけど。
——今だったら言える、とかありますか。
鈴木 いや、とくにないですね。当時から面と向かって言ってたし。らもと取っ組み合いの喧嘩になったときのこと覚えてるけど、大阪の四ツ橋で。溜まり場があったんですよ、「パームス」っていう。「パームス」はできた時から知ってて、よく行ってたんですよね。で、あそこで喧嘩になって、「表へ出ろ」となって。二人ともラリっているからまともな喧嘩にならない。他のやつが来て、「君ら、ものすご喧嘩の姿がかっこわるいから、もうやめたら?」とか言われて(笑)。
——15年もたったらイメージが逆に純化してはっきりしてくるってことはないですか?
鈴木 うーん。あんまり時間たったと思ってない。言われてみればそれだけたっているけど、あまり変化してないと思う。若い頃のイメージからぜんぜん変化してない。らも君に関してだけじゃないですけど。
音楽と文章を書くことは、ぜんぜん違うもんだからやってるんです
——音楽はクラシックから入ったということでしたが。
鈴木 そうですね、いまでもクラシック好きですけど。ノイズやってんのに家ではシューベルトとか。「EP-4」は、黒人音楽のファンクのイメージで現代音楽をやろうと思ってた。そういう演奏ですよね。
——鈴木さんは「EP-4」の最初のメンバーですね。結成は1980年。じつは私、当時リアルタイムでは見れてないんです。今や伝説のバンドですよね。
鈴木 京都に溜まり場があって、「CLUB MODERN」っていうとこ、そこに僕もよく行ってた。「EP-4」のリーダーの佐藤薫がプロデュースしてた店だった。ニューウェイヴとかパンクとかの溜まり場で。で、「やる?」とかいうことになって。
——担当楽器はずっとキーボードですか。
鈴木 僕、最初弾かなかったから、肘で弾いたりしてたから、ずっとピアノ弾けないと思われていた(笑)。僕はロックもジャズも聴いてましたよ、嫌いな音楽はとくになくて、音楽はなんでも好きですね。それこそ津軽三味線とかも好きで、ノンジャンル。パンクもリアルタイムだから。ちょうど僕がフランスにいた時にセックスピストルズとか出てきて、フランスのパンクってちょっと違うんだけどね。で、日本に帰ってきて、新宿の先輩というか年上の人たち、おじいさんたちが、「創士くん、パンクって知ってる?パンクだよ!」とか言ってた。そういう時代に遭遇したから、ピストルズも好きでした。「EP-4」は、わりと最近に復活ライブみたいなの、したんですよ。
——鈴木さんは一度「EP-4」を抜けたのですか?
鈴木 そんなこともあったけど、今でも僕もメンバーですよ。復活ライブにも出演しました。バンド自体は、普通のことだけど、かつてのメンバーが全部揃わない。リーダーの佐藤薫は健在ですよ。
——「EP-4 unitP」のライブは、つい最近、神戸で見せていただきました。
鈴木 もともと「EP-4」っていうのは勝手にメンバーがユニット作っててね、昔からいろんな人とやっているんですよ。だから「EP-4 unitP」は、「それの形式でまたやっていい?」って佐藤にきいたら、「やれや」って。
——「EP-4 unitP」はいつからやっているのですか?
鈴木 5年くらい前かな。最初は僕とパーカッションのユン・ツボタジと、オプトロンっていう自作楽器、蛍光灯ギターの伊東篤宏っていう人がいるんですけど、その人と一緒にやったのが最初かな。
——鈴木さんの中では「EP-4」はずっと続いてたんですか?
鈴木 もちろん続いてて。ただ、音信不通の時期も、リーダー自体が雲隠れみたいな時期もあったし、外国にいたし。なかなか連絡もしてなくて、そのうちメンバー死んじゃったりしたんですけど。だから今は、もともとのメンバーは仲良しで。ちょうどこの前「CLUB METRO」でね、久々にやろうとしてたんだけど、コロナでイベント自体がなくなっちゃった。「EP-4」は長いですよ、80年からやから。もう40年。半世紀ちかい。いま佐藤君は自分のレーベルみたいなんやってて、そっちで忙しいみたいで。「Φonon(フォノン)」ていうレーベル。まあ「EP-4」のことは佐藤君に聞いたほうがいい。
——「EP-4 unitP」以外の音楽活動はいかがですか?
鈴木 いろんな人とやってますよ。それこそ、ここ(「アビョーンPLUS ONE」)の大川透君(写真奥)ともやったこともあるし。ソロはやんない。めんどくさい。
——現在動いているユニットはありますか?
鈴木 いまはない。「チルドレンクーデター」となんべんかやって、レコーディングとかも加わってやったけど。それが最後くらいかな。神戸のロックの人の録音に入ったりもしてる。一人で現代音楽みたいなのやってたこともある。クラシックのジョン・ケージ弾きの女性と二人で組んでやってたりもしたんだけど、長続きしてない。
一人でやってもつまんないね。爆音だったらいいんですよ、僕(笑)。超気分が悪くなるくらいの爆音だったらいい。爆音が好き。
——クラシックが好きなのに爆音好きなんですね。
鈴木 ヴェーベルンとかにすごい影響受けたから。シュトックハウゼンとかはそんなに影響受けてないけど、エドガー・ヴァレーズとか好き。
——「EP-4 unitP」では、チベットの声明を使われてたのがすごく印象に残っています。
鈴木 「EP-4 unitP」ってそんなバンドなんですよ、佐藤君はチベットに行ったりしてたし。すごい好きですね、宗教のマントラとかコーランの朗読とか。怖いけど、ときどき聞いたりしている(笑)。シャンソンもすき。バルバラとかすごい好き。ヴェルヴェット・アンダーグラウンドはリアルタイムで聴いたから影響受けました。下手くそなんだけどね、まあノイズ的な音楽としてはいちばん最初だから。
音楽と文章を書くことは、ぜんぜん違うもんだからやってるんです。だからメッセージとかないですよ、僕の音楽には。
——文章から出てくる声、身体性ということをおっしゃっていましたが。
鈴木 文章に音楽的なものを見るっていうのは常にある。それはそうなんですけど、だからといって音楽のほうに文学がそんなに関係しているかっていったら、まあなんかイメージはあるんだろうけど直接的にはほとんど関係ない。
——音楽も身体性だとは言えませんか。
鈴木 むしろ、音楽っていうのは僕にとっては出来事に近い。音楽についてはあまり語れないね。ただ、他のミュージシャンとやるのは楽しい。ある種の触発だからバンドは。そういうのを音にしているところはあります。
——らもさんもバンドをやられてましたよね。
鈴木 らものバンドは、僕もレコーディングに参加しましたよ。「一緒にやれ」って言われて「嫌や」って言った。「なんでや」って言うから「俺、有名人のバンド嫌いや」って(笑)。で、「こんなしんどいのにドサ回りなんか絶対嫌やわ」って言ったら、それで大喧嘩になった。「お前はなんでそんなに自分の考え方を狭めるんや、昔からそうや。それが自分をダメにしていることわからんのか」とか言うから、「うるせえ」って電話で大喧嘩。
塚村編集長 らもさんって、そんなに怒らはるんですね。あんまり怒ってるイメージはないですけど。
鈴木 怒ってた。どなってた。
——らもさん、悔しかったんと違いますか?鈴木さんが「うん」と言ってくれないから。
鈴木 だから、あとで僕が折れて、「レコーディングやったら何曲かやってもいいよ。ただステージとか嫌や」って。まあそういう時期じゃなかったんですよ、僕自身がステージに立ってやるとか。
——鈴木さんの音楽性とらもさんの音楽性とはだいぶ違う気がしますね。
鈴木 違いますよ、違うけど彼に合わして、ビートルズの「トゥモロー・ネバー・ノウズ」みたいな。普通のロックンロールみたいなのやりましたよ。基本的には彼はロック、ローリングストーンズとか好きで。もともとはフォークもやってた。僕はフォークはなかったな。歌えるけどね。
——らもさんにはノイズのイメージはないですね。
鈴木 そうですね。でも彼もパンクは好きだった。……まあ、そんな感じかな。
(5月12日、神戸市内で取材。協力:アビョーンPLUS ONE。写真: 塚村真美)