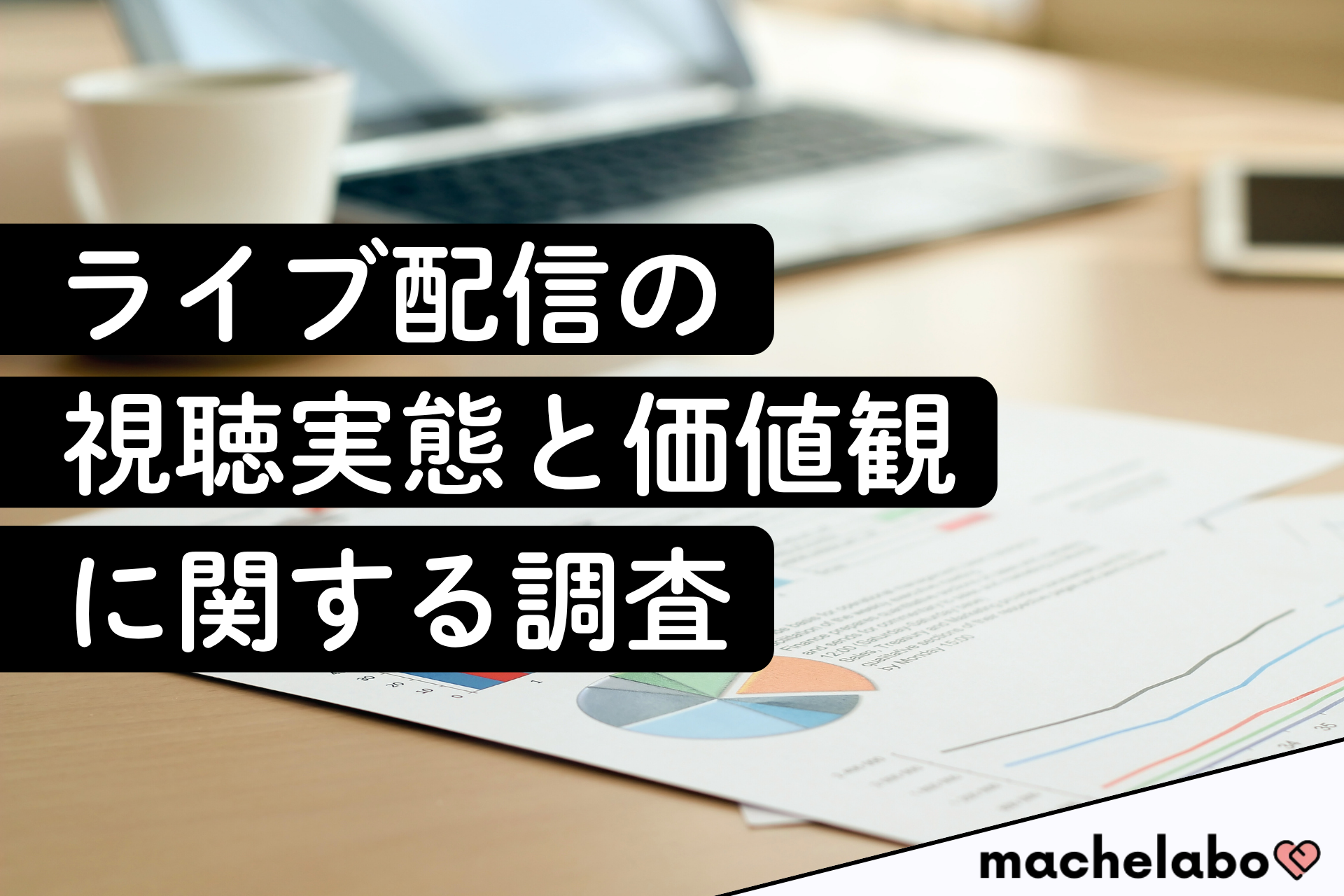「猫の挨拶」
ずいぶん間が空いてしまった。
昨年の末以来、バーに行くことを覚えた。
彦根で暮らした20数年間は、街中まで数キロはあったので、ちょっと近所に飲みに行くという習慣とは長いこと無縁だった。歩いて行けるところにおいしいネパール料理の店ができてからは、仕事帰りにそこでビールを飲んでパパドを囓り、アチャールを食べていた。
東京で移り住んだ場所は街中に近く、少し歩けば、安いところから高いところまで、飲み屋がやたらとある。しかし来たばかりの年は、新しい仕事になじむのに忙しくてあまり飲みにも行けず、ようやく二年目になろうかという2020年にはコロナ禍になってしまい、なじみの店を作る機会を逸していた。2022年になっても、いまだにコロナ禍は油断ならないのだが、感染者数が減ると飲みに出るようになった。といっても、大勢で賑やかに、とは行かず、たいてい一人だ。
エレベーターで昇っていきなり目の前に扉があるようなところは、ちょっと気後れがする。できれば一階、せいぜい二階で、外から扉が見えるくらいのところに、当てずっぽうで入ってみる。20数年前に比べると、こちらの風貌も年寄りじみてきたせいだろうか、初めてのバーに一人で行っても、若いときよりなんだか丁寧に扱われているような気がする。とはいえ、いつまで経っても酒の種類がちっとも覚えられなくて、何を頼んだらいいのかよくわからない。きょうは暑いのでとか、眠る前にちょっと飲めるものをとか、あいまいなことを言ってみる。そういういい加減なことばすら、若いときは妙に通ぶって嫌味にきこえないかしらと口にするのがためらわれたものだが、この年になると、特に裏表もなく言えてしまう。そんないい加減な注文でも、出てきたものが思いがけなくおいしいとうれしくなる。
書き物をするときに、なぜか喫茶店やファミレスでないと集中できないのに似て、読書するときも、家よりもバーの方が進む。以前、山田風太郎の原稿を書くときに、そのときだけ遠い飲み屋に通ってちくま文庫の明治ものを片っ端から読んだことがあった。バーで隣り合わせた人と話す愉しみを知らぬわけではないが、たいていの場合は本を読んでいる。本を読んで長居しても邪険にされないバーを選ぶ。喫茶店で書いて、疲れたからバーで飲みながら読む、ということもある。
もっとも、バーにばかり通っていたのでは金がどんどんなくなってしまう。普段は、レモンサワー一杯300円くらいの飲み屋に入って、そこで小皿など頼んで、やはり本を読む。家では静かにしていても気が散るのに、飲み屋ではテレビがついていても人が話していても読書ができるのは不思議なことだ。
*
あるバーの近くにある公園から猫がいなくなってひと月経つ。6月に飼い主とともに引っ越してしまったのだ。公園を通るたびにちょっと覗くと、三度に一度くらいは、ちょうどちょろちょろと生えた竹の茂みの凹みに居て、あ、いるなと思って通り過ぎた。そのせいで、いまも通るたびに、何となく目をやって、いないことを確かめてしまう。
引っ越しの日、バーに行ってみると、客はいなかった。奥の止まり木に座って、もうさすがに猫は来ないですねとマスターと話していて、ふと戸口を見たら、黙って入ってきた。試すような足取りで、少しずつ近づいてきて、止まり木に座っているわたしを見上げた。昨年の暮れ、ふと気まぐれにコンビニでチャウチュール4本入りを買ってしまってからというもの、それは鞄の中にずっと入っていて、足下に猫が来るたびにやったので、わたしには計4回の前科があった。食べものを与える人は他にも幾人もいるだろうから、覚えていたとも思えないが、あるいはそういうことをする者の気配が漂っていたのだろうか。しかし、餌をねだられているというよりは、なんだか神聖な儀式のようで、止まり木から降りかねた。
カウンターの外に回ってきたマスターが、おいと声をかけてしゃがむと、ようやくにゃあと鳴いて、猫らしい振る舞いになった。毎年冬になると、猫はこのバーの入口にあるストーブに毎日のようにあたりに来ていたけれど、いつもはカウンターの奥まで入ってはこないのだそうだ。挨拶に来たの?とマスターが問うと、その場でゆっくりと一回りして、店を見上げるように止まって、出ていった。
バーに来たのは、それが最後だったという。
(7/25/22)
*前回のお話「猫の谷」はこちら