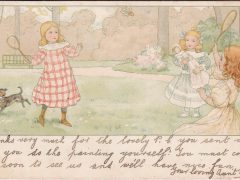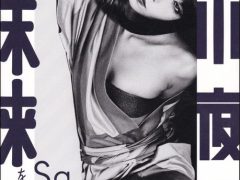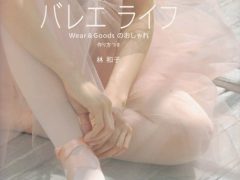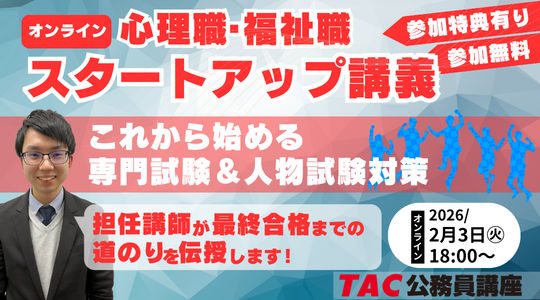挿し絵:北林研二
逆にわかる
東京の地下道は味気ない。なんといっても店も看板も少なすぎる。隙さえあれば店を開いて地下を「地下街」と化す大阪の感覚に慣れていると、なぜこんなに何もない道が続くのか不思議なほどだ。
そのせいだろうか、東京の長い地下道を歩いても、さっぱり道順が頭に入ってこない。たとえば、地下鉄の有楽町駅で降りて、そこから長い地下道を通って東京ミッドタウン日比谷にある映画館に行く、というのを、これまで何度も繰り返してきたのに、いつも自分がどこを歩いているのかよくわからなくて、いちいち看板の文字を確かめてきた。
それが、突然変わった。
先日、いつものように有楽町を降り、1号車側の長い階段を上って改札口を出て歩き出した瞬間、あれ、ここは逆に来たことがある、と感じたのだ。来たことがあるも何も、わたしはここを十数回は歩いており、行きも帰りも同じ道を通るのが習慣だったのだが、これまでは、その行きの道と帰りの道の印象がまるでばらばらで、もと来た道をたどり直しているという気がまったくしなかった。ところが、向こうから来る人がふと、未来の自分であるかのような気がして、とたんに、行きの時間と帰りの時間とがつながった気がした。3DRPGで、自分の操作しているキャラクターの視点をぐるりとひっくり返して、向こうからこちらに向かってくるように見るときの、あの感覚にちょっと似ている、と言ったらおわかりいただけるだろうか。
朔太郎の『猫町』で、方向感覚が狂った語り手が、いつもの道の東西南北を取り違えたために、見慣れた町並みがまったく見知らぬものに見えるという体験を語っているけれど、これはちょうど逆で、それまではばらばらに見えた往路と復路とが、ひとまとまりの道として息づきだした。

その日観たのはゼメキス監督の『HERE 時を越えて』で、一軒の家の空間にまったく別の時間における同じ空間が割って入ってくる感覚がずっと続くというものだった。帰りの道はその映画の力を借りてさらにおもしろかった。味気なかった地下道が、やけに親密になってきた。右向こうにあるあの壁のしみは、行きのときには左そばにあって、わたしはそれをなんとなく気にしながらいつも通りすぎていた。行きのときには左にあって、ここで出たほうがいいのかしらといちいち確かめていた出口表示を、帰りにはちらと見るだけで通り過ぎるのだ、ということにも気づく。帰り道にいちいち、行きの時間が割って入ってくる。
わたしはついに、この地下道をものにしたのかもしれない。これからはもう、映画館に通うこの道は、まるで違う道になる。自分に起こった感覚の変化に軽い興奮を覚えて、それは、電車に乗ったあともしばらく続いた。

そして電車が止まったとき、目の前に現れた看板の駅名が、まるで見慣れぬものであることに気づいた。わたしは、行き先と逆の電車に乗っていた。もう、六駅目を過ぎていた。
(4/17/25)
これまでの「東京なでなで記」はこちらから
映画『HERE 時を越えて』公式サイトへ