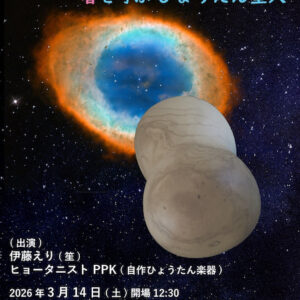牛と龍之介の新宿
九月になったが、とても暑い。
『澄江堂雑記』(大正13年)によれば、「とても」が東京で肯定的な表現として使われるようになったのはどうやら大正期の半ばらしい。
「とても安い」とか「とても寒い」と云う「とても」の東京の言葉になり出したのは数年以前のことである。勿論「とても」と云う言葉は東京にも全然なかった訣(わけ)ではない。が従来の用法は「とてもかなわない」とか「とても纏まらない」とか云うように必ず否定を伴っている。(芥川龍之介『澄江堂雑記』)
明治25年生まれ、東京生まれ東京育ちの芥川龍之介の書くことだから、信憑性は高いだろう。試みに大正5年になくなった夏目漱石の晩年の作品から会話を拾い上げていくと「とても適いませんな」「とても助かる見込みはないんだとさ」「とても幸福になる望はないのね」などと、なるほど徹底して否定的である。
そう言われてみると、たとえばドラえもんへの心情を「とっても大好き」と歌うのは、なんともモダンで、新しい表現に思えてくるから不思議だ。
*
まだ「とても」が東京で否定的な表現だった頃、芥川龍之介は新宿に住んでいたことがあった。その住まいというのは、どうやら今の二丁目あたりらしい。あたりらしい、と曖昧な言い方になってしまうのは、それらしい看板が見当たらないからだ。終の棲家となった田端にはちゃんと旧居跡を示す表示板が立っているのに、新宿二丁目には、ない。だいたいが、新宿二丁目に行くと、いつも迷ってしまう。あんなに狭い街で迷うも何もないはずなのに、どうしてなのだろう。たとえば新宿ピットインに行ってから、さほど複雑とも思えない辻をいくつか曲がって、墓地を区切っているらしい高い塀にさしかかったあたりで、あれ? 自分はいまどこにいるんだっけ? となる。
そもそも、二丁目に入る時点で、なんだか妙なのだ。JR新宿駅から新宿通りを東へ、明治通りをわたってから、末広通りを冷やかしてさらに進むと、突然、中央分離帯のある「御苑大通り」が、まるで街をぶった切るように斜めに貫いている。この通りが三丁目側と二丁目側をばっさり分断していて、なんだか川のこちら側から向こう岸に渡るような感じだ。
二丁目に関する本を読むうちに、そう思っていたのはわたしだけではないことを知った。文化人類学者の砂川秀樹は、大塚隆史のことばを引用しながらこんな風に書いている。「一九六三年に都電・杉並線が廃止され、線路のあった新宿二丁目とその手前の新宿三丁目のあいだの道路が整備されて五〇メートル幅に拡張されている。その道路を越えることが、「川を渡る」[大塚1995:14]と表現されることがあるように、都電の〈エッジ〉としての性質をひき継ぎ、新しい〈エッジ〉としての役割を果たし、分離性は維持されている」*1。
「御苑大通り」はもともとは戦後、1949年に新たにできた都電の路線が横切ったあとだった。靖国通りから現在の新宿三丁目東交差点のところでぐっと南東に曲がり、新宿二丁目交差点のところで今度は東に曲がり、新宿通りを走っていた。引用部分の通り、それが1963年に廃止され、道路として整備された。砂川の著書には、都電時代の新宿二丁目交差点付近を映した1958年の写真が掲載されているのだが、線路の両側はまだ未舗装の、バラックの点在する荒涼たる領域で、ちょっと驚いてしまう。ちなみにかつてはこの荒涼たる都電の線路から東側が「赤線」地帯だったから、その頃から、「渡る」感覚はあったのではないだろうか。
それにしても、この元都電の線路である大通りの横切り方は、暴力的なまでに不自然だ。それは、この通りがあちこちで「Y字路」を形成していることからも明らかだ。花園神社前の三角地もそうだし、ときどき「新宿タイガー」を見かける新宿五丁目東交差点の南西角、交通安全の誓いの像の南側にも、三角地ができている。前にも記した通り、Y字路では暗くて細い方が古く、広い通りはあとからショートカットのために作られたことが多い。この「御苑大通り」のもとになった都電の線路も、もともとあった街の構造を、寸断する形で作られたのだろう。戦後すぐという時期から考えて、それは東京大空襲で焼け野原となったことがきっかけだと考えられる。
話が芥川龍之介からずいぶんとずれた。では都電の走るよりずっと前、明治末期から大正期にかけて龍之介が住んでいた頃の新宿二丁目はどうなっていたのだろう。龍之介は生まれてすぐに下町の本所小泉町にあった芥川家に預けられたが、明治44年、実父の持ち家のある新宿二丁目に移ってきた。龍之介の実の父、新原敏三は、明治21年から大正元年にかけて、このあたりで耕牧舎という牧場をやっていた*2。
僕の父は牛乳屋であり、小さい成功者の一人らしかった。僕に当時新らしかった果物や飲料を教えたのは悉く僕の父である。バナナ、アイスクリイム、パイナアップル、ラム酒、――まだその外にもあったかも知れない。僕は当時新宿にあった牧場の外の槲(かし)の葉かげにラム酒を飲んだことを覚えている。ラム酒は非常にアルコオル分の少ない、橙黄色を帯びた飲料だった。(芥川龍之介『点鬼簿』)
その牧場や家というのは、どのあたりなのか。看板がないから、調べるしかない。「地図で見る新宿区の移り変わり―四谷編―」*3には明治期の二丁目がどういう地割りだったかを示す地籍図が掲載されている。一方、当時の牧場の番地は、新宿二丁目71番地であり、芥川龍之介が友人に宛てた手紙には、二丁目の自宅までの略図が描かれている*2。71番地がすべて牧場だったとすると、図の緑色の広々としたエリアがそれにあたる。ただし「地図で見る~」には古老の記憶に基づく二丁目界隈の地図も載っており、そちらを手がかりにすると、二丁目の濃い緑部分は内藤新宿を開いた「高松さん」の土地で、耕牧舎は薄い緑部分、西にある千坪ほどの矩形のエリアである。

【図】現在の区画に新宿二丁目71番地(緑色)を重ねたもの。少なくとも矩形の部分(薄緑色)には芥川龍之介の実父、新原敏三が経営する耕牧舎があったと考えられる。文献によっては緑の部分全体を牧場に含めるものもある。赤丸の位置が芥川龍之介の暮らした新宿の家。
牧場が矩形だったとすると、それは現在の三丁目と二丁目をまたぐエリアにあたり、龍之介が移り住んだ家は、ちょうど現在の新宿五丁目東交差点の歩道上にあたる。なるほどこれでは、史跡の看板も立て辛いだろう。そして、牧場であったかどうかはおくとしても、現在の二丁目の仲通りから西、花園通りから北は一面の原っぱであったことは間違いのないところだ。
では、なぜいまその牧場のありかがわかりにくくなっているのだろう。牧場は大正のはじめごろ、付近への臭気が問題となり廃場となってしまった。大正6年の地図ではまだ牧場も二丁目の原っぱも残っているが、現在の三丁目東あたり、追分に京王線が開通し、街の構造は急激に変化しつつあった。関東大震災の直前、大正12年にはいずれも宅地で埋まっている。そして、震災後には、二丁目と三丁目の区画はさらに大きく変わり、所番地も変更された。昭和3年測量の地図をみると、牧場の跡地の真ん中に道路が貫いており、これが現在の要通り(末広亭の一本東の通り)の元となっていることがわかる。そして、先に書いたように、戦後には都電がかつての牧場のあった土地を斜めに貫いた。こうして幾度も街の構造が塗り替えられたために、もはや牧場は輪郭をたどるのも難しくなってしまったのだ。あえて牧場の矩形を現在に当てはめると、北端がちょうど新宿五丁目東交差点の南側歩道あたり、南が東急ステイ新宿あたり、東端が花園通り向かいの歩道あたり、西端が老舗の「どん底」あたりということになるだろう。
*
芥川龍之介の父が亡くなったときのことは、『点鬼簿』に記されている。
僕は二十八になった時、――まだ教師をしていた時に「チチニウイン」の電報を受けとり、倉皇と鎌倉から東京へ向った。僕の父はインフルエンザの為に東京病院にはいっていた。(芥川龍之介『点鬼簿』)
昨年までなら、このくだりを読んでもピンとは来なかっただろう。けれど、いま読むと、はっとさせられる。芥川龍之介が二十八ということは、大正8年のことだ。おそらくここで記されている「インフルエンザ」とは当時世界的なパンデミックを引き起こしていた史上最悪のインフルエンザ、通称「スペイン風邪」のことであり、龍之介の父、新原敏三はこの流行病にかかって亡くなったのだ。
僕が病院へ帰って来ると、僕の父は僕を待ち兼ねていた。のみならず二枚折の屏風の外に悉く余人を引き下らせ、僕の手を握ったり撫でたりしながら、僕の知らない昔のことを、――僕の母と結婚した当時のことを話し出した。それは僕の母と二人で箪笥を買いに出かけたとか、鮨をとって食ったとか云う、瑣末な話に過ぎなかった。しかし僕はその話のうちにいつかまぶたが熱くなっていた。僕の父も肉の落ちた頬にやはり涙を流していた。(芥川龍之介『点鬼簿』)
現在の新型コロナウイルス禍での生活常識からすると、実に無防備で、病弱な龍之介はよくインフルエンザに感染しなかったものだと思わされる。しかし一方で、長らく養父母のもとで暮らし、若くして実母を喪った龍之介と父親の親密なやりとりには、心動かされずにはいられない。「僕の手を握ったり撫でたりしながら」という触覚的なやりとりが、親子の話す間、長い通奏のように続いている。手を握る、その手応えが、相手にもすぐに伝わる。触覚は、視線や声よりもすばやく、触れることと触れられることを同時に顕わにする。眼と耳を使うやりとりは、触ることのもたらす細やかさに、とても適わない。それは、わたしたちが現在盛んに使っている遠隔のやりとりに欠けているものでもある。
(9/7/20)
*1 砂川秀樹『二丁目の文化人類学 ゲイコミュニティから都市をまなざす』太郎次郎エディタス(2015)。引用は、大塚隆史『二丁目からウロコ』翔泳社。
*2 『新潮日本文学アルバム 13 芥川龍之介』新潮社(1983)
*3 東京都新宿区教育委員会「地図で見る新宿区の移り変わり―四谷編―」(1983)