毒気を含んだ享楽、空とぼけたキテレツ。
全方位的活躍の巻上公一を中心にわが道を闊歩するヒカシュー。
心身&お脳を刺激する丁重なおもてなしが待ってるよ。

『人間の顔』から2年ぶりに新作『丁重なおもてなし』を出したヒカシュー。風変わりな6人の個性が上等の玉子豆腐のように溶け合い、愛と狂気と冒険をテクノ的ジャズ風ロックの音作法で異次元に誘う。このところ、ソロで八面六臂の活躍を見せる巻上公一に、1979年バンド開始以来、色あせないこの独特の世界の不思議パワーを問う。
――『丁重なおもてなし』っていう歌がヘンで面白いですね。
巻上 アルバム自体、最初の頃に戻ったような感じでね。いろんなのが入ってて何とも言いがたいものがあるけど、あの歌はちょっと皮肉っぽいんだよね。テレビを見てて、テレビの向こう側にロックを歌ってるアイドルがいて、すごい上手いダンスをしながら、巻き舌で英語みたいな発音してるわけ。何言ってるかわかんない。でもまあそれは許すから、こっちに来てお茶でも飲みなさい、和菓子も用意しますっていうね(笑)。
――そういう皮肉っていうか、パロディ化するというのが底の方にいつもありますね。
巻上 それはいつも考えてるの。たとえば、『人間の顔』の時に〝ゾウアザラシ〟の詞があって、それはデビューした頃から考えてた歌なんだけど、要するに自分が考えて不可解なことがいろいろ起きてしまう——人間は不条理の中で生きてるっていうことを表現したかったんだよね。それで、不条理を形にする時にゾウアザラシ的なものって考えたわけ(笑)。巨大で自分の部屋にいたら困るっていう。それは政治やいろんなもののメタファーであったりするんだけど。置き換えた方がぜんぜん別の話にできるでしょう。ナマナマしくしない方がいいし。いろんな意味を持ってこれるから。で、自分でもわかんない意味ってあって、それがまた楽しいの。わかんないものを自分で探りながら書いていくの。言いたいことは決まってなくて書きながら検討してるの。じゃないと面白くないから。
――それでモヤッとしたものを提示してる。
巻上 うん。そういうのって他で書かれないしね。昔はもっとモヤッとしてたよ。『幼虫の危機』なんて4行。〝楽しいな幼虫が死ぬなんて、楽しいな昆虫が死ぬなんて、楽しいな動物が死ぬなんて、楽しいな人間が死ぬなんて〟という。小さな命が失われつつあると思って書いたんだけど。
――今度のはライブ盤を入れると、もう10枚目ぐらいですよね。作る時はやっぱり前のよりはどうこうしようって考えるんですか?
巻上 あまり考えて作ってない。何か進んでると思ってやってないんだよね。そんなには。タラタラタラタラと作ってる。作るの遅いし、無理に作んないし。5年くらいかかってる詞とかあるもん。まいっちゃうよな。今回のアルバムもライブで3年ぐらいやってるような曲ばっかりだよ。で、その間にここはこうしようとか、ここは失敗してるとかって変えていくわけ。お客さんと一緒に作っていくというか。だから、レコーディングはもう完成されてるから凄い早い。
――『平成じゃらん節』でもつくづくと再確認したんですけど、巻上さんの歌唱って三波春夫じゃないけど独特で、あれは意図してる部分ってあるんですか。
巻上 はっきりした発声っていうか、俺の歌は自然にそうなるんだよね。昔、寺山修司が好きで、東京キッドブラザーズにも何年かいたんだけど、その頃の歌を聞いても今と同じ歌い方をしてるわけ。それで浮いてるの。コーラスのレッスンしてても怒られてばっかりいたもん。ソロならいいけど一人だけ声はデカイし、みんなが声枯らしてても、ぜんぜん枯れないし。やたらうなっちゃってね(笑)。演劇やってる人でもああは歌わない。珍しいって。生来的にパッパッとしたのが好きでね。まあ自分の特性なんだから、それを生かせばいいと。
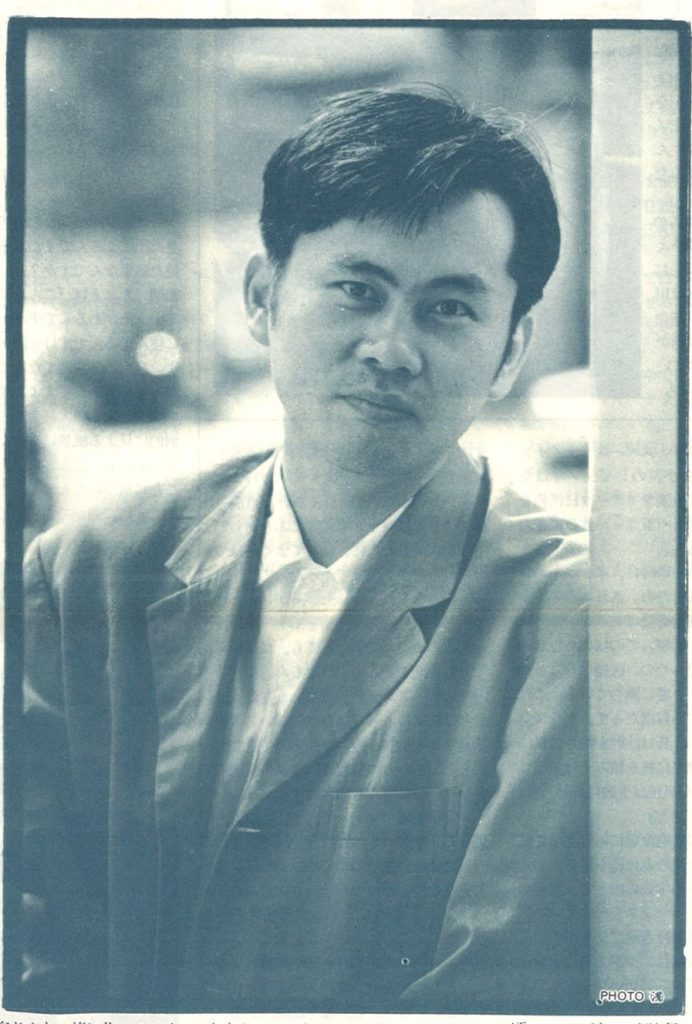
――ヒカシューは、その歌を中心にそもそもどういうバンドにしようとしたんですか?
巻上 うーむ、とらえどころがない!(笑)俺がワンマンみたいに見えるかもしれないけどやっぱりグループでさ、それ以外は決めごとがあんまりないね。最初始めた頃は肉体っていうの、身体性っていうの、そういったものがテクノロジーにからめとられちゃってて、肉体そのものもまるでコピーされたような感じを持ってたわけ。そういうのを歌にしてたの。テクノブームの前、77〜78年頃にそういうことを考えてて。だから他のバンドよりずいぶんステージで体を動かしたよね。
――徒手体操みたいだった。
巻上 動きすぎだ!とか言われてたもん(笑)。その頃、フュージョンが流行っててね、あれが僕ダメだったんだよね。まったく好きじゃなかったの。それで何か違うのをやりたくて。
――ぜんぜん違う(笑)。
巻上 うん、ぜんぜん(笑)。よくパンクっていうかセックス・ピストルズの影響受けたってみんな言うでしょう。あれも僕、大嫌いでさ、N.Yのニューウェーブとかの方がずっと好きだった。テレビジョンとかトーキング・ヘッズとか。そっちの方が頭良さそうじゃない(笑)。痛いことはしないし。ピストルズは痛いしサウンドもうるさいし、何か作られたものって感じが強かったね。そりゃ後で歴史として聞いて、多少意味はあんのかなって気はしたけど、他のバンドの方が面白かったからね。大体そうだよ。あまりワァッと出て現象になっちゃうバンドよりも、その影にかくれてるバンドの方が時代を捉えてるよ。
――そう言えばヒカシューもそんな感じがする。(笑)
巻上 はは、影にかくれて…。まあブームにはならないよね。
――同じ時期に出たテクノポップのバンドがみんないなくなったでしょう。
巻上 いなくなると思ってたぜ(笑)。僕達とぜんぜん違うし、ヒカシューはやり続けててあまり意味を失わないからね。最初にやったことが良かったの。まちがってなかった。あそこでもうかなり多面的なことをやってるからね。可能性がいっぱいあるの。どれをやってもいいの。歌の力というのもあるし。
――減らないって感じですね。最初からその意味で異端だったような。
巻上 うん、だから普通の歌を歌ってても異端と思われてるからラクだよね。この前やった〝超歌唱セッション〟で『およげ!たいやき君』を歌ってても、だから読み直しをされるでしょう。子門真人が歌ってたらそのまま聞き流す歌詞をさ。人によって歌がちがってきこえるのは肉体っていうのは批評性を持ってるからなの。そういう装置を。それが声に出るんだよ。だから人の歌って面白い。
――その〝超歌唱セッション〟やチュチュランド・アカデミーや高橋悠治さんとやったりと、ヒカシューと並行して、ずいぶんたくさんのことをやってるでしょう。やりたいことだらけに見える。
巻上 何かやってないとダメなんだよね。貧乏性だから、何でも欲しがる。一番表現しやすいのはヒカシューだけど、まあ乞われるままに。ただ何でもありなの。人の歌でも何があってもいいし。ゆっくり、やりたいことを追い追いやっていって5年後ぐらいには何かに実るんじゃないかな。それは自分でもまったく予想はつかないんだけど、フィードバックしながらやってるよ。失敗しても明るいしさ(笑)。
(インタビュー・構成:やまだりよこ/写真:浅田トモシゲ)

(「花形文化通信」NO.19/1990年12月1日/繁昌花形本舗株式会社 発行)




















