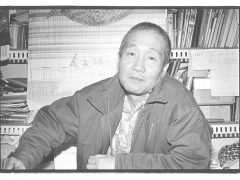1970年に結成された野外劇の雄、維新派。
丸太を組み、何もない空間に劇場を作ることから始まる超総合スペクタクル演劇。
音楽と台詞と肉体と風景がジャンクにからみ、やがてリリカルに去っていく。
今回の公演は久々の本拠地大阪での大掛かりな野外劇。
劇場名は「Kinetic-Theater」。あらゆる装置が移動可能な“動く劇場”。
架空の都市“蒸気の街”で映画制作に励む少年達の物語。
さあ、壮大な書き割りセットが歌い始め、満月はブリキに変わる。
そして白い少年達は蒸気と共に現れる。
――膨大なプロットから想像すると、今回の公演は、80年代後半から松本さんが少年シリーズでちりばめてきたモノのひとつひとつを集大成するように思えるんですが?
松本 集大成……まあ、長い間、野外でやれなかったから。結構ずーっと、温めてたもんはあって。今までは、少年たちの主観的な世界で、あんまり客観的な他社っていうのは出てなかったけれども、今回は兵隊さんたち入れたり、捕虜入れたり、洗濯ばっかりする女入れたりとか、ちょっとドラマチックになってきてるかなぁ。で、そういう中に映画も入れて。僕らとしては、野外でやるエンターティナーとなってるから(笑)。外から見たらごっつみすぼらしいエンターティナーやけども。セットができるだけ動くとか、映画的手法でやるとか、役者よりももっと美術を前面に出すシーンとか、今までのノウハウをさらに加速させたって感じ。
――映画的ってどんな風なんですか?
松本 ズームの感覚とかパンする感覚とか、オフ・スクリーンとか映画的な感覚を、お客さんとの一種の記号の一致でやれないかな、と。お客さんの方に「ああこれは映画のアレやってるな」と思てもうたらそれでええねんけどもね。絶対そんなふうには実際、見えへんねんけど。俺ら、芝居なんてやっぱりそんな見方せえへんし。
――維新派って、どろどろしてるとか肉体主義とか、アングラなイメージがずっとつきまとってきたじゃないですか。でも松本さんの寝かせてたものって、映画的なものとか、本当のものよりも虚構の世界とか、結構クールだったりする。すごく大きい劇場を建てるのも、それだけ大きい嘘がつきたい、できるだけ大きい書き割りの世界を作りたいってことだと思うんですけど。
松本 最近の芝居てセコイもんね。世の中でオウムの事件があったら、オウムのことをすぐに取り上げて脚本にするとか、世知辛いやんか。で、まあ野外に、それも南港みたいな僻地に、お客さん来てくれてるわけやから、一種、都市からの逃亡やからねぇ。だからちゃんと逃亡した、逃亡地を作ったらなあかん。そこまで行ってまたオウムしゃべられたらイヤやんか。僕らも若い時は、そういう夢の話とかね、あるいは架空の国の話とかやったら、逃げてるとかいうて攻撃したこともあるけどもね。でも人間にはやっぱり逃げることっていうのはものすごい大事なことやし、いいトンネルを作りたいなって。
――維新派が生まれたのは、アクションとかその辺の時代ですね。
松本 ある程度のモノがもう飽和状態になって、とにかくそれを壊さなあかんと。戦後の生まれで、自分自身もそうやったけど、テーマ喪失っていうところで、テーマと表現方法の転換とかがさかんに行われた。例えば、平和っていうテーマを劇場で言ってもしょうがないんだと。野外でスッポンポンになって、平和を表現するほうがいいんだっていう。テーマ性より自分がどこに立つか、どんな格好でどういう方法で、と様式を先につかむ。それと美術やってる人はすごく音楽に憧れたりとか、逆に政治やってる人はものすご音楽に憧れたり、そういう時代。垣根を取っ払おうってことはものすごいあった。だからそういう違う才能みたいなもんに刺激されて、維新派なんかは特に自然にそういうことが行われてきたんとちゃうかな。
――大勢で作るから、葛藤とか妥協もあるんでしょうか。
松本 いつも妥協。言うてみればそれが面白いねんけど。そんなにオリジナリティでやってるつもりはないからね。
――プロット見たら、単語がだーっと並んでる。そういう言葉を挙げていくような作業がまず、あるんですか?
松本 最初はだーっとやって、そのうちみんなが喜んでくれるのんをリサーチして。いわゆる工業地帯が好きやっていうのは特殊な自分だけの感覚じゃないしね。
――取って来て、自分のイメージに近いものを集めてきて、共通の記号性の強いものが、残ってくる……。
松本 うん、そうやね。まぁ、それの切り取り方はね、もう分かりやすい切り取り方で具体的な形に変えていきたい。演技ですむところでもちゃんと入れ墨したりとか(笑)。その辺がすごく何というか無粋な世界かなあ。やっぱり粋な方いうたらねえ、すべてパントマイムでやるとか一人の芸でやるとか。落語なんか粋な世界やもんねぇ。座布団の上に乗ってすべてそれでやってしまう。
――そんな粋なイマジネーションの世界に憧れたりも。
松本 ある程度、もうやったもしゃあないっていう気がすんねん。うん。粋はね。粋ってのは、個人的な日常の中で自分の時間で楽しめばええことで、人前に立つもんじゃないと思うねん。
――松本さんって割と演劇の場にいながらすごく音楽的資質とか、絵画的資質が多い気がするんです。
松本 その分、文学的素質がないねん、俺。浪花節的な文学やったら、できるけど。
――維新派は松本さん自身が出演していたいわゆるどろどろの頃と今とは随分変わりましたけど。
松本 そうやねえ、あれはね、やっぱりそれまでね、自分が出とったからね、だから、詩人から作詞家になったみたいなもんやね。あるいは映画監督みたいに。詩人てやっぱり自分の書くこと、内面性とかにものすごい責任持ってるでしょ。自分がやっとったら客観性がなく、見たいものより行為者がやりたいものをやってしまう。客観的な要求っていうことと、ものすごい主観的な要求っていうことの違いやろねえ、確かに、そのどろどろの時代っていうのは主観的な要求。別に世の中がそれを求めるとか求めないとか関係なしに客ゼロでもよかったと思うわ。昔はなんか、芝居でウンコ食べたりもしとってんけど。それは客観的な要求じゃないよね(笑)。
――おシリに傘を突っ込んだりとか、そんな要求は今でもあるのでは?
松本 昔を振り返って「非常にやりたいことをあっけらかんとやっていた」と言う人もいる。それは確かにそうやったと思う。お客さんのことなんか考えてなかったもん。ようこんなん見に来てるな、と思てたもん。僕自身が絵を描いてたから、モノ見せんのにね、チケット売るっていう感覚が未だになじまれへん。画廊なんかチケット切らないでしょう。表現行為にチケット切らないでしょう。お客さんの席とか作らないやんか。だから劇場に入るのに客を並ばせたりしてんのが絶えられへん(笑)。どっかまだ主観的なことやってるっていうのが、あるんやろうね。
――松本さんはもう踊らないんですか?
松本 体力ないわ。まあ体力のいらん踊りがあるかもわからへんけども、大変なことやと思うわ。体一本で舞台に立ついうのは。完全に客観的な思考になっとるから自分をサラシもんにするようなのは、もう(笑)。もともと人前に出るのが向かない人間やねん。露出狂は露出狂やねんけどね。でもものすごい自意識過剰。なんかすぐぱっと冷めてしまうんよ。カラオケなんかもよっぽど酔っぱらわなできへん。すぐ考えてしまうねんな、どう見られてるかを。感情表現てのはようせんなあ。
――昔、舞台に立ってた時も?
松本 客から見たら「完全に切れてると思われてるねんやろな」とか考えながら舞台に立って「寒いなあ」とかね(笑)。せやからごっつ誤解されてると思うけど、至って冷静。(笑)
――周りで踊っている人の中には、切れてる人がやっぱりいるでしょう。
松本 だから気持ち悪かった。稽古でもそういう風な稽古見てたら、演出やってても下向いてんねん。終わった頃に目開けて、やっと終わったって(笑)。やすきよなんかも、やっぱり、やっさんいっつも切れてたやろ、あれ西川きよし大変やったと思うわ。
インタビュー 嶽本野ばら/構成 塚村真美/写真 福永幸治
(「花形文化通信」NO.89/1996年10月1日/繁昌花形本舗株式会社 発行)