
挿し絵:北林研二
柿
一月の終わりに柿の実がなくなった。毎年、大家さんの庭に一本だけ生えている柿がたわわに実をつける。それをヒヨドリやメジロがつつき回して、すっかりなくなってしまうのが、だいたい一月だ。柿というと秋のイメージがあるけれど、鳥にとっての柿のシーズンはむしろ冬ではないだろうか。
つい最近まで、柿が苦手だった。子どもの頃、母親がときどき柿をむいてくれたのだが、ぽりぽりとした硬さとそこから立ち上がってくる匂いがどうも口に合わなくて、一切れか二切れでもうごちそうさまだった。その後、石田三成が死に際に差し出された柿を断ったという逸話を読んで、三成に特段肩入れしていたわけではないが、死に際に断られる食べ物なら無理に食べなくてもいいやと思った。以来、自分から好んで柿に手を出す気にはならなかった。
正岡子規の「くだもの」という随筆には「樽柿ならば七つか八つ」とあって、いかに無類のくだもの好きとはいえ、七つとか八つは食べ過ぎではなかろうかと思ったことがある。しかも三時のおやつに食べるとかいうのではなく、「二ヶ月の学費が手に入って牛肉を食いに行たあとでは、いつでも菓物を買うて来て食うのが例であった」という文のあとに続けて「七つか八つ」なのだからどうかしている。柿が苦手な人間には、想像を絶する景色だ。
「くだもの」には「御所柿(ごしょがき)を食いし事」という話も載っている。子規が病を推して奈良を訪れた際、これまたすでに夕飯を食べ終えたあと、宿屋の下女に御所柿を頼んだら直径一尺五寸、というから四、五十センチはありそうな丼鉢に「山の如く」柿が盛られてきた。柿をむいてくれる女のややうつむいている顔がほれぼれとするようで、柿もうまい、場所もいい、と、ボーンと釣鐘が鳴る。女が「オヤ初夜が鳴る」と言いながら、さらに次の柿をむきつづけている。

むかし「柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺」という句のことを、なんとなく昼間の茶屋の店先で、八等分くらいに切った柿をちょっと囓ったという印象で捉えていたのだが、「御所柿を食いし事」を読むと、夕飯も終え、あたりは暗く静かで、そこに鐘の音が鳴る。鐘は法隆寺ではなく東大寺である。そして柿を食う子規は、病身とは思えぬほどの食欲である。病なのに柿なのか、柿という病なのか。
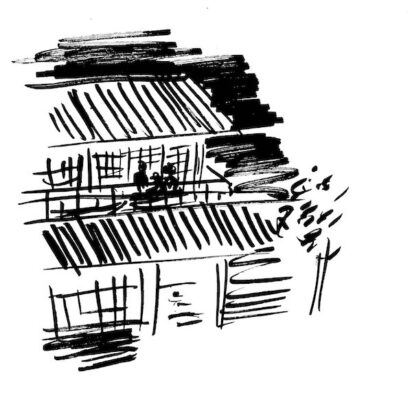
東京に越してきてから数年後の晩秋、大家さんから庭の柿を分けてもらった。ありがたく受け取ったものの、食指が動かず、しばらくテーブルの上に放っておいた。そのうち、すっかり熟し切って皮を押すとぶよぶよになり、さすがに捨てるわけにもいかず、仕方なく半分に切ってみた。中はもうとろとろになっており、切り分けることもできず、スプーンですくって舐めてみた。
これがびっくりするほどおいしかった。
ジャムがそのまま果実の形になってしまったかのような濃い甘さとともに、例の、柿独特の匂いがやってくる。やってくるのだが、それがあまりに甘くて、苦手が裏返ってしまった。むしろその匂いを核にして、甘さがより引き立つ気さえした。そうなると、これまではいちいち感じないようにしていたタンニンから来るのであろう渋みも、崩れきっていない果肉の弾力も、魅力に思われてきた。
気づくと一個をあっという間にたいらげていた。これならば七つ八つは無理としても二個三個と食べることができる。
ネットで検索してみると、甘柿には「マスカルポーネ」をあわせるとよい、とある。マスカルポーネってなんだ。アルカポネと音が似ている。イタリアの食べ物だろうか。いつも行くスーパーにそんな凝った名前のものがあったかしらんと訝しんだが、チーズやらクリームやらが並んでいる中に、ぽつんと一個置いてあった。マスカルポーネは乳製品だった。

舐めてみると、塩味も砂糖味もない、ねっとりとしたクリームチーズという感じだった。本当にこれを柿と一緒に食べるのだろうか。スライスした柿をあわせて蜂蜜などをかけるとよいらしいのだが、あいにく果肉にそれだけの硬さはない。小皿の左にマスカルポーネを載せ、右に半分に切った柿を載せると、白と橙の兄弟みたいだ。試しに白をスプーンの先でちょいとすくって、そのままとろとろの柿もすくって、一度に口に運んでみる。
なるほど、これはうまいものだ。
マスカルポーネの粘り気から、乳の成分が溶け出して、柿の甘味とあわさるのだが、その配分が舌の上で刻々と変化していく。どういうことだろう、どういうことだろう、と思いながら何匙もすくってしまう。微かな渋みもさらなる甘味を引き立てているらしい。ちょっと蜂蜜を垂らすと、さらに甘さがゼイタクになる。
こんなにうまいものならもっと食べたい。しかしマスカルポーネの方はまだまだ余っているが、柿の方がなくなってしまった。
以前、大家さんから、なってる柿は勝手にもいでもいいですよと言われていたのを思い出した。けれど、手の届くところになっているやつはすでに取り尽くしていた。
それからほどなくして、大家さんとばったり会ったので、柿のお礼を言ってから、手の届かない実は全部鳥が食べちゃうんですよね、と言ったら、「じゃ取って食べたら?」と何でもないことのようにおっしゃる。「高いとこは、高枝切りバサミがあるから」。
高枝切りバサミ!久しぶりにその甘美なことばの響きをきいた。かつてのテレビショッピングの人気商品。映像ごしには何度となく見たことがあったけれど、自分で使ったことはなくて、なぜそんなに売れるのかいまひとつ実感できなかった、あの高枝切りバサミを、まさか大家さんがお持ちだったとは。
ハサミは、柿の木のすぐそばの物置小屋の傍らに立てかけてあった。しょっちゅう通り過ぎる場所なのに、これまでそんなものがあるとは気づいていなかった。大家さんは、柄をしゅるしゅると伸ばし、手元のハンドルの安全ロックをはずし、二、三度握ってハサミのアクションを試す。思わず「ちょっとどうなってるのか見てもいいですか?」と先の形を観察した。わたしの記憶では、これはただ枝を切り取るだけのハサミではない。「切った先の枝を落とさずつかめる優れもの」なのである。見ると、ハサミの横には幅の広いペンチの先のような、平たい金属板がついていて、ハンドルを握ると、ハサミが枝を切ると同時に金属板が切り口の少し横を挟む。それで、「枝をつかめる」のだ。
大家さんがお手本代わりに柿を一個切り取ってくださる。切り取っても柿は落ちない。まるで高枝切りバサミが一本の長い枝で、そこから短い枝が生えて柿がなっているみたいだ。交代させてもらって、自分でもやってみる。最初は落とさないように、ハンドルに不必要に力を入れて手が痛くなったが、だんだんコツがつかめてくると、それほど強く握らなくても、一度つかんだ柿は簡単には落ちないことがわかった。どんどん試したくなり、調子に乗ってかなり高いところのやつまで切り取った。
たくさんとれたので、大家さんと分けて、さらに知り合いにもおすそわけした。手渡すときに、マスカルポーネ、という使い慣れないことばを言ってみたら、ああ、と知っている風だった。わりと有名な取り合わせらしい。
木のてっぺんにはまだいくつも残っていて、それもハサミの柄を伸ばせば切り取れそうだったけれど、鳥たちのために放っておいた。
鳥は、秋の硬い柿はついばまない。樹上になった実がどろどろに熟してから、ようやくつつき始める。だから鳥にとっての柿の食べ頃は、十二月から一月ごろになる。
いまやわたしにとっても、柿は冬の食べ物である。
(2/17/26)
これまでの「東京なでなで記」はこちらから




















