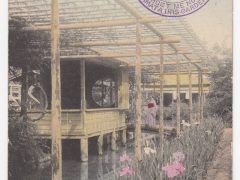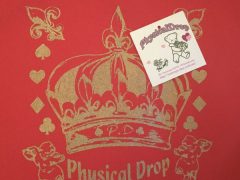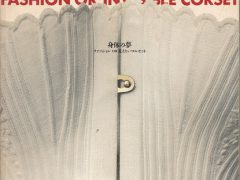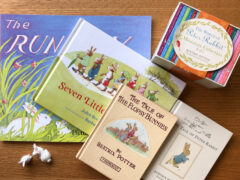「スパイラル」エスプラナードの階段(2024年撮影, 東京)
「スパイラルの階段」
文・写真・図 下坂浩和
槇文彦(1928-2024年)設計の複合商業ビル「SPIRAL」が建築雑誌に取り上げられたのは、1986年1月号でした。前年に展覧会で模型を見て、その外観に驚き、工事の様子を眺めに出かけたりもしていたので、ついに出来上がったのだな、と思ったのをよく覚えています。展覧会にあわせて出版された小冊子(『THREE PROJECTS IN PROGRESS』)に何枚も掲載された初期段階のイメージスケッチを見て、最初はファサードを左右対称にまとめようとしたが、あるとき突然、最終案のように積み木をランダムに積み上げたままのほうが良いと気づいたのではないか、とデザインプロセスを勝手に想像したものでした。

「スパイラル」外観(2024年撮影, 東京)
そして完成した建物を見た時は、その複雑なデザインにもかかわらず、外装のアルミパネルやサッシが割付から詳細寸法にいたるまで破綻なくおさまっていたことに、もう一度びっくりしました。この外装は、下のほうは右から左へ、その上は逆に左から右へと上昇する階段状に構成されていて、下方の右下から左上へのガラス部分は、1階のギャラリーから2階のショップ、さらに3階のホールへと上るエスプラナードと呼ばれる階段状の屋内空間で、その空間がそのまま外観に表されているのです。
スパイラルというビルの名称は、1階の奥にある2階へとつながる螺旋状のスロープから名づけられたのでしょうが、この外観に表れた階段も、1階のエントランスから入ると、平面上に「の」の字を描きながら上昇する空間で、このビルのもうひとつの螺旋と言うこともできます。

1階ギャラリーから青山通り方向に向かう階段(2025年撮影, 東京)
前回までに村野藤吾と丹下健三をそれぞれ「温かみのある」「クールな」デザインとして取り上げましたが、その間の「ちょうど良い」デザインはないのか、と考えたときに思いついたのがこのスパイラルの階段でした。目盛りで測って中間、というよりは、温かみとクールさの両方の良さをあわせ持つデザインと言うこともできます。
直線の組み合わせでデザインされた階段ですが、1階奥のギャラリーから手前の青山通り側に向かって上がる幅広の階段は、ほんの少しですが両側の壁が先に行くほどすぼまりパースペクティブが強調されていて、ウィットを感じるとともに、天井の曲面とも相まって柔らかな印象を受けます。仕上げ材料には大理石、ステンレスなどの硬質な素材と柔らかなカーペットの両方が使われています。

壁際を見ると奥にすぼまっているのがわかる(2025年撮影, 東京)
道路に面したガラス張りの部分は、階段が5段、6段、9段に分割されていて、それぞれの間の長い踊り場にはこの建物ができた時から椅子が置かれています。ベンチシートではなく、少し距離を保って置かれたひとり用の椅子ですが、ここには、いつ行っても必ず何人かの人が座っていて、本を読んだり、ボーッと外を眺めたりしています。ガラス越しに2階の高さから風景を見下ろすことができる居心地の良い場所で、椅子をふたつ近づけて座っている人たちを見かけることもありますが、ひとりの人がほとんどで、静かに街と向き合うことができる都会ならではの場所なのです。

今とほとんど変わらない竣工直後の様子(1987年撮影, 東京)
ところで、スパイラルができて少したった頃、まだ学生だった私は大学図書館の書庫で何時間もかけて、建築雑誌のバックナンバーを順番に遡って見たことがありました。気になる建築家の作品を見つけては、ページを繰る手を止めて解説文をじっくり読んでみたのですが、槇文彦設計の代官山ヒルサイドテラス第3期計画が掲載された『新建築』1978年4月号に寄せた、槇文彦自身によるテキスト「遠くから見た「代官山集合住居計画」-代官山の3つの計画を通して-」の「第2期の計画の頃」という部分に、以下の文章を見つけました。
「ひと昔前のフランスのジャック・タチがつくった “Mon Oncle(ぼくの伯父さん)”という映画の中で、様ざまなかたちで近代建築の風刺がなされているが、タチが扮する主人公が、4階建ての建物のペントハウスに昇って行くのに彼の姿が表れたり、隠れたりするのが現代建築の空間の透過性を揶揄していて面白かった。」
この文章の中で、代官山ヒルサイドテラスの第2期の建築を「ジャック・タチ型」と呼んでいたのです。これを読んだ私は椅子から転げ落ちそうになりました。私自身『ぼくの伯父さん』は大好きな映画でしたから、この文章が発表された9年後に竣工するスパイラルのファサードが、代官山の第2期以上に、この伯父さんの住むバラック風建物を彷彿とさせることに気づいたのです。実際に見比べてみると、外観がそれほど似ているわけではありませんが、非対称のファサードを右下から左上へ、そこからさらに右上へ、と上がるところが、伯父さんの上っていく動きが外から窓越しに見える様子と、そっくりに思えたのです。

「スパイラル」外観(1987年撮影, 東京)

伯父さんはジグザグ状に階段を上りながら、数字の窓やバルコニーで姿を表す
『ぼくの伯父さん』はご存知の方も多いと思いますが、主人公の少年が住む両親の建てた家は「クールな」デザインで、伯父さんの住まいは貧しくも「温かみのある」建物です。監督のジャック・タチは自身が扮する伯父さんの側を人間味あふれる様子で描いているのですが、この映画がつくられたのは1958年で、まだ建築の分野でモダニズム批判が提起される以前でした。
スパイラルに関する槇文彦の著述の中には、この映画に言及したものは見たことがないので、それだけに一層「スパイラルのファサードが非対称のデザインになる過程で、ぼくの伯父さんの家に影響を受けたのではないか」という勝手な推測を、私は信じて疑わないのでした。
(2025年6月22日)
- 下坂浩和(建築家)1965年大阪生まれ。主な設計実績は「稲荷の家」(2014年)、「吉川英治記念館ミュージアムショップ」(2004年)ほか。2024年まで勤務した日建設計で担当した主な建物は「大阪市立東洋陶磁美術館エントランス棟」(2023年)、「W 大阪」(2020年)、「六甲中学校・高等学校本館」(2013年)、「龍谷ミュージアム」(2010年)、「宇治市源氏物語ミュージアム」(1998年)など。
これまでの「うつくしい階段」はこちらから
「ぼくの伯父さん」はU-NEXTで視聴できます