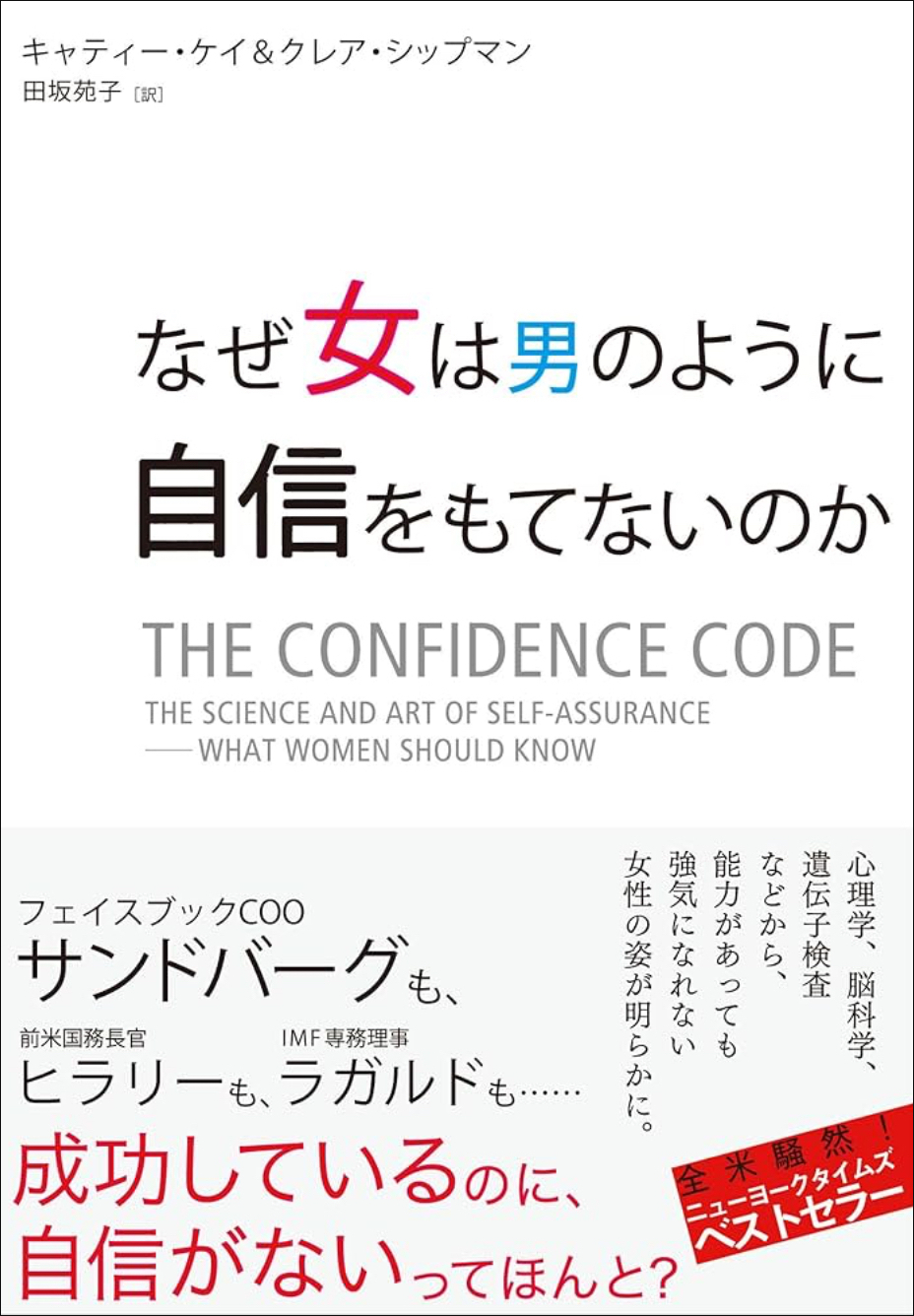鈴木さんの『離人小説集』(幻戯書房)には、7つの短編小説が収められ、どの作品にも作家や文学者が主人公や語り手として登場します。第1回のインタビューでは、この小説が書かれたきっかけについてお話いただきました。
第2回からは、個々の作品に出てくる作家たちとそのイメージについて、たっぷりとお話をうかがっていきます。まずは芥川龍之介と内田百閒の奇妙な友情を描く「既視」、右脚を切断したアルチュール・ランボーの「丘の上の義足」、稲垣足穂が神戸を歩く「ガス燈ソナタ」の3作品です。(丸黄うりほ)

「既視」の芥川と百閒。奇妙でちょっと例のない二人の関係
——ここからは7つの作品について順にお話をうかがっていきたいと思います。最初は芥川龍之介と内田百閒が登場する「既視」です。
鈴木創士さん(以下、鈴木) 芥川龍之介のことをボロクソにいう人もいるけど、僕はきれいな人だったと思っています。で、内田百閒は芥川の親友で、同じ夏目漱石門下なんだけど、すごい偏屈で。税務署が差し押さえにきてるのに行きつけの蕎麦屋でしか食わないとか、そういう人。で、彼は怪談を書いている。
それで、僕からみたら友情だと思うんだけど、奇妙で、なんかちょっと例のない二人の関係を書きたいというのがあった。で、やっぱり芥川が自殺したっていうのも大きくてね。僕は、自分が自殺しようと思ったことも若い頃は人並みにあったけど、自殺した作家というのにすごい興味がある。たとえば、アントナン・アルトーなんかは自殺を否定しているんですよ。自殺の選択肢はないっていう強いところのある人で。それに比べると芥川っていうのは頑固だけどものすごい弱いものに取り囲まれているようなところがある。ただ作家としては僕はすごく才能のある人だと思っていて。その奇妙なふたりの関係を書きたかった。ま、ここに書いていることはほとんど事実。最初に出てくる坂道も田端(東京都北区)っていうところに実際にあります。
——芥川龍之介が、完璧なヤク中に書かれていますね(笑)。
鈴木 いや、完璧にヤク中ですよ。あのころは睡眠薬もほとんど麻薬に近いような強力なのしかなかったから、睡眠薬中毒も麻薬中毒と一緒。芥川はほかのものもやってます。エッセイとか読んでると、こんなんクスリやってなかったらなんでわかるの?ってあるしね。この時代の文学者は多いですよ。まあ、坂口安吾みたいに意図的に覚醒剤と睡眠薬を常用する、それで書くっていう感じではないかもしれないけど。
——ヤク中の芥川と偏屈な百閒が会話をして、「君は怖いよ」と言い合って、お互いを牽制しあっています。
鈴木 そうなんですよ、だから友情なんだけどお互い忌避しているようなところもあって。芥川は随筆とかを読むと、発狂するのが怖かったらしい。お母さんが発狂したみたいで、自分もそうなるんじゃないかっていうのがずっと怖かった。でも、百閒をみると、おまえのほうが狂っていると思っている。「君はおかしい。見てると怖くなる」って。そういうやり取りは、彼らの書いたものの中にも出てくるんですよ。
——この二人の関係、私は読んでいると鈴木さんと中島らもさんが浮かびました。
鈴木 ああ、そういうの意識はしてなかったけどあるかもしれないね。
——らもさんが芥川、私のイメージでは。で、偏屈の百閒が鈴木さん(笑)。
鈴木 百閒はすごい変な人で、あれは女性からみたら嫌いだろうと思うけど。
——(笑) 作品は女性にも人気がありますが。
鈴木 作品は面白いけどね、「冥土」とか。猫が好きでね、汽車とか。意識はしてなかったけど、そういうのが出ている可能性はあるな。
——鈴木さんのご著書『中島らも烈伝』(河出書房新社)の最初のほうに、らもさんが亡くなったと連絡が入ったというところがありますよね。この作品でも、芥川龍之介が亡くなったという連絡が百閒に入って……。
鈴木 ああ、そうか。
——不思議な感じの友情関係にあった二人、たんに仲が良いというだけではなく、牽制し合うようなところもあって。
鈴木 そうですね、らもとは殴り合いの喧嘩したこともある(笑)。
——そのくらいの相手が先に逝ってしまったときの、百閒の取り残され感が……。
鈴木 いや、それはあるかもしれないね。芥川の家族が立っているイメージとか、意識してなかったけど、言われてみれば僕の中にそういうイメージがあるのかもしれない。
——なので、これはもちろんモデルは芥川と百閒なんだけれど、鈴木さんご自身のことを書かれているのかもしれないと思いました。
鈴木 うん、そうかも。らもくんが亡くなったのも夏だったしね、いま言われてみて初めて気づいたけど。確かね、僕『中島らも烈伝』の中で百閒の引用してる。2行くらいだけど、芥川が死んだのも暑い夏だった……みたいな。百閒の俳句かなんか。
猛暑にはかならず人死にがある。真夏の死。何十年も前に、芥川の死んだ夏…。
亀鳴くや土手に赤松暮れのこり 百閒
(『中島らも烈伝』p.10)
——亡くなったことを知った瞬間の、時間が凍ったみたいな気配。
鈴木 イメージってね、もともとの意味ではすごい難しい言葉なんだけど、イマーゴっていうラテン語からきてるんです。像、映像のことですね、もともとは物理的な像のことなんです。で、ギリシャの哲学者が言っているのは、ものが見えるっていうのは、ここからイメージがはがれて目に飛び込んでくるんだって言っているのね。僕は絵とか美術も好きだからそういうことも考えるんだけど、イメージっていうのは頭の中で思い描いているというよりも、たとえばこのイメージね、僕らがここにいてこうしゃべっている、これって要するに光が起こしていることんなんだけど、このイメージっていうのは永久に消え去らない。もし宇宙人が望遠鏡でのぞいてたらさ、これが見えるわけですよ、ずっと旅するわけですよ、イメージって、そういう物理的な面ももっている。だから僕らも星が見えるわけですよ、同じことです。高性能の望遠鏡で宇宙人がこの姿をのぞいていたら、何万光年か後にこの姿が見える。すごい物質的なものなんです、イメージって。
だから、ただ僕が頭に思い描いているだけじゃなくて、そういう像が残っている感じがずっとしてて。らもが亡くなった時も、火葬場に行ってみるとめっちゃ蝉が鳴いてて……。ああ、そう言われると、これと一緒だね。
「丘の上の義足」、ランボーのイメージはボウイの曲が鳴り響く火星
——2作目は、アルチュール・ランボーが登場する「丘の上の義足」です。
鈴木 ランボーっていうのは大変な人。ものすごく頭のいい男だったと思う。10代で詩を書いて20歳くらいでやめちゃう。彼は外の世界に行きたいとずっと思ってた。フランスが嫌いだったんだね。で、商人っていうかいろんなことするんだけど、それこそサーカスにつとめたりとか。最後はアビシニア、今のエチオピアです、ここに行って武器の商人になって、で、全部騙されたりしてね。最後は癌になってフランスに運ばれて脚を切断して、義足になっちゃって死んじゃうんだけど。
僕にとってランボーのイメージっていうのは、火星なんですよ。岩がごろごろしていて草も何も生えてない赤い丘みたいなところにランボーが浮いててね、で、そのバックにデヴィッド・ボウイの曲が、何の曲かわからないんだけど、大音量で鳴り響いているイメージがあってさ(笑)。
ランボーには、やっぱり脚のこともあってね。彼も放浪者だから、ずっと散歩してる。歩き回ってて、思考のスピードもものすごく速いんです。それが詩に現れてる。僕はランボーも翻訳しているんですけど。いままでの翻訳もいいのもあるんですけど、僕はめっちゃ忠実にやったんですよ。なぜかというと思考のスピードを出そうと思って。それは直訳でしかできないから。意味っていうのがあるから、わけわかんないとダメだからそこは別問題なんですけど。とにかく思考が速い。
だから、5年くらいしか詩は書いてないんだけどその間に老成しちゃってると思うんだよね。で、やはりあれほどの天才だから、きっとアフリカに行っても詩を書いてたに違いないとかいう研究者がいまだにいるんだけど、僕はまったくそう思ってなくて、一切書いてないと思う。あれでやめたし、最後の作品なんか読んだらあれ以上のことは書けないと思う。人間って無限に書けるわけじゃないから。そういうタイプの人ですよね。
それで、昔はランボーを読んで文学青年になるっていう人が多かったんだよね。僕も若い時にランボー読んでいかれちゃったんだけど、言うのが恥ずかしくてね、ずっと隠してた(笑)。フランス文学やりだしてからも、自分からはランボーの研究とか遠ざけてたんですよ、なるべく影響受けないでおこうと思って。影響受けてるのはわかってたけど。でも、それは翻訳で読んでたからね、小林秀雄、中原中也、金子光晴……いろんな訳があるんだけど。
ただね、年取ってもういちど原文読んでみようと思って、読んで2回目にほぼお手上げ状態みたいになって。これ作品としてもすごいなと思って、もう脱帽。それでね、翻訳したんですよ。だからこの人とのつきあいも結構長いんだけど。若いから感受性はみずみずしいんだけど、思想的にはおじいさんみたいに老成している。
彼はフランスで生きている間に有名になるんですよ。ポール・ヴェルレーヌとかが見つけて雑誌に出て。で、アフリカでも連絡がくるんですよ、大使館に呼び出されて、君があのランボーか?とか聞かれて。証言でも残っているんだけど、眉ひとつ動かさなかったらしい。知らんって言って。原稿依頼もきてたけど全部拒否してる。もう書く気は無いと。
面白いのは彼の妹の証言。脚切って癌だから痛みがひどくて、モルヒネ打ってせん妄状態になっていたときに、ずっとうわごと言ってたんです。で、あとでわかったんだけど、それは最後に書いた『イリュミナシオン』の言葉だったって。だからランボーは詩を捨てたけど、詩のほうはランボーに取り付いていたんです。言葉が取り付いて、たぶん刺青みたいになってたから、うわごとに出てきた。晩年の手紙なんか商売のことばっかりなんですよ、文学のことは一切書いてなくて。
——うわごとっていうことは、無意識レベルでは詩が残っていたってことですね。さきほどおっしゃっていた(インタビュー1/5)、ランボーの「私は一個の他者である」という言葉も気になるんですが。この7つの小説のラインナップのなかにランボーが入っていたのは、その言葉があったからなのかなと。
鈴木 そうですね。やはり「離人」ということを考える時に、それはひとつあったかもわかんない。
——この7つの小説がなぜこの人選だったのかなって思うんですけど。
鈴木 いや、もっと候補はあったんですけどね。ルイ・オーギュスト・ブランキとかジェイムズ・ジョイスとか。
——身体性ということでランボーは欠かせなかったということですね? 脚のこと。歩くシーンも多いですし。
鈴木 そう、ずっと歩いてるんですよ、歩きすぎた。それで、脚を切断してね。で、火星でランボーが浮いてる夢見たときに、僕も右脚が悪くなってね。ランボーにお祈りして、おまえの本を訳すから治してくれよって言ったんだけど治してくれない。(笑)
——ランボーが切断した脚は、どっちですか。
鈴木 右。右脚切断してる。
——ああ!それもなんか、つながりを感じますね。
鈴木 だから肉体にくるんですよ。人を好きになるっていうのは肉体的なこともあるじゃないですか。それとそんな大差ないかもしれない。肉体が入ってくるんですよ。だって男性が女性とそういうことになる時でも相手の肉体に入るっていうの、あるでしょ。だから肉体的なものって自分たちは気づいてないけど、精神的なものにもいっぱい入り込んでいる。むしろ、そういうもので精神的なものができてるっていうところもあるから。でも不思議なのは僕はべつにボウイの大ファンってこともないのに。
——ボウイがランボーを好きだとか?
鈴木 かもね……。ボウイはジャン・ジュネが好きだったらしい。会ったこともあるみたい。映画をつくる話もあってポシャったみたいだけど、ボウイに主役させようとしてた。待ち合わせして、ボウイが来てないってなった時も、ジュネはすぐわかったみたい。ボウイは女装していた。
この本にもジュネを入れたかったけど、泥棒だし、エキセントリックだから逆に難しいんですよね。ジュネも思考的な部分が多くて難しいんだけど、彼の肉体があって、それが人生そのものみたいな本だから。それ以上のものが書けないから、戯画的になっちゃうかなと思ってやめちゃったんだけどね。
ダメになった足穂が神戸を歩く「ガス燈ソナタ」
——次は稲垣足穂モチーフの「ガス燈ソナタ」です。
鈴木 足穂はね、彼も僕も神戸出身というのがあって、若い時から足穂がトアロード歩いてるイメージがあります。これも散歩なんだよね。
——そうですね、これは完全に散歩の小説ですね。
鈴木 これはエミルっていう主人公なんだけど、足穂の「彌勒」っていう小説の主人公の名前なんですよ、まあ足穂自身のことだと思うけど。で、彼は、すごい抽象的な思考ができる人なんだけど一方では男色とかね、アルコール中毒とか(笑)。 抽象的な思考が基本なんだけど、それが全部具体的な、それこそ身体的なところから出てきてる。たとえば「彼等(they)」っていう小説があって、それは香水の話で、僕もそこからとってこの小説を空の香水瓶の話からはじめてる。「彼等(they)」ってものすごくきれいな小説だけど。
まあ、足穂が神戸にいたときはまだまともだったと思うけど、「ガス燈ソナタ」は、もうダメになった足穂が神戸に来たという話にしたんです。だから耳元で「むかつく」という声が聞こえたりとかね(笑)。それはもうアル中の幻覚なんだけど。で、足穂っていうのは人に絶対涙を見せたりしないダンディな人で、そんなことは本当はなかったんだけど、この小説では最後に泣かしたんですよ。涙を流すっていうのを書いて、足穂ファンはうっとくるかもしれないけど、わざとね。
——この小説は7作品のなかではパスティーシュ的というか、足穂が使いそうな言葉とかアイテムを使っていますよね。なので、足穂のファンにも楽しめる要素が濃いなと思いますが。
鈴木 そうね。ただ、お月さんをピストルで撃ち落とすっていうのは足穂にはない。僕の創作ですね。
——足穂もアル中ですよね。登場人物たち、ここまで全員なにかに酔っ払いながら歩いている感じです(笑)。
(5月12日、神戸市内で取材。協力:アビョーンPLUS ONE。写真: 塚村真美)