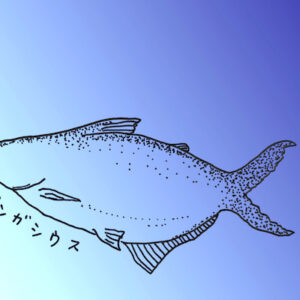昨年と一昨年のお正月、カルタ取りで伯母に連敗を喫しているので、今年は勝つぞと、旧年中はほぼ毎日一度は百人一首の本を開いて対戦に臨んでおりましたが、さすがに自粛の正月。伯母はステイホーム、よしんば来られたとしても、カルタ取りでの三密は避けられそうにありません。
「みかきもり 衛士のたく火の夜はもえ 昼は消えつつ ものをこそ思へ」 大中臣能宣(おおなかとみのよしのぶ)49番
この一年ぱらぱらとめくって読んだ百人一首の本というのは「田辺聖子の小倉百人一首」(角川文庫)で、一首一首、現代語訳と4頁ほどの解説がついています。単なる逐語訳や読み人の説明ではなく、少女時代から蓄積された氏の豊かな教養と感性が薫じられ、多少の想像を織り交ぜながら、ユーモアでもって届けてくださっています。それら百ある解説のうち、この49番が私には一等面白く、ここだけは何回も読みました。
「衛士のたく火」からの連想で、おせいさんはまず『枕草子』にある「火炬屋」の記述をさらりと引かれます。ほんの数行の中に、清少納言の動きを廊下の隅から見ていたかのような描写。ともかくここで、宮中で警護のために夜通し焚かれるかがり火をイメージすることができます。
次の段落は「衛士」について。重要な任務は皇宮警護であること、応募ではなく全国から選抜された優秀な兵士であること、三年交替であったかも、ということを資料をもとにご紹介くださいます。そこで勝手に連想してしまうのが、『ベルサイユのばら』に登場する近衛兵のオスカルやアンドレ。国や時代は違えども、品格の備わった、胸板のそこそこ厚い男前を思い浮かべるのです。
さて、ここから、おせいさんは話を百人一首から『更科日記』へと転じます。『更科日記』に書かれた、衛士にまつわる「竹芝寺」の物語について、ほぼ2頁弱、紙幅の約半分を費やされています。ここの部分が大好きで、おせいさんに紙芝居を読んでもらっているみたいな気分で、アニメのごとく脳内に、ロマンチックな映像が流れます。
シーン1 御殿の庭を、衛士がひとり掃いている。
シーン2 衛士はブツクサつぶやく(このセリフはぜひ、田辺先生の現代語訳でお楽しみいただきたい)、「仕事が辛く、故郷に帰りたい」と。
シーン3 衛士の語りにあわせて、故郷の風景を再現――武蔵の国。ずらり並ぶ酒壺。その上に引っかけられたひょうたんのひしゃく。それが風になびいて揺れている。
シーン4 御簾の影から、そのつぶやきを聞いていた姫君(星飛雄馬のお姉さんよろしく)、「近う寄れ」と衛士を呼ぶ。
シーン5 姫はもう一度話を聞かせるよう衛士に言い、衛士はいま一度話をする。
シーン6 「連れて行って」と姫が言う「それを見せて」。衛士は断る。「気まぐれではない」と姫。衛士はこれは何かと縁と思い、姫を背負う。
シーン7 走る走る、衛士は走る、東へ東へ、武蔵の国へ。
さあここで、おせいさんのワンポイントが効いてきます。「天皇も皇后もあちこち捜されたが、このとき耳よりな情報が入った。この原典の文句がいい」と。一人で『更科日記』を読んでいたらスルーしたに違いない一文です。「武蔵の国の衛士のをのこなむ、いと香ばしき物を首にひきかけて、飛ぶように逃げける」
「逃げる二人のスピードが思われる」とおせいさん。「姫君のたきしめていられた香が、あとへ残っただけで、さだかにその「物」は見えなかった」と。
そこで、シーン7には、劇画タッチの斜線が入ります。それが動く。高畑勲監督『かぐや姫の物語』で、姫が駆けていくシーン、あのスピード感と重なります。もう、衛士の太い首にしがみついている姫君の姿は、ジブリのかぐや姫になってしまうのです。そして、香の匂いを想像し鼻がくすぐったくなるのでした。
49番の歌にある衛士のたく火のように、パチパチと夜に燃えてくるような恋心はすでになく、夜になるとくすぶっていた恨み辛みが燃えてきて眠れなくなるようなことはしばしば。
田舎生まれの夢見る文学少女が「おばすて」の年ごろとなって一生の思い出をつづった『更科日記』。私めも「姥」という字がふさわしい年齢を迎える、そうめでたくもないお正月ですが、菅原の孝標のむすめさまの日記を最後までしみじみと読めるような年ごろとなったことは、たいへんうれしく思うばかりです。
by 塚村真美