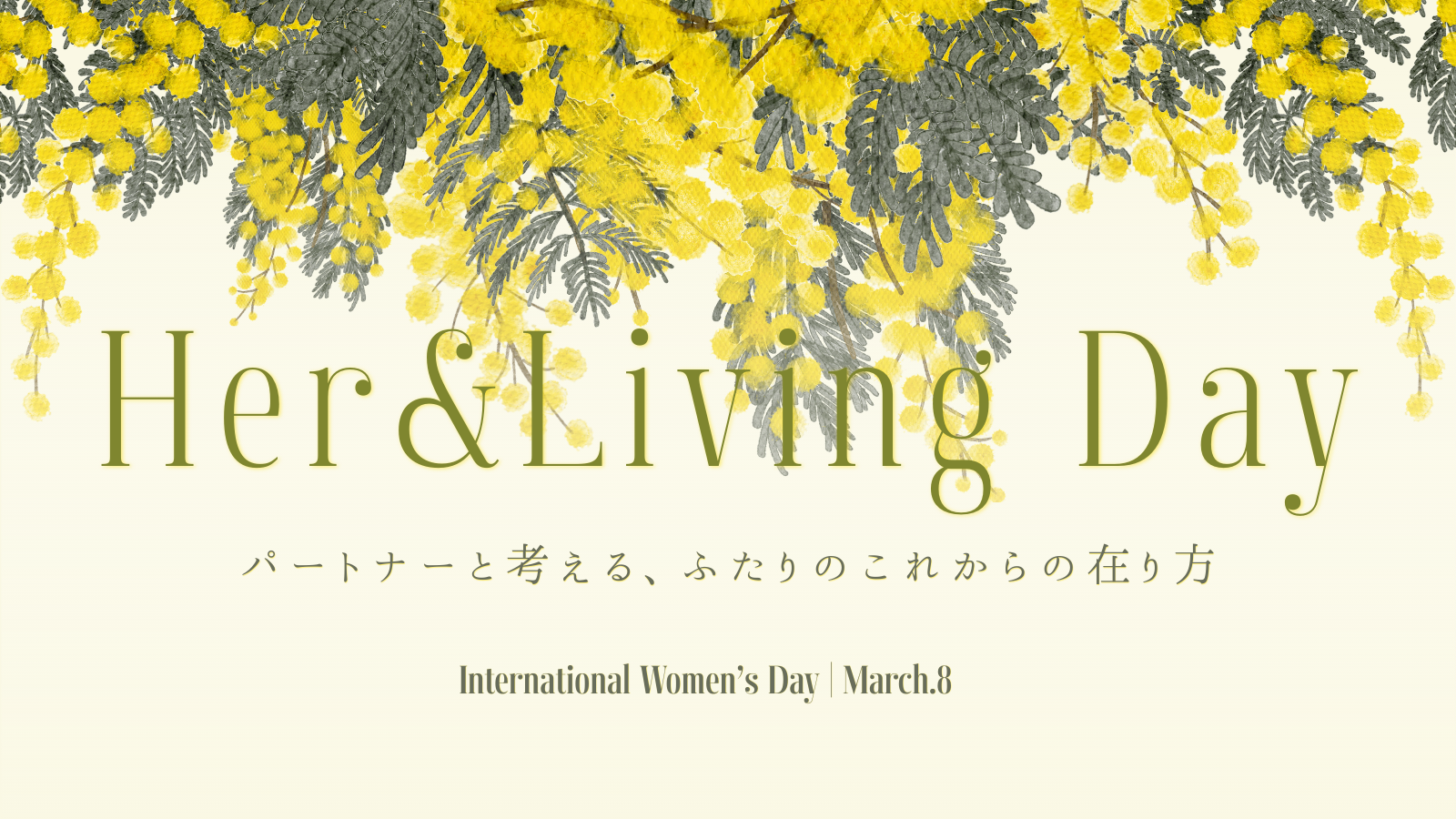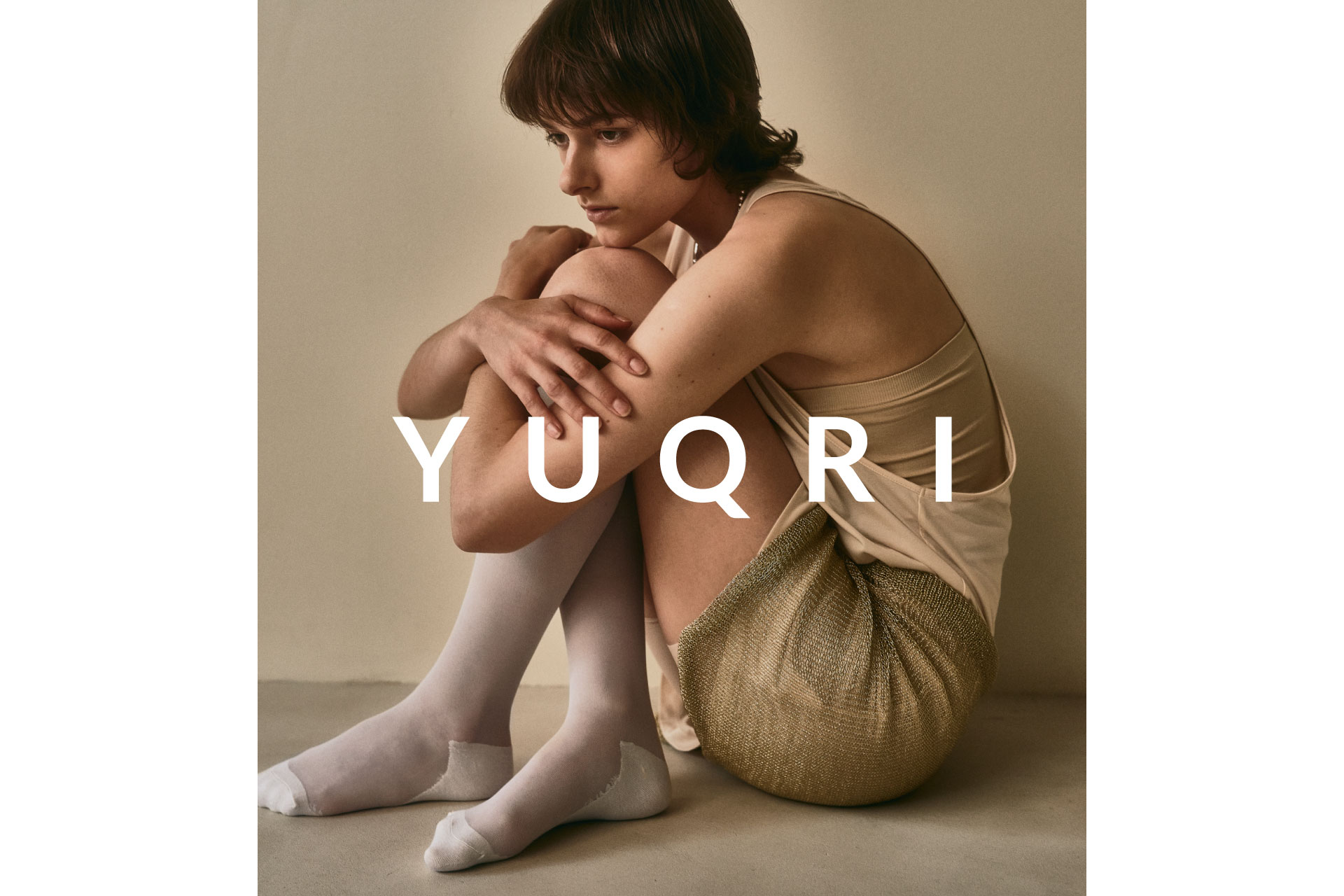バンジョーのルーツはひょうたんだった!
by 丸黄うりほ
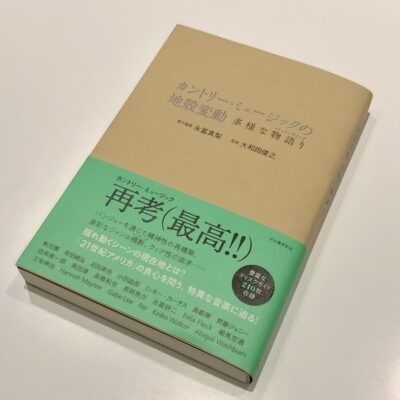
『カントリー・ミュージックの地殻変動 多様な物語り(ストーリーテリング)』責任編集:永冨真梨、監修:大和田俊之(河出書房新社)
年明けの「ひょうたん日記」(1月15日 、 16日)で、彦根市の「山の湯」に行ってきたことを書きました。目当ては湯浅学さんと安田謙一さん、そして細馬宏通さんによる「新春放談♨」。トークショーが始まる前に、細馬さんが私に話しかけてくださいました。
「最近出た本に、ひょうたん楽器について書いたんですよ」
えっ?ひょうたん楽器?
それは読ませていただかないと!
……というわけで、きょうはその本『カントリー・ミュージックの地殻変動 多様な物語り(ストーリーテリング)』(河出書房新社)を紹介したいと思います。
カントリー・ミュージックといえば、私などはアメリカの田舎に住む白人のおじさんたちが好む音楽だという認識で、日本人にはアウェイなイメージ。どちらかというとあまり積極的には聴いてこなかったジャンルです。ところが、ビヨンセのアルバム「Cowboy Carter」(2024年)がビルボード誌のカントリー・アルバムチャートで1位を獲得するなど、最近このジャンルに地殻変動ともいうべき動きが出てきているようなのです。
この本では、そうしたカントリー・ミュージックの現在地をふまえつつ、カントリーに関わる活動をしてきたミュージシャンのインタビュー、対談、鼎談、研究者によるエッセイ、音楽評論家やミュージシャンによるディスクガイドまでが5つの章にわけて収められています。責任編集の永冨真梨さん、監修の大和田俊之さんのほか、執筆者として、またインタビュー、トークなどに登場する人々は総勢22名。日本で活動してきた人もいれば、アメリカで活躍中の人もいます。
細馬宏通さんのエッセイ「バンジョー史を捉え直す——ビヨンセからリアノン・ギデンズへ」は、第4章に収められていました。
細馬さんはビヨンセの「TEXAS HOLD ‘EM」(YouTubeへ)を聴き、冒頭に流れるバンジョーの響きに惹かれ、その奏者がリアノン・ギデンズであることを知ります。そこからたどり着いたのが、「リアノン・ギデンズとバンジョーの歴史を掘り起こす:アフリカン・ルーツからアメリカン・ミュージックへ」という動画(YouTubeへ)。さらに資料を補足しながらバンジョーの歴史を探っていくと……。
アフリカからアメリカに連れられてきた黒人奴隷によって、ひょうたん楽器「ゴード・バンジョー」がカリブ地域でたくさん作られたこと。また、そのルーツの一つとしてアフリカの「アコンティング」という長いネックを持つ弦楽器があることなどが明らかになります。
ゴード(gourd)とは英語でひょうたんのことです。「アコンティング」はakoting、日本ではカタカナで「エコンティン」と表記されることもあり、西アフリカのセネガルやガンビアに住むジョラ族の伝統的なひょうたん楽器です。私はずっとバンジョーのルーツは西アフリカのひょうたん楽器「コラ」だと思っていたのですが、「アコンティング」などいくつかの楽器や、「リュート」など西洋楽器の特徴が入り混じり、クレオール化して生まれた楽器なのだということが、この本を読んでよくわかりました。
そのように、もともと黒人たちの楽器であった「ゴード・バンジョー」が、19世紀のミンストレル・ショウなどを経て白人の弾くものになり、一般化していったこと。そして、ひょうたんから別の素材へと変わっていったことが、わかりやすい文章で記されています。
ああ、そうだったのか!バンジョーよ!
細馬さんのページを読んでから、私はバンジョーとカントリー・ミュージックを急に身近に感じてしまい、他のページもがっつりと読みました。すると、第1章のインタビューにもひょうたんが登場しているのを発見!
それは、ハンナ・メイリー(Hannah Mayree)というミュージシャンで、かつ「Black Banjo Reclamation Project」の主宰者である黒人女性のインタビューでした。直訳すると「バンジョーを黒人の手に取り戻すプロジェクト」。彼女は実際にひょうたんを育てて、収穫したひょうたんからバンジョーを手作りするというワークショップまで開催しているそうです。
ハンナ・メイリーさんによると、バンジョーはもともと黒人にとって神聖な楽器であったといいます。
余談ですが、先日、我々「ヒョータニスト・パーティ」のライブをさせていただいた大阪・内本町の「マルコノスタルジ」では、たまたまその日、カリブの宗教音楽の練習をしていました(「ひょうたん日記」1277日目)。お店の方によると、アフリカから強制的に連れてこられた人たちが、カリブではマリア様を拝むふりをして、自分たちの信じる海の女神を拝んでいたというのです。「隠れキリシタンの逆パターンですよ」とのことでした。このような状況で生まれたカリブの宗教音楽には、「ゴード・バンジョー」が使われていたのではないでしょうか?
「Black Banjo Reclamation Project」をネットで検索してみると、なんとホームページに栽培中のひょうたんの花やタネ、くびれのない丸いひょうたんを二つ割りにして作ったバンジョーの写真などがでてきました! しかも、この会のシンボルマークは、「ゴード・バンジョー」にひょうたんの蔓と葉がからんだデザインです。
いやー。たまらん。感激で涙が出そうです。
細馬先生、素晴らしい本を書いてくださり、またご紹介くださいまして、ありがとうございました!
(1284日目∞ 2月20日)
「でれろん暮らし」でも奥田亮さんが「ひょうたんバンジョー」について書いています。
※次回1285日目の丸黄うりほ「ひょうたん日記」は2月26日(水)にアップします。2月24日(月・祝)の奥田亮「でれろん暮らし」はお休みです。