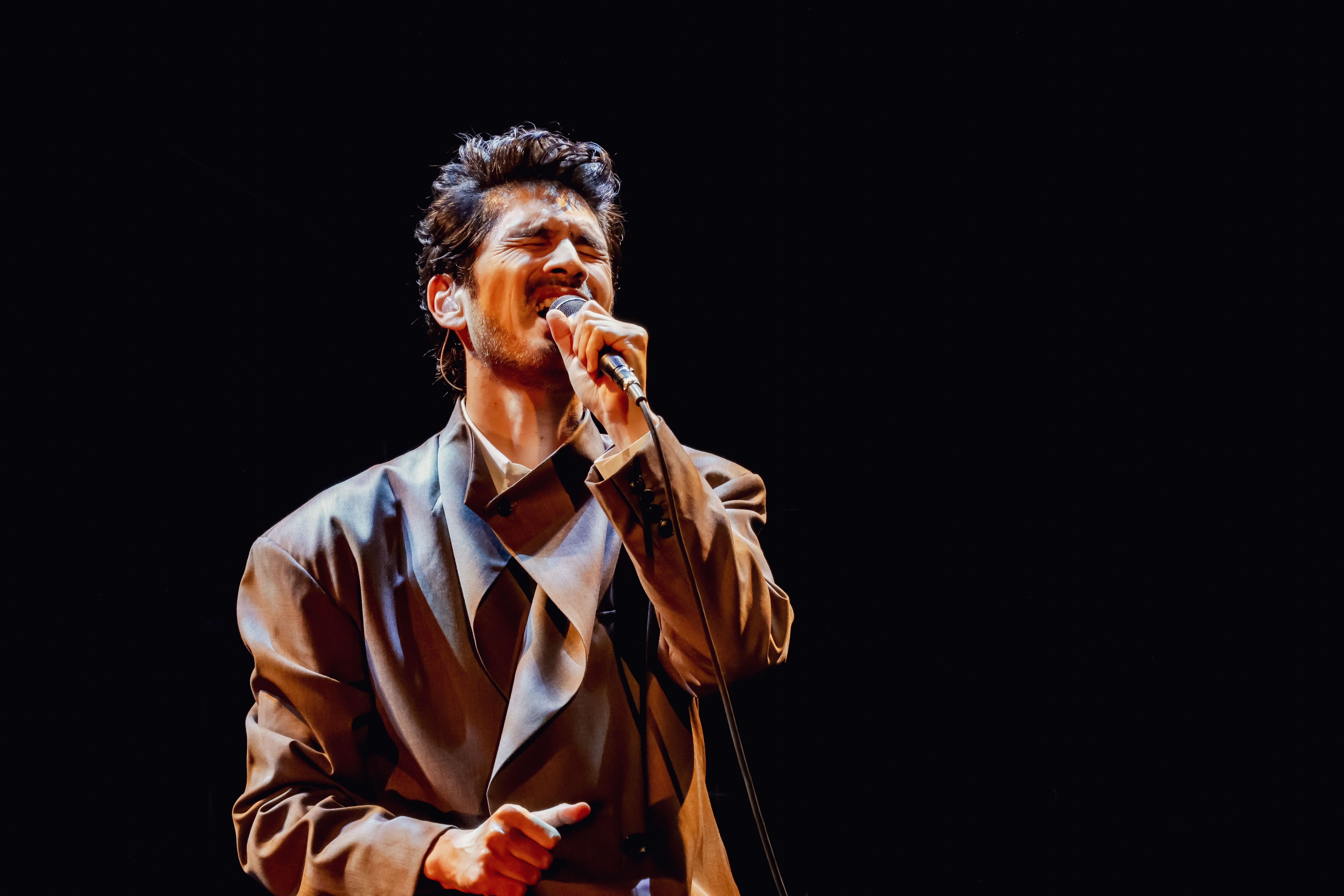なんだかひょうたんが喜んでいるような声に聞こえます。
by 奥田亮

6種類の弦が揃いました。
先週からの続き、《瓢立琴》のメンテ・改良の最終段階です。先週までにだいたいのパーツの修理、改良は済み、あとは弦を張って音を出すのみというところにきて、弦がないことに気づいてポチったところで終わっておりました。
使っている弦は、建築用の「純絹坪糸」という糸。ずいぶん前にホームセンターで何か弦になるものはないかと物色していて見つけたのでした。坪糸というものがあるということ自体知りませんでしたが、「墨つぼについていて、材木などの面にまっすぐな黒線をつけるのに使う糸」です。きっと昔からずっと使われている方法なのだろうと思います。墨糸とか墨縄とも呼ばれるようです。なぜか素材は絹。三味線やお琴の弦と同じです。これは使えると思ったのでした。しかも長さ15mで200円〜300円程度! ホームセンターで見つけた時は、店頭にあった2種類の太さを買ったのですが、今回ネットで検索すると、もっとたくさんの太さがあることがわかりました。
調べると、約0.2mm〜0.8mmまでの間に10種類の太さがありました。手元にあったのは、0.4mmと0.45mmだったのですが、そこそこ細かったのでもっと太いのを購入することにしました。ということで、0.40、0.45、0.55、0.60、0.70、0.80の6種類が揃いました。これくらいの太さの差があれば、それなりに音の違いがあるのではないかと思われます。
ところでこの坪糸、実際の用途で使っているわけではありませんし、使っている現場を見たこともないのですが、そもそもどうしてこんなに太さの違いが必要なのか、見当もつきません。糸の台紙には「墨付が良く、伸びずに正確な墨打ができる」とあります(「墨打」という言葉と響きにグッときます)。確かに伸びないと墨打が正確というのはわかる気がしますが、太さの違いは何なんでしょう。台紙の裏面には、他の用途として「渓流釣りの糸」「模型帆船の帆張りの糸」と書かれています。この方がまだ、太さの違いが必要なのはわかるような気がします。これからは、「手作り楽器の弦」も用途に加えてほしいですね。伸びないのは楽器の弦としても優れていますから。
閑話休題。さっそく糸を張ってみることにしました。まずは真ん中に一番太い0.8mmを張りました。特製駒をつけて鳴らすと、当然今までよりも低い音が響き、遠くできれいな倍音も響いています。それと、うしろに空けたサウンドホールを手で閉じたり開けたりすると、明らかな響きの差が出るようになりました。ちゃんとひょうたんに音が響いているということなのかなと思います。やはり大きさや形状に合った適正な周波数や音質があるんですね。そういう音を聴くと、なんだかひょうたんが喜んでいるような声に聞こえます。

弦を張っていきます。
勢いを得て7本とも張ってみました。揃えた弦は6種類だったので、とくに必然はないのですが、0.55mmを2本にしました。張って試奏してみると、これまでの《瓢立琴》よりもしっとりとした響きになったように思います。ただ、弦の高さが凸凹していて弾きにくいことがわかりました。真中の駒は意図的に高めにしたのですが、全体にあまりバランスがよくなかったようです。

7本張って駒をつけました。
これからは少しずつ駒の高さや位置、弦の張り具合を調整しながら、音階を定めていくのを楽しみたいと思います。この作業に入ると、そのこと自体が面白くて「曲」というところにまで意識が向かなくなるのですが、これまさに「音」「楽」、音を楽しむ以外のなにものでもないのです。でれろん。
(1282日目∞ 2月17日)