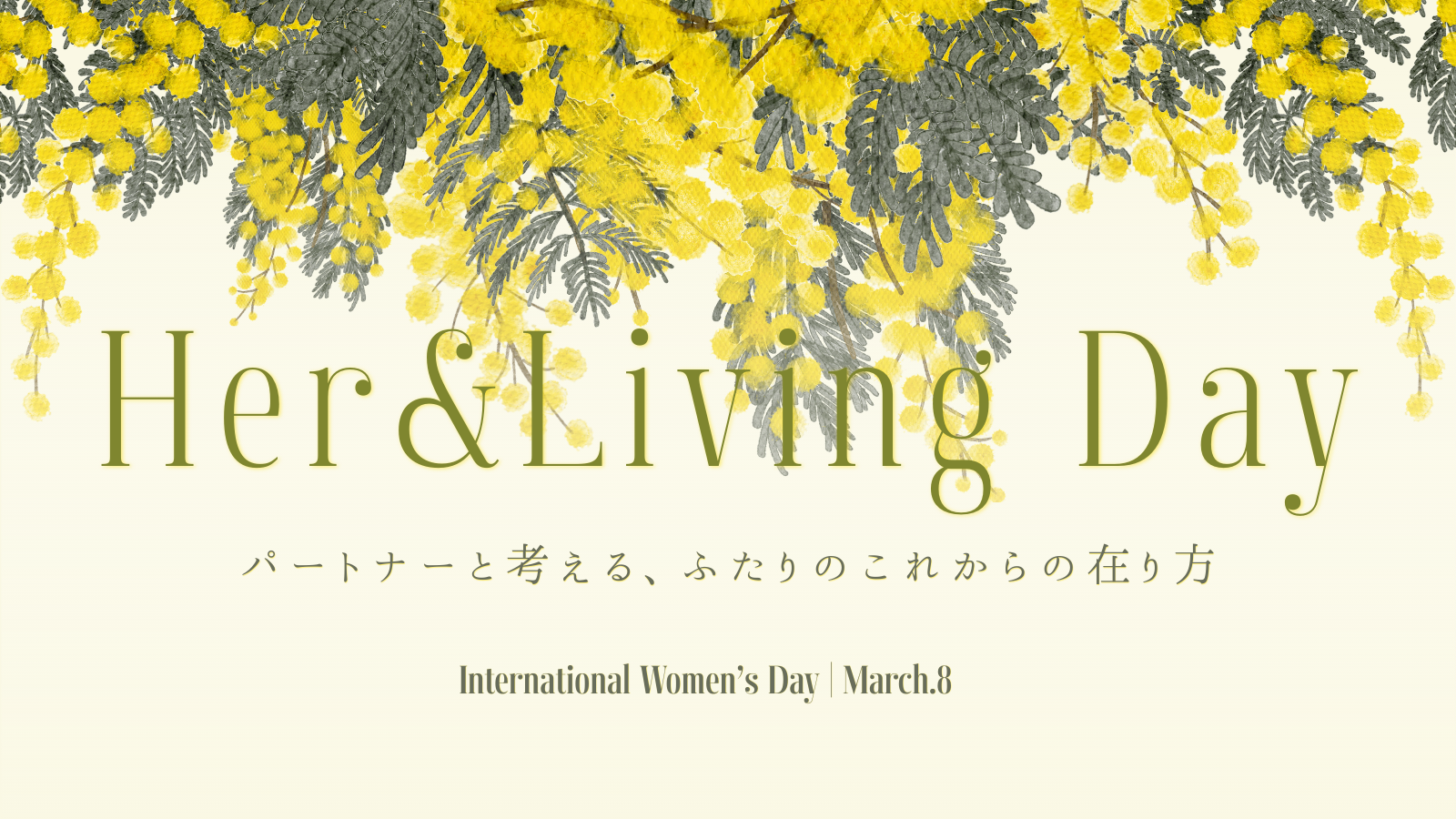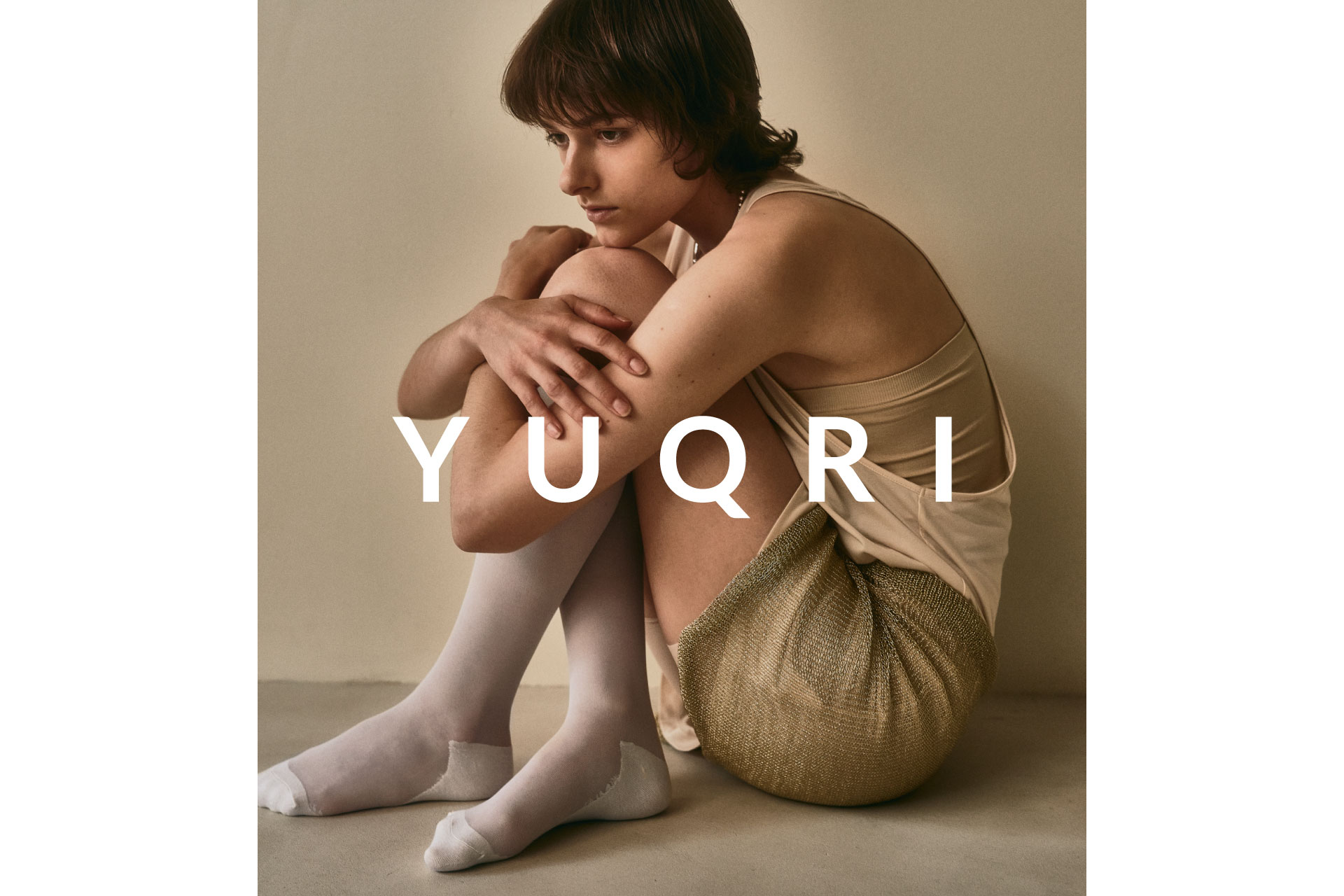とりあえずはこれで良しとしようと思います。
by 奥田亮

《瓢立琴 銘 剥き身》ビフォー。
昨年末、新楽器《芳一》の改良がうまくいかなくて頓挫したついでに、いくつかの楽器のメンテについてご報告しておりましたが(12月2日のでれろん暮らしへ)、なかなか実行に移すまでには至っておりませんでした。それが、ハリー・パーチの話題などが出てきた流れで、ようやく楽器づくりに意識が向き始め、どっこらしょと重たい腰が上がりましたよ。まあ、寒いのを理由にしてもいたのですが、部屋を暖かくしてなんとかやり始めました。じつは今年に入って、密かに(?)レコーディングをやってみたりもしたのですが、どの楽器もどこかが壊れていたりで、レコーディングしようにも、まともな楽器がほとんどないやんか、という状態だったことも、腰をあげた理由でした。懸案になっていたのは《瓢立琴》。琴柱が散逸していたのと、心棒がまっすぐに立っていなくて不安定だったのを修復する必要があったのです。
まずは、面倒な心棒を垂直に立てる方からやっつけることにしました。心棒と底板が直角になるよう線を引いてみると、やはりけっこう斜めになっています。楽器全体の高さは、短くなってもとくに問題はないので、少し多めに切ってしまうことにしました。

歪みを直すべく、心棒が垂直に立つように底を斜めに切断。
切って中を見てみると、あっそうか、心棒だけでは心許ないので、ひょうたんと心棒を固定するために木片を噛ませていたのでした。なるほど、そういうことか。もうどうやって作ったのかも忘れておりました。

中には木片が噛ませてありました。そうだったんだ。
さらにこの底板の正面には、弦を留める穴をあけ、少し多めにはみ出させています。そして長瓢自体、天然自然の形をしていることもあって、心棒を通す穴は底板のセンターというわけにはいきません。意外とトリッキーなことをしてるんですよね。既存の穴を利用しつつ、多少調整しながらなんとか心棒を通すことができました。

底板だけでは安定しないかもしれないので、木片を追加。
このままでもなんとかなるのかもしれませんが、弦の張力はあなどれません。もう一枚太めの木片を噛ませることにしました。なんとかうまい具合に底板がはまったので、接着剤で固定して一応作業は完了したのですが、見てみると、ん? どうも思ったほどは垂直になってない…。しかも今度はちょっと横に倒れています。でも、まあ最初のものよりは安定しているので、とりあえずはこれで良しとしようと思います。不定形は円柱を斜めに切るのはけっこう難しいですね。まあ、私の技量はこんなもんです。ホントに適当なんです。

《瓢立琴 銘 剥き身》アフター。横から見たところ。やっぱり前のめり。

さらに横にも倒れてる。まあいいか。
さて、次は散逸した琴柱の作りかえです。ここからはまた長くなりそうなので、続きは次回に持ち越したいと思います。さてうまくいきますかどうか。そして、レコーディングはできるのでしょうか、でれろん。
(1276日目∞ 2月3日)
- 奥田亮 ∞ 1958年大阪生まれ。中学生の頃ビートルズ経由でインド音楽に触れ、民族音楽、即興演奏に開眼。その後会社に勤めながら、いくつのかバンドやユニットに参加して音楽活動を続ける。1993年頃ひょうたんを栽培し楽器を作って演奏を始め、1997年「ひょうたんオーケストラプロジェクト」結成、断続的に活動。2009年金沢21世紀美術館「愛についての100の物語」展に「栽培から始める音楽」出展。2012年長野県小布施町に移住し、デザイン業の傍ら古本屋スワロー亭を営む。2019年還暦記念にCD『とちうで、ちょっと』を自主制作上梓。