
ワーズワースの水仙
武田雅子
この詩はよく知られたもので、英語の教科書にも取り上げられている。
私自身の出会いは教科書ではなかったのだが、中学生の時、いくつかワーズワースの詩を読み、もっと読みたいと思ったものの、その頃は便利な岩波文庫も新書もなく、わかりもしないのに、それほど分厚いものではなかったので、研究書を見つけて購入した。その本には、部分的だが彼のいろいろな詩からの引用があって、それで結構、満足していたように覚えている。

筆者が中学時代に読んだ『ワーヅワス鑑賞』小川二郎著(南雲堂不死鳥選書)。ワーズワースが描かれた栞は近年のもの。
では、まず、作品を見てみよう。
I wander’d lonely as a cloud
谷を越え山を越えて空高く流れてゆく
That floats on high o’er vales and hills,
白い一片の雲のように、私は独り悄然(しょうぜん)としてさまよっていた。
When all at once I saw a crowd,
すると、全く突如として、眼の前に花の群れが
A host of golden daffodils,
黄金色に輝く夥(おびただ)しい水仙の花の群れが、現われた。
Beside the lake, beneath the trees
湖の岸辺に沿い、木々の緑に映え、そよ風に
Fluttering and dancing in the breeze.
吹かれながら、ゆらゆらと揺れ動き、躍っていたのだ。
Continuous as the stars that shine
夜空にかかる天の川に浮かぶ
And twinkle on the milky way,
燦(きら)めく星の群れのように、水仙の花はきれめなく、
They stretch’d in never-ending line
入江を縁どるかのように、はてしもなく。
Along the margin of a bay:
蜿蜒(えんえん)と一本の線となって続いていた。
Ten thousand saw I at a glance
一目見ただけで、ゆうに一万本はあったと思う、
Tossing their heads in sprightly dance.
それが皆顔をあげ、嬉々として躍っていたのだ。
The waves beside them danced, but they
入江の小波(さざなみ)もそれの応じて躍ってはいたが、さすがの
Out-did the sparkling waves in glee:-
燦めく小波でも、陽気さにかけては水仙には及ばなかった。
A Poet could not but be gay
かくも歓喜に溢れた友だちに迎えられては、苟(いやしく)も
In such a jocund company!
詩人たるもの、陽気にならざるをえなかったのだ!
I gazed – and gazed – but little thought
私は見た、眸(ひとみ)をこらして見た、だがこの情景がどれほど豊かな
What wealth the show to me had brought.
恩恵を自分にもたらしたかは、その時には気づかなかった。
For oft. when on my couch I lie
というのは、その後、空しい思い、寂しい思いに
In vacant or in pensive mood,
襲われて、私が長椅子に愁然として身を横たえているとき、
They flash upon that inward eye
孤独の祝福であるわが内なる眼に、しばしば
Which is the bliss of solitude;
突然この時の情景が鮮やかに蘇るからだ。
And then my heart with pleasure fills
そして、私の心はただひたすら歓喜にうち慄(ふる)え、
And dances with the daffodils.
水仙の花の群れと一緒になって躍り出すからだ。
(平井正穂編『イギリス名詩選』岩波文庫)
教科書に採用されているくらいだから、それほど英語は難しかったり、詩としての特殊な書き方がされているわけではない。原詩で読みたいという人のために、少しだけ最後に注意点をあげておいた(*)。
また、内容としても、心に憂いを抱えてさまよい歩いているとき、ふっと花の群れに出会って救われるという、誰でも経験したことがあるささやかな出来事なので、共感しやすい。これも、教科書に採られている理由だろう。留意すべきは、この時のことをそれからしばらくたって思い出しているということで、回想というのは、この詩人の他の作品においても、しばしば取り上げられる重要ポイントであるということ。そして、孤独は1行目(訳では2行目)にあるように「悄然と」したものであるが、また最後にあるように「内なる眼」という祝福を授けてくれるものでもあるということである。
中学生のときこの詩に出会い、響きも美しく、行の最後の音も、1,3行目、2,4行目、そして締めくくるように、7,8行目と続いて、韻を踏んでいるので、一生懸命暗唱したものだが、孤独に悩む年ごろに、「内なる眼という孤独の祝福」という言葉に知らず知らずのうちに支えられていたように思う。詩を暗唱すると、フレーズを何度も繰り返すことになり、自分の中に蓄積されていったのだといま思い返している。
一口に水仙と言っても…
岩波文庫に、「題名は作者がつけたものではなく、一般に呼びならわされているものに従った」とあるように、“The Daffodils”(水仙)というのはワーズワースのつけた題ではない。そして、水仙と聞くと多くの日本人は、芯の黄色い、白い花びらの楚々とした花を思い浮かべるだろう。しかし、この花は、「黄金色に輝く」とあるように、ラッパ水仙である。
日本の水仙は、生の花ではなく作り花なのだが『たけくらべ』の最後に登場し、「寂しく清き姿」と描写され、儚い恋の象徴として強い印象を残す。鏑木清方の絵で、一葉女史の墓を訪う、主人公の美登利もこの水仙を手にしている。それからしたら、この詩の花は、陽気に嬉々として踊るのだから、これはまったく違う風情である。

イギリスの雑誌『Victoria』(March,1993)に紹介されていた、湖水地方のスイセン。
私だって詩を書く
この詩はワーズワースが妹ドロシーと散歩しているときに実際にこのような風景に出会ったことが、ドロシーの日記によりわかっている。そしてまた、先に触れたように、後になって、つまり2年後に詩を書いたことも、書き残されている。このように彼女の記録は、ワーズワース研究に欠かせない資料であり、日常生活においても、兄のために家事を引き受け、身の回りの世話をし、彼の結婚後は子どもたちの面倒を見た。と、いかにも女らしい女性として、ドロシーは紹介されてきた——男性の先生によってクラスで、男性の研究者の本の中で。
今回、詩人についてのDVDを見ていて、「妹ドロシーと妻は、彼の詩を清書して、彼に尽くし……」という箇所で、思わず吹き出してしまった。学生時代は、女性らしさとはそんなものという流れの中に身を置いて何も感じていなかったが、やがて私たちはフェミニズムの嵐に見舞われ、違う見方を与えられたからである。
嵐といわれたように、一時は極端なところまで行ったりしたが、この嵐は文学の世界にも当然押し寄せ、さまざまな見直しが行われた。私自身は、それほどその嵐に吹かれたわけではなかったが、アメリカのフェミニストの社会学の教授と話していて、「私は自分がフェミニストとは思わないけれど、フェミニストの主張にはなるほどと思うことが多い」と言ったところ、「女性ということは生まれながらにフェミニストなのよ」と返されて、目からうろこの思いがしたものであった。
過去に、女性の芸術家が数少ないのは、彼らに才能がないからではなく、黒人の芸術家が少ないのと同じで、その機会が閉ざされていたからだった。『ジェイン・エア』と『嵐が丘』のブロンテ姉妹も、男性名でしか作品発表できなかったし、ジョージ・エリオットもジョルジュ・サンドも奇しくも、同じ男性名Georgeの英語読みとフランス語読みで世に出たのだった。隠れていた女性詩人もいたということで、英米のロマン派やヴィクトリア朝の女性作家や詩人の作品が発掘され、私も友人と『ロマン派英米女性詩人選集』というテキストを編んだりした。
その中に、このドロシー・ワーズワースの作品も取り上げた。そう、彼女もお手伝いばかりしていたのではなく、自身も詩を書いていたのである。ただ、本人は詩人だとは思っていなかったということだし、作品自体もそれほど強い魅力をもったものではない。しかしそれも、女性はひたすら男性を裏で支えるべきだというのではなく、自身が詩人を目指すという生き方も選択肢としてあったというなら、ことは違ったかもしれない。
ジャマイカからイギリスは遙かに遠く、日本からも…
最近は、月一歌舞伎や、Met Live Viewingなど、第一級の舞台を録画した映画を見ることができるようになった。実際の舞台の最高の座席ですら望めないというクローズアップなども楽しめる。ロンドンのナショナル・シアターの演劇プログラムもその一つで、『スモール・アイランド』という作品を、まったく予備知識なしに、ただナショナル・シアターだから悪かろうはずはないというだけで見に行った。

ロンドンのナショナル・シアターで上演された『スモール・アイランド』のパンフレット
主人公はジャマイカの女性で、1948-71年のウィンドラッシュを描いた物語で、2004年に発表されたアンドレア・レヴィの小説(イギリスで最も権威ある賞の一つオレンジ賞を獲得)を劇化した作品である。当時、ジャマイカをはじめ西インド諸島はイギリス領で、人々はよりよい生活を心に描いて、イギリスに移民したのだった。
アメリカの友人のご主人で、ハーヴァードの高名な教授がジャマイカ出身であることくらいしか、私自身ジャマイカに縁はなく、ラムレーズンのアイスクリームが大好きなので、ラム酒を買ったら、ジャマイカが原産地とあって「へーえ」と思ったくらい無知だった。このウインドラッシュについてもまったく知らなかった。しかし、かつて日本からも安い労働力として、アメリカやブラジルへ人々が渡っていったことがあり、成功した者もいるだろうが、多くは苦難の道を歩んだことは想像に難くない。
主人公は、先にイギリスに向かった婚約者に呼び寄せられてロンドンにやってくるが、理想とあまりにもかけ離れたみすぼらしい部屋に驚く。そして教師として働こうと夢見ていたが、ジャマイカで得た資格は通用しないと、ここに来て初めて悟らされショックを受ける。
Black Lives Matter(黒人の命は大事だ)はアメリカから始まったが、イギリスでの黒人差別もこの当時すでに、はなはだしかった。誇り高い白人のイギリス人の誰が、黒人に英語をイギリス文学を習うというのか。自分を待ち構えている差別を知らず、主人公が、詩だって暗唱できると口ずさむのが、このワーズワースの作品であるところが、痛々しい。
そして思いめぐらしてみれば、そのせつなさは私にも返ってきて、身につまされる。今から50年前の私の学生時代、それから何年間かにわたって、英文科に行く女子大生は多く、かといって、文学者になる道を目指しているわけではなく、英語を使って実務に就く者も少なく、教養をつければよいということだったのではないだろうか。そして、私自身もその一人でなかったか……。
流れるような心地よい訳
この詩を、『海潮音』の上田敏に師事し、大正昭和に活躍した竹友藻風(1891-1954)が訳しているので、出だしと最後をのぞいてみると——
谷と小山の上高く 漂(ただよ)ふ雲のわれひとり
迷ふ行手に見し群は 黄金の色の水仙花
…
よろこび表(うち)にみち渡り 舞ふや心と水仙花
声に出して読んでみるとなんと耳に心地よいことだろう——それは、この訳が五七調でできているから。前出の訳では、英語の学習のためもあって、見比べてわかりやすいように、できるだけ原文の英語に近く日本語を並べてある。それからしたら、この訳は、多少意味や語順は犠牲にしても、5音と7音で訳されている。それは、日本語訳を読んでも、そこに「詩」が感じられることを意図したためである。
和歌、そして短歌、また俳句をもっている私たち日本人の耳は、5音と7音のつながりを聞くと、そこに「詩」を感じる。一方、英詩は、リズムと韻で成り立っていて、それを音に出してみると、そこに「詩」を感じる。だから、彼らの詩を、日本語の訳で読んでも詩と感じさせるためには、五七調で訳せばよいということになる。英語の響きに身をゆだねて気分がよいように、五七調もまことにいい響きを醸し出す。
それでは、これが万能かというと、悲しいかな、そうは簡単には行かない。五七調は、和歌の世界を思わせるために、典雅ではあるが、古めかしさももたらす。ワーズワースは、1770-1850年の人だから、もう今では、古めかしさも出てもいいかもしれないが、50年前に、この訳を読んだとき、やはり古いという感はぬぐえなかった。
この詩は、自然と出会って抱く感慨を描いているという点で、日本古来の和歌と相通ずるものがあるから、それほど違和感がないかもしれない(これはこれで、本来違う面も多いのに、似ている面ばかりが強調されてしまうことになるという危険性がある)が、たとえば、現代のスラムを描いた詩は五七調では訳せないのである。
もっとも、英語の現代詩は、リズムも破格で韻も踏まないということも多いから、現代の日本語でそのまま訳すということになるのだが。とはいえ、歌の歌詞などは、規定どおりの伝統的形態をとっているので、リズムと韻による「詩」は、日本語にすると、どうも散文的になってしまうという問題は常にある。
詩人はワルツを踊る
さて、その英語のリズムの一例が、この詩の最後に出てくる。この詩は“dances with the daffodils”(水仙と共に踊る)で終わる。ここで、詩人が踊るのはワルツではないかと、私は思っている。この英語を発音してみると、dan-ces-withthe-daffo-dil-s ● • • ● • • というリズムを踏むことになり、大きな●に当たるところは、“dan”と“daffo”と同じ重い[d]の音の繰り返しで、リズムがより強調される。3拍子のダンスは他にいろいろあれど、やはりここはオーソドックスにエレガントにワルツでいきたい。
素直に心を
この詩から、フェミニズムやら、文化の不平等性やら、「詩」の翻訳やら、あちこち話が飛んでしまったが、改めて詩を読み直して、素直に心に入ってくることに打たれた。ワーズワースといえば、コールリッジとともにロマン派の嚆矢と文学史で習い、さまざまに意味づけされてきた。ごく大さっぱにいうと、ワーズワースの時から、感情を素直にそのまま歌うようになったということで、私たちは、つくづくその流れの中にあるのだという思いを強くしたのである。そして、一方で、また新たにワーズワースを見直さなければならないのだとも。この詩も自然と人間の関わりが扱われ、ワーズワースは自然詩人といわれてきたのだけれど、環境破壊の危機のいま、自然についても考え直さなければならないのだから。
(11/25/2020)
(*)原詩を読むにあたって
- 動詞wander、stretchは過去形になると“-ed”が着くのだが、音数の関係で、“e”が省略されて、’のしるしがついている。
- 2行目の“o’er”の場合は、省略されているのは“v”で、元の形は、“over”となる。
- 4行目の“a host”は、前の行の最後“a crowd”を言い換えたもので、同じ「群れ」という意味だが、前者の方が、兵隊さんが並んでいる感があり、この微妙なところが工夫のしどころ。
- 11行目は普通の語順で主語・動詞・目的語にすると“I saw ten thousand”となり、
- 最後から2行目は、普通の語順にすると“my hear fills with pleasure”となる。
- 15行目は“cannot but+動詞”「~せざるをえない」の形、17行目の“little”は「少ししか~ない」。
読書案内

The Poetry of Flowers — A Bouquet of Romantic Verse and Paper Flowers 花が飛び出すポップアップ絵本
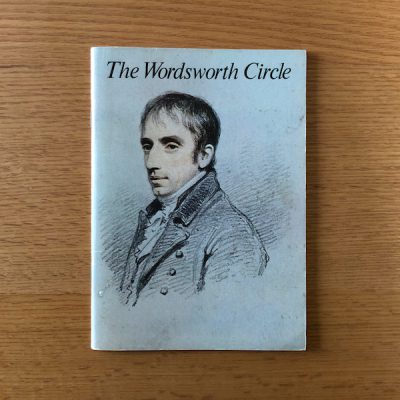
ワーズワース研究の機関誌
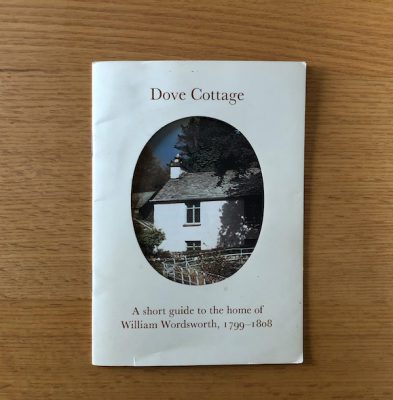
湖水地方にあるワーズワースの家Dove Cottage のリーフレット
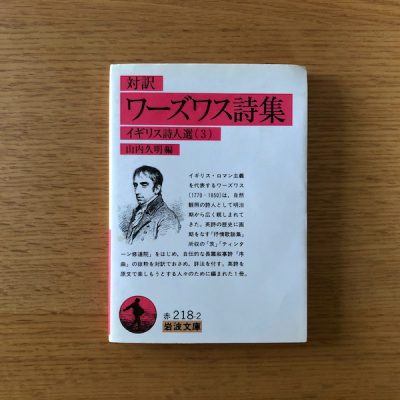
『対訳 ワーズワス詩集 イギリス詩人選(3)』岩波文庫

出口保夫著『ワーズワス 田園への招待』講談社+α新書

『イギリス名詩選』岩波文庫

ワーズワースの詩を朗読したCD(The Great Poets Series)
武田雅子 大阪樟蔭女子大学英文科名誉教授。学士論文、修士論文の時から、女性詩人ディキンスンの研究および普及に取り組む。アマスト大学、ハーバード大学などで在外研修も。定年退職後、再び大学1年生として、ランドスケープのクラスをマサチューセッツ大学で1年間受講。アメリカや日本で詩の朗読会を多数開催、文学をめぐっての自主講座を主宰。著書にIn Search of Emily–Journeys from Japan to Amherst:Quale Press (2005アメリカ)、『エミリの詩の家ーアマストで暮らして』編集工房ノア(1996)、 『英語で読むこどもの本』創元社(1996)ほか。映画『静かなる情熱 エミリ・ディキンスン』(2016)では字幕監修。




















